|
本日は、マリアナの沈み込み帯でどのような電気伝導度構造が得られているのかを、お話しさせていただきます。これは、私が6月までおりました独立行政法人海洋研究開発機構で3年かけて行ってきた研究で、現在も継続しています。
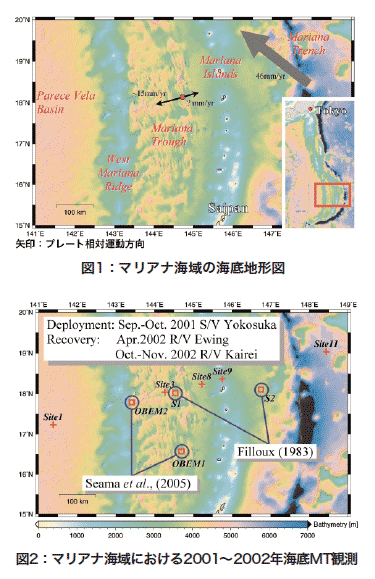 マリアナ海域における電磁気観測 マリアナ海域における電磁気観測
観測を行ったマリアナ海域の海底地形を図1に示します。マリアナ海溝では、太平洋プレートが年46mmの速さでフィリピン海プレートの下に沈み込んでいます。矢印は、沈み込みの方向を示しています。マリアナ海溝の西側にはマリアナ島弧があり、その背後にマリアナトラフがあります。マリアナトラフは現在も拡大を続けている活動的な背弧海盆で、拡大様式は低速で非対称です。東側の拡大速度はよく分かっていませんが、西側の年15mmよりもさらに遅そうだということが、GPS観測や地磁気などの調査から分かっています。マリアナトラフの西側には、かつての火山弧である西マリアナ海嶺、そしてパレスベラ海盆があります。
このマリアナ海域に2001年秋、海底電位差磁力計(OBEM:Ocean Bottom Electromagnetometer)を11台設置し(site 1?11)、半年から1年間の観測を行いました。その結果、site 1、site 3、site 8、site 9、site 11の5点で、海底の電場と磁場の変動データを取ることができました(図2)。この海域では、ほかの観測によって取られたデータもあります。本研究では、2001年の観測で得られた5点と、2005年に得られたOBEM2、1983年に得られたS1とS2を加えた、比較的直線状に並んでいる合計8点のデータを使って、上部マントルの2次元電気伝導度構造を調べました。
MT法により電気伝導度構造を求める
観測によって得られた電磁場変動データをMT(Magnetotelluric)法によって解析することで、海底下の電気伝導度を導き出します。MT法では、各観測点で得られた水平2成分の電場変動(E)と磁場変動(B)のスペクトル間のトランスファー(変換)関数を求めます(図3)。このトランスファー関数をMTインピーダンス(Z)と呼びます。MTインピーダンスが海底下の電気伝導度に関する情報を持っているわけです。ここでは、X軸は拡大軸に平行な方向、Y軸は拡大軸に垂直な方向に取ってあります。MTインピーダンスはテンソル量になっていて4つ成分がありますが、2次元構造が卓越している場合、XXとYYの対角成分は非常に小さく、XYとYXの非対角成分が主要な成分になります。電流がXの向き、つまり拡大軸に平行方向に流れる場合を「TEモード」と呼びます。また、電流がYの向き、つまり拡大軸に垂直方向に流れる場合を「TMモード」と呼びます。
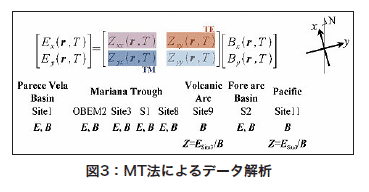 このようにして得られたデータをインバージョン(逆解析)して電気伝導度構造をモデル化するのですが、その前に海底地形の効果を補正します。海水はその下の地殻に比べて高伝導度なので、海底面が大きな電気伝導度境界になっています。海底地形の凸凹がデータに影響するため、まず海底地形の影響を取り除き、得られたデータをインバージョンします。TEモードのみのデータをインバージョンした場合と、TMモードのみをインバージョンした場合、両方を同時にインバージョンした場合の3通りの解析を行っています。 このようにして得られたデータをインバージョン(逆解析)して電気伝導度構造をモデル化するのですが、その前に海底地形の効果を補正します。海水はその下の地殻に比べて高伝導度なので、海底面が大きな電気伝導度境界になっています。海底地形の凸凹がデータに影響するため、まず海底地形の影響を取り除き、得られたデータをインバージョンします。TEモードのみのデータをインバージョンした場合と、TMモードのみをインバージョンした場合、両方を同時にインバージョンした場合の3通りの解析を行っています。
図4と図5が、得られた電気伝導度構造のモデルです。それぞれの図の上に描かれているのは、測線に沿った海底地形です。赤い矢印が、拡大しているマリアナトラフです。その東側には島弧とマリアナ海溝があり、そこから東が太平洋プレートになります。三角形は、観測点の位置を表しています。横軸は拡大軸からの距離、縦軸は350kmまでの深さを示しています。赤色が電気伝導度の高い領域、青色が低い領域です。
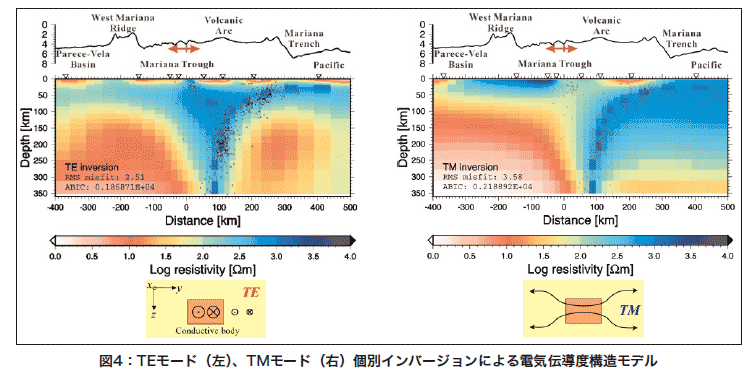
図4左は、TEモードのデータのみインバージョンしたモデルです。これは、拡大軸と平行方向の電気伝導度だと考えることができます。それに対して図4右はTMモードのみをインバージョンしたモデルで、拡大軸に垂直方向の電気伝導度の構造になっています。
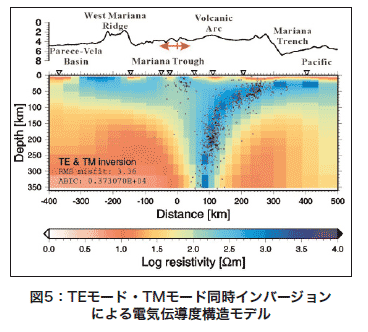 もしマントルが等方的な電気伝導度を持っていたとすると、両者は理想的には同じようなモデルになるはずです。二つのモデルに共通している特徴は、上が青く、下が赤いことです。点は、震源分布を示しています。そこに沈み込むプレートがあります。実は、MT法のデータは、低伝導度の所にはあまり感度がありません。沈み込むプレートは低温で電気伝導度が低いと考えられるので、震源分布に沿って電気伝導度が低いものがあるという制約を与えています。また両者に共通する特徴として、背弧側のマントルの方が太平洋側より高伝導度である、という結果が得られています。 もしマントルが等方的な電気伝導度を持っていたとすると、両者は理想的には同じようなモデルになるはずです。二つのモデルに共通している特徴は、上が青く、下が赤いことです。点は、震源分布を示しています。そこに沈み込むプレートがあります。実は、MT法のデータは、低伝導度の所にはあまり感度がありません。沈み込むプレートは低温で電気伝導度が低いと考えられるので、震源分布に沿って電気伝導度が低いものがあるという制約を与えています。また両者に共通する特徴として、背弧側のマントルの方が太平洋側より高伝導度である、という結果が得られています。
一方、両者の違いは、背弧側ではTMモードのモデルの方がTEモードのモデルよりも高伝導度である点です。これは、もしかしたらマントルの異方的な構造を表しているのかもしれません。
TEモードとTMモードを同時にインバージョンして得られた電気伝導度モデルが図5です。このモデルでもやはり深度数十kmまでは低伝導度で、その下が高伝導度になっています。しかも、背弧側の方が太平洋側より高伝導度であるというモデルが得られています。
電気伝導度変化の要因
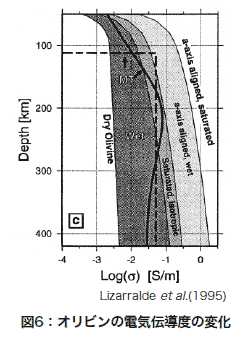 電気伝導度がどのようなパラメータによっているかというと、第一義的には温度が効いています。高温になると高伝導度になります。また、部分溶融(メルト)があり、しかもメルトがつながっていると、高伝導度になります。鉱物中では、水素イオンが拡散することで電気を運びます。そのため、鉱物中に溶解した水素イオンがたくさん含まれている、つまり水の量が多い鉱物ほど高伝導度になります。また、水素イオンの拡散速度は、鉱物の結晶軸の方向によっても異なることが実験から分かっています。もし、マントル対流などによって鉱物の結晶軸が並んでいたとすると、異方的な電気伝導度となって表れます。オリビンはa軸方向の拡散が大きいので、a軸方向に並んでいると高伝導度になると考えられています。 電気伝導度がどのようなパラメータによっているかというと、第一義的には温度が効いています。高温になると高伝導度になります。また、部分溶融(メルト)があり、しかもメルトがつながっていると、高伝導度になります。鉱物中では、水素イオンが拡散することで電気を運びます。そのため、鉱物中に溶解した水素イオンがたくさん含まれている、つまり水の量が多い鉱物ほど高伝導度になります。また、水素イオンの拡散速度は、鉱物の結晶軸の方向によっても異なることが実験から分かっています。もし、マントル対流などによって鉱物の結晶軸が並んでいたとすると、異方的な電気伝導度となって表れます。オリビンはa軸方向の拡散が大きいので、a軸方向に並んでいると高伝導度になると考えられています。
標準的な温度の場合、オリビンの電気伝導度がどのように変化するかを図6に示しました。ドライなオリビンの場合、電気伝導度は0.01S/mよりも低くなります。図4と図5のモデルにおける青色に相当します。そこに、水が入ってウェットになってくると、電気伝導度が1桁から2桁上がります。さらに、結晶がa軸方向に並びかつ水に飽和していると、1S/mを超える高電気伝導度になります。
マリアナトラフと東太平洋海膨の比較
マリアナトラフの背弧側の電気伝導度構造について、東太平洋海膨ですでに得られている電気伝導度構造と比較してみます(図7)。深度数十kmまでが低伝導度で、その下が高伝導度である点は両者で似ています。青い領域は、ドライのオリビンの電気伝導度と同様です。赤い領域は、水がある程度入っている場合の電気伝導度に相当します。
なぜこのような境界ができるかは、次のように解釈することができます。拡大軸の下で部分溶融が生じると、固相中に含まれていた水がメルトの方に抜けてしまい、固相から水がなくなってしまいます。その結果、乾いた鉱物が両側に広がります。部分溶融が進む深さは、60?70kmと見積もられています。その深度と、低伝導度から高伝導度へ変わる電気伝導度境界がよく合っています。つまり、部分溶融による水の再分配を、低伝導度から高伝導度への電気伝導度のパターンが表していると考えられます。
また、東太平洋海膨では、拡大軸に平行な方向の電気伝導度よりも、拡大軸に垂直な方向の電気伝導度の方が高いというモデルが得られています。マリアナトラフでも、ひいき目に見ると似ているように見えます。これは、オリビン結晶のa軸の配列ということで説明できるかもしれません。
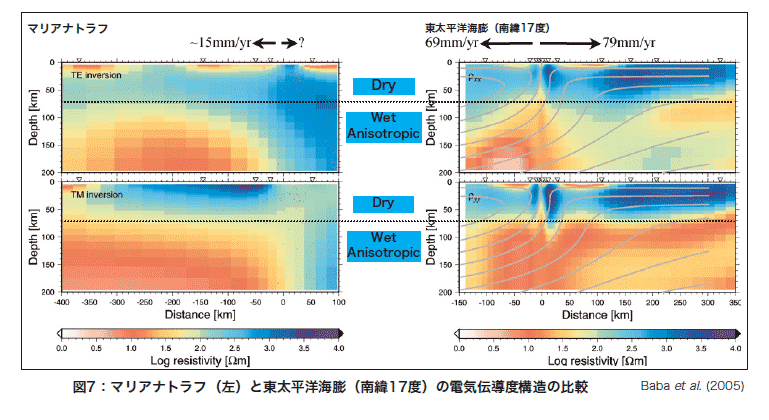
背弧側の電気伝導度は太平洋側の約3倍
次に、マリアナ海域における背弧海盆マントルと太平洋側マントルの電気伝導度の違いを見てみます。背弧海盆マントルは、太平洋側より約3倍も高伝導度です。このデータについて検証を行いました。背弧海盆マントルと太平洋側マントルを同じくらいの電気伝導度にすると、いままで説明していたデータと合わなくなることが分かりました(図8右)。背弧海盆マントルと太平洋側マントルの電気伝導度に3倍程度の違いがあるのは本当らしい、ということが確かめられました。
図8左下はグローバルトモグラフィーの結果で、P波加速度構造です。海の下なのであまり解像度はありませんが、地震波においては背弧側が太平洋側より低速度になっていることが分かります。
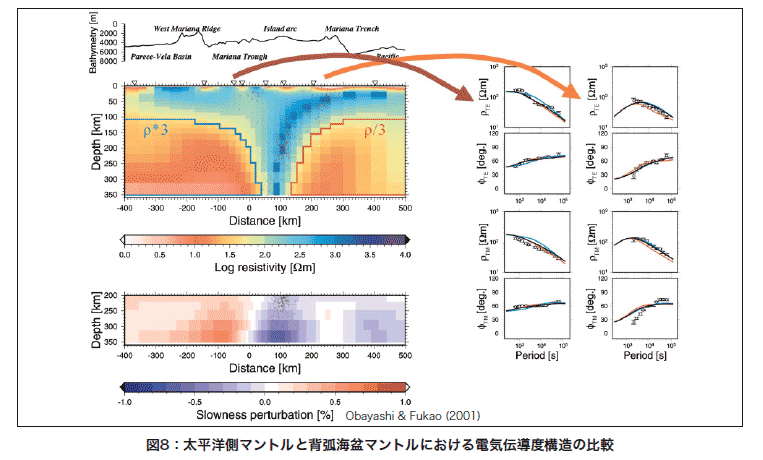
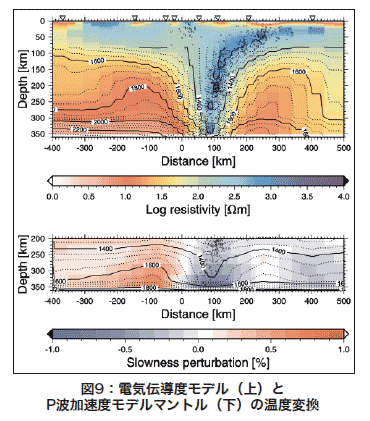 電気伝導度と地震波を市來雅啓らの方法で温度に焼き直したものが、図9です。電気伝導度から求めた温度も、地震波速度から求めた温度も、やはり背弧側の方が約100度高くなっています。しかし、電気伝導度から求めた温度の方が、より高く見積もられています。この違いは、水の量に起因していると思います。P波加速度は鉱物中の溶解した水素イオンの影響をあまり受けませんが、電気伝導度は先ほど言ったように水素イオンの影響を大きく受けるためです。 電気伝導度と地震波を市來雅啓らの方法で温度に焼き直したものが、図9です。電気伝導度から求めた温度も、地震波速度から求めた温度も、やはり背弧側の方が約100度高くなっています。しかし、電気伝導度から求めた温度の方が、より高く見積もられています。この違いは、水の量に起因していると思います。P波加速度は鉱物中の溶解した水素イオンの影響をあまり受けませんが、電気伝導度は先ほど言ったように水素イオンの影響を大きく受けるためです。
まとめ
中部マリアナトラフを横切る海底MT観測によって、太平洋からパレスベラ海盆に至る2次元の上部マントルの電気伝導度構造を推定しました。その結果、背弧側では深さ70kmに低伝導度から高伝導度に変わる境界があり、それは部分溶解による水の再分配で説明できると考えられています。そしてもう一つ、背弧側マントルの方が太平洋側マントルよりも電気伝導が約3倍高い。これは、温度が約100度高いことと、マントルが水を含んでいることで説明できると考えています。
|
 東京大学地震研究所ニュースレター
東京大学地震研究所ニュースレター![]()