大きな地震より小さな地震が多いのはなぜか?
−自ら止まる地震破壊の性質−
亀 伸樹・山下輝夫、科学、68、702-709、1998
地震観測の結果と従来の破壊理論の予測結果は全く正反対になる。理論の立場からは、いったん始まった破壊は非常に止まりにくいことが示される。しかし、観測によるとほとんどの地震はすぐに止まるのが普通であり、大地震にまで成長することはむしろ稀である。見えない地中で地震はどのようにして止まっているのであろうか?
1. はじめに、
2. 地震の力学モデル、
3. 破壊面の形、
4. 形状が自由な破壊のシミュレーション、
5. 自ら止まる地震破壊の性質、
6. 非一様性の「逆」効果、
7. 自然断層の屈曲方向のパラドックス、
8. 断層帯の形成と地震活動、
9. おわりに、
10.文献、
1. はじめに 地震は、地殻内部に発生した亀裂(断層)が弾性波速度近く(2〜3km/秒)で成長する高速破壊現象である。地震には、断層の長さが数百kmに至るマグニチュード(M) 8クラスの巨大地震から、数m以下(M0以下)の微小地震までが存在する。大きい地震と小さい地震の発生数の違いをみてみよう。観測によるとマグニチュードが1大きくなるごとに発生地震の数は約1/10に減ることがわかっている。この関係は発見者の名前よりグーテンベルグ・リヒター公式と呼ばれている(文献1)。マグニチュードが4違う場合、例えば、M3とM7の地震(断層長さはそれぞれ0.4kmと40km程度)では、地震発生個数の比は10000対1になる。すなわち地震というものは小さいマグニチュードのものが圧倒的多数を占め、大きな地震はほんの少数であることがわかる。このような実際の地震の起き方をみる限りでは、地殻内部の破壊はいったん成長を始めてもすぐに止まってしまうことが普通で、大きくなるほうが難しそうにみえる。
我々の破壊現象に対する感じ方は、おそらくこれとは正反対であろう。例えば、ガラスの板を両端から力をかけて割ってみると、割れ目が一気にガラス板を横切る破壊ですべてが終了する。この場合、ガラスは引き裂かれて破壊する。我々が普段目にする破壊はこの引っ張り破壊である。これに対して地震の場合は、圧縮応力が作用する中で互いにずれる方向で物が壊れるいわゆる剪断破壊である。岩石を用いた剪断破壊の実験には強力な加圧装置が必要になる。10cm程度の岩石試料で実験を行うと、いったん破壊が始まるとあっと言う間に試料全体が壊れてしまう。剪断破壊の停止を見るためにもっと大きな岩石破壊の実験をしたいところであるが、装置の大きさの制約から現状では不可能である。
破壊力学理論は、亀裂がどのように成長を始めるかということについて多くのことを明らかにしてきたが、いったん成長を開始した亀裂が、どのように自然に停止するのかということについては未解明のままである。しかし、地震破壊がどのように停止するかということを定量的に理解することは、地震の規模の予測の観点からも重要な課題である。この解説では、筆者らの地震破壊シミュレーションの研究から明らかにされた、従来の考え方とは全く異なる地震破壊の停止機構について述べたい。
2. 地震の力学モデル
これまでの破壊力学の立場から地震破壊現象を考えてみよう。破壊力学というのは特に亀裂の先端に注目して、先端がこれから成長するのか否かを力学的に決定する理論である。地震破壊は弾性体中にある剪断型の亀裂が高速に成長することによって蓄積した弾性エネルギーを解放する過程としてモデル化される。理想化された状況として、亀裂の出現前に媒質の各点に作用している剪断応力(これを以下、初期応力と呼ぶ)、及び、破壊強度の分布が場所によらず一様であるようなものを用意する。なお、剪断応力とはずれを起こそうとする応力であり、初期応力は、亀裂のはるか遠方で媒質に加わっている応力により生ずるとする。この媒質中に剪断型の亀裂が出現し、成長を始める前の状態をまず想定しよう。この亀裂の作り出す剪断応力は図1のようになることがわかっている。亀裂面上では既にずれが生じているので剪断応力は初期応力より低下している。一方、亀裂の先端では剪断応力の集中が見られる。この応力の集中の度合いは、亀裂の長さと亀裂面上で解放された応力の大きさ(応力降下量)に比例する。破壊現象はこの亀裂先端での応力集中の度合いと媒質の破壊強度の観点から記述される。この段階ではまだ亀裂先端での応力集中は媒質の破壊強度を越えておらず、亀裂は静止したままである。この状態から先、次第に遠方で加わっている応力が増すと亀裂先端の応力集中が媒質の破壊強度を越える時が来る。これが地震の始まりである。
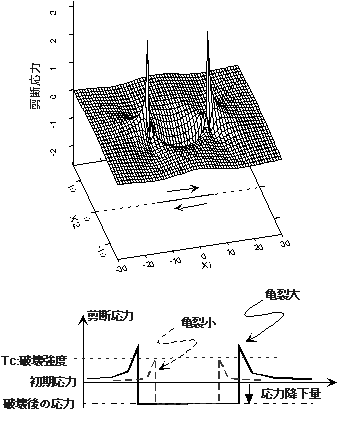 図1:亀裂によって引き起こされる剪断応力の変化。亀裂面上でずれが生じ、剪断応力が低下すると仮定する。なお、このようなずれを「右ずれ」と言い、逆方向のずれ(二つの矢印の方向が逆になったもの)を「左ずれ」と言う。
図1:亀裂によって引き起こされる剪断応力の変化。亀裂面上でずれが生じ、剪断応力が低下すると仮定する。なお、このようなずれを「右ずれ」と言い、逆方向のずれ(二つの矢印の方向が逆になったもの)を「左ずれ」と言う。
上のような状況下でいったん破壊が始まると亀裂の成長は急激に加速され弾性波速度(2〜3km/秒)程度で伝播するようになり、そのまま永遠に停止しないことが破壊力学により示される。応力集中は、亀裂の長さに比例するから、亀裂の成長とともに、どんどん増していく。破壊が開始する時の応力集中がちょうど破壊強度と等しかったわけであるから、成長開始後、亀裂先端の応力集中が破壊強度を下回ることはない。こうして、初期応力と破壊強度分布が場所によらず一様な場合、破壊が止まることがないことがわかる。
従来、地震破壊の停止は、初期応力と破壊強度の分布の非一様性から説明が試みられてきた。以下、この二量を破壊パラメタと呼ぶ。そもそも応力の加わっていない領域にまで亀裂先端が達すると、亀裂が進展しても応力が解放されなくなり破壊は止まりやすくなる。これは実際、プレート境界で発生するような巨大地震の場合に当てはまる可能性はある。この場合、応力が十分加わっている領域全体を破壊しつくして止まることになる。しかし、これは地震破壊の停止機構のうちのほんの一部であろう。大地震発生前の十分広範囲に高い応力が加わっている場合にもなお、ほとんどの地震は小さいままで止まっているからである。次に破壊強度の非一様性の観点から破壊の停止を考えてみよう。破壊強度が局所的に高く亀裂が進むことができない領域はバリアーと呼ばれている。前に述べたように、亀裂先端の応力集中の度合いは亀裂の長さに比例して大きくなるので、大きく成長した亀裂ほど、その停止に強いバリアーが必要になる。過去の定量的な研究の結果、ある程度より大きくなった亀裂を止めるには現実的でない程の破壊強度が必要になることが明らかにされた(文献3)。このように、従来の力学モデルでは未だに地震破壊の停止を説明することができないのである。
3. 破壊面の形
これまでの地震破壊の力学モデルでは、暗黙のうちに、破壊はまっすぐに成長すると仮定してきた。これには大きく2つの理由がある。1つには、地震断層は大まかにみると直線的な構造をしていて、地震破壊のモデル化の第一歩としては十分良い近似になっていたのである。実際、破壊停止現象を除けばまっすぐな破壊成長のモデルでほとんどの地震現象の説明がついてきた。もう1つは、数学的な難しさから破壊の成長方向がまっすぐなモデルでしか高速破壊のシミュレーションができなかったからである。まっすぐに破壊が進むという暗黙の拘束条件の下、破壊パラメタの非一様性の観点から地震破壊の停止を理解しようとしたが、うまくいかなかった。これは、破壊の停止を考えるのに破壊パラメタの非一様性だけでは不十分であることを意味している。
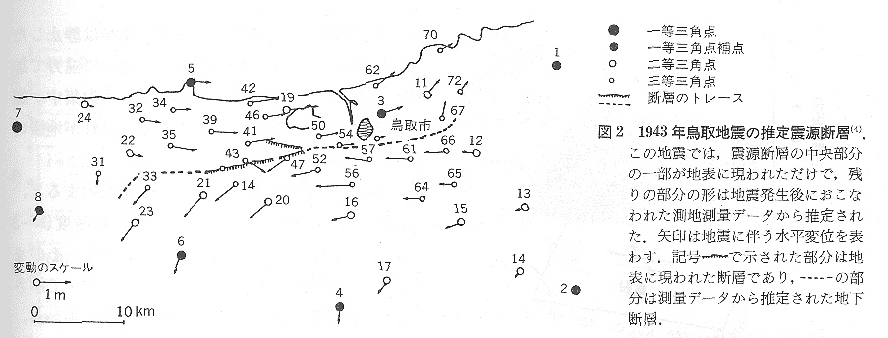
そこで我々は破壊の成長を支配する要素として破壊面の「形」に注目する。まっすぐでない破壊面の例として1943年の鳥取地震の断層を見てみよう(図2参照)。この地震では震源断層の中央部分の一部が地表に現れたのみで、残りの部分の形は地震発生後に行われた測地測量データから推定された。この鳥取地震の推定断層は破壊停止端で大きく屈曲している。なぜ、このようなことが起きたのであろうか?実は、破壊面は曲がろうとする性質があることはかなり昔に(約50年前!)Yoffeによって既に理論的に予測されている(文献4)。彼女は高速成長している亀裂の先端付近で応力が最も大きくなる方向は亀裂面の延長方向からずれることを指摘した。これは破壊面は自ら曲がろうとする性質があることを意味している。これまでのモデルでは、破壊面は曲がろうとしているにも関わらず、計算手法が無いという理由から不本意にも無理矢理まっすぐ進めていたことになる。そういう意味で従来の破壊力学研究が意味を持つのは、亀裂が曲がり始める直前までに限られてしまう。従って、この破壊面の形という要素をモデルに取り入れない限り、本当の地震破壊の性質を知ったことにはならないであろう。この考えから我々は「破壊面の形を完全に自由にした場合に、破壊はどのような形に成長するのであろうか?」という基本的な問題に取り組んだわけである。この問題は従来の計算方法では解けないため、新しい計算手法を開発する必要があった。
我々が新しく開発した計算法は、破壊面の形を破壊成長開始に先だって決める必要がなく、かつ、破壊の成長する方向に全く制限がないという点において画期的なものである。破壊面の形が時間と共に形を変えていく問題の解法は数学的に多くの困難があるが、これを何とか克服することに成功した(文献5)。ここに準備は整った。
4. 形状が自由な破壊のシミュレーション
まず最初に、破壊パラメタが場所によらず一様である場合を考える。これは破壊パラメタの非一様分布の影響を一切排除することにより、破壊そのものの性質を調べるのがねらいである。遠方で加わっている圧縮応力の方向、成長が始まる直前の亀裂の配置を図3に示す。
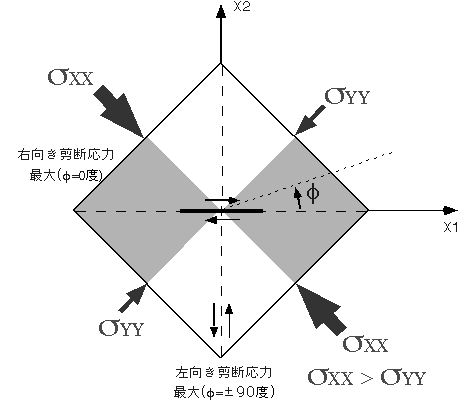 図3:モデル配置図と座標系。初期亀裂のはるか遠方で±45度の2方向から圧縮応力が加わっている。剪断応力が最大となる面はx1軸上とx2軸上の2方向にあり、加わっている剪断応力を解放するずれの向きは、それぞれ右ずれと左ずれで反対となる。ここでは右ずれを起こすx1軸上に初期亀裂を置く。φはx1軸から反時計方向に計った角度である。
図3:モデル配置図と座標系。初期亀裂のはるか遠方で±45度の2方向から圧縮応力が加わっている。剪断応力が最大となる面はx1軸上とx2軸上の2方向にあり、加わっている剪断応力を解放するずれの向きは、それぞれ右ずれと左ずれで反対となる。ここでは右ずれを起こすx1軸上に初期亀裂を置く。φはx1軸から反時計方向に計った角度である。
また、ここでは破壊面上の摩擦力が0、すなわち破壊面がもっとも滑りやすい場合を考える(摩擦力の効果については後で別に調べることにする)。先端の応力集中が媒質の破壊強度ぎりぎりに達している亀裂を用意し、これを初期亀裂と呼ぶ。シミュレーションでは物理量は全て無次元化してある。初期亀裂の長さはlo=5、媒質の破壊強度Tc=1.21である。遠方で加わっている応力をほんの少し増してやると亀裂先端の応力集中が破壊強度を越えて破壊成長が開始する。この時間をt=0にとり、これより後0.5ずつ時間を進めて破壊の成長がどうなっていくかを計算により決定していく。計算の手順は以下の通りである。(1) 各時間ステップ毎に亀裂先端のすぐ前方で、±90度の範囲で角度φの方向に沿って剪断応力を計算する。(2) 剪断応力が最大になる方向(最大剪断応力軸)とその値を決める。(3) 剪断応力の最大値が破壊強度を越えた場合は破壊面を最大剪断応力軸方向へ長さ1だけ進める。越えてなければ破壊面はそのままにする。(1) (2) (3) を繰り返すことにより破壊面形状の時間発展を求めた。
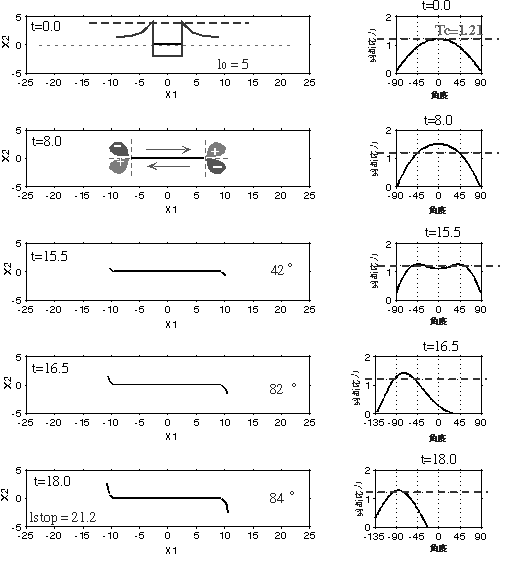 図4:形状を自由とした破壊成長の様子(文献5)。図の右列は各時刻での亀裂先端から角度φ(-90<φ<+90)の方向に沿う剪断応力を示す(φについては図3を参照)。点線は破壊強度である。右ずれの破壊を起こしている亀裂はφ>0の領域には圧縮応力、φ<0の領域には引っ張り応力を作り出す。
図4:形状を自由とした破壊成長の様子(文献5)。図の右列は各時刻での亀裂先端から角度φ(-90<φ<+90)の方向に沿う剪断応力を示す(φについては図3を参照)。点線は破壊強度である。右ずれの破壊を起こしている亀裂はφ>0の領域には圧縮応力、φ<0の領域には引っ張り応力を作り出す。
図4に計算により求められた破壊成長の様子を示す。時刻t=0の静止状態にある初期亀裂では最大剪断応力軸はφ=0度方向を向く、すなわち最も破壊が成長しやすいのは初期亀裂面の延長方向である。破壊の成長開始後、破壊速度は速やかに加速し高速化する。t=8ではまだ最も成長しやすい方向は亀裂面の延長方向であり、亀裂はまっすぐに進み続ける。t=15.5になると最大剪断応力軸が亀裂面からずれはじめφ=±42度の方向で破壊強度を越える。このとき破壊面はどちらに進みやすいかを、仮に摩擦力が働いていればという視点から考えてみる。亀裂は右ずれを起こしているのでt=8で+と書いた領域には圧縮応力、−と書いた領域には引っ張り応力を作り出す。摩擦力は押しつける力に比例するので+の方向と−の方向を比べると−方向の亀裂面の方が摩擦力が弱く、ずれが起こりやすいと考えることができる。したがってここでは亀裂は摩擦力の低い側に進むと考えた。さらに曲がった後の亀裂成長の計算を続けるとt=16.5に82度の方向、t=18に84度の方向で破壊強度を越え、曲がる角度が大きくなっていく。しかし、t=18より後、亀裂先端の応力を計算し続けても破壊強度を越えることは無い。すなわち破壊の成長はt=18で停止してしまう。驚くべき事に、形を自由にした破壊のシミュレーションを行うと剪断型亀裂は自発的に曲がり、その後すぐに自然に止まってしまう結果になった。
5. 自ら止まる地震破壊の性質
なぜ破壊は自分で曲がりその直後に止まってしまうのか、その力学について考えてみよう。亀裂が高速に進展することにより亀裂先端に集中した剪断応力は次々に解放され弾性波が放射される。この波動が作り出す亀裂先端付近の応力場は最大剪断応力軸を亀裂面からずらす効果があることが示される。破壊成長開始直後のまだ速度があまり高くない段階(t=8)では、波動は亀裂先端のはるか前方を去っていくので波動が亀裂先端付近の応力に与える影響は小さく、最大剪断軸は初期亀裂面と同じ方向のままである。したがって、この段階では破壊はまっすぐに進む。しかし、破壊成長速度が高速化し弾性波速度に近くなると、波動先端は亀裂先端のごく近くに存在し続け、波動が応力集中に支配的な役割を果たすようになる(t=15.5)。この段階で亀裂先端の剪断応力軸が亀裂面方向からずれ、亀裂は自発的に曲がり始める。
さて、亀裂の成長速度が高速化すると、亀裂先端付近で波動が支配的な役割を果たすることによって破壊面が曲がることがわかった。しかし、曲がった後に成長が停止するのはなぜであろうか?その答えは剪断型の破壊が2方向からの圧縮応力の下で起きる点に隠されていた(図3参照)。このような応力場では剪断応力が最大となる面が二つある。1つはφが0度の方向でありもう1つは90度の方向である。この2つの面にそれぞれ亀裂がある場合、剪断応力を解放するずれは右ずれと左ずれとなり互いに逆向きになる。先程のシミュレーションでは右ずれにより初期応力を解放する0度方向に初期亀裂を置いた。破壊が始まった後、亀裂面上で解放される応力は自らの成長を加速し、破壊速度は高速化していく。亀裂は高速破壊の最中に自らの先端から放射する波動の効果によって自発的に曲がり始め、その後破壊面の傾きを増していく。亀裂面の傾きが45度を越えると成長にブレーキがかかり始める。そのような所で右ずれの破壊が起きるということは亀裂面で応力降下ではなく逆に応力上昇をもたらすことになるからである。亀裂面で応力が上昇する(負の応力降下を起こす)ことによって、亀裂先端の応力の集中の度合いが次第に低下していく(亀裂先端の応力集中の度合いは亀裂面上の応力降下量に比例することを思い出そう)。一様に初期応力が分布している媒質中では、まっすぐに破壊する限り亀裂面上では常に正の応力降下を起こすはずであったのが、亀裂面が曲がることにより自動的に負の応力降下に転じてしまう。こうしてt=18以降、亀裂先端の応力の集中は破壊強度を越えることができなくなり亀裂の進展は停止してしまうのである。
6. 非一様性の「逆」効果
破壊シミュレーションの結果は、破壊パラメタの分布が場所によらず一様な場合には破壊は自らすぐに止まってしまうことを示す。この自発的に止まる地震破壊の観点から、ほとんどの地震が小さい理由がつく。破壊はすぐに止まることが本性であり、止まらない事を心配をする必要がそもそもなかったのである。しかし、今度は逆に「どうすれば破壊は止まらずに大きくなれるのであろうか?」という問題が生じることになる。
先の計算では破壊パラメタが一様に分布する場合を考えてきたが、地震が起きる断層帯にはこれらは完全一様に分布しているわけではない。非一様性が有る場合に、破壊はどこまで成長できるのであろうか?
破壊パラメタの分布が一様なモデルを基準にとり「基準モデル」と呼ぶことにしよう。「基準モデル」では初期亀裂の長さlo=5, 破壊強度Tc=1.21で計算を始め、最終亀裂長はlstop=21.24であった(これは初期亀裂の長さの約4倍の大きさである)。非一様性を導入したモデルで破壊シミュレーションを実行し、その結果を「基準モデル」と比較する。最初に考えた非一様性は初期応力の大小と破壊強度の大小を考慮した計4種類の非一様性モデルである。ここで用いた非一様性の度合いは従来のまっすぐな形の破壊計算の際には破壊停止に全く効果がないほど弱いものである。初期亀裂の周辺(白地領域)での破壊パラメタの値は基準モデルと同じにそろえ、亀裂がある程度成長してからその値が異なる領域(灰色地)に先端が進入するように設定した。それぞれについて、破壊成長の計算を行い成長停止後の破壊面形状を決定した(図5参照)。
計算結果を見ると、「基準モデル」より最終亀裂長が小さくなったモデル(A, D)と大きくなったモデル(B, C)に分かれる。それぞれの非一様性を見ていこう。モデルA, Dでは、それぞれ、初期亀裂の外側に破壊強度が低い領域と、初期応力の大きい領域を考えている。従来の考え方に従い、破壊はまっすぐに進むものと考える限りでは、これらの非一様性は破壊をより促進し、止まりにくくする要素である。しかし、形が自由な場合には破壊成長が促進されると速やかに高速化し、より早く曲がり始める。従って、より短い亀裂長で破壊が停止してしまう。モデルB, Cでは、それぞれ、破壊強度が高い、または、初期応力が小さい領域を初期亀裂の外側に想定している。これらの非一様性は、破壊の成長を抑制する要素と従来考えられてきた。しかし、形が自由な場合には破壊がなかなか高速化しないため、曲がりはじめるのが遅くなる。その結果、最終亀裂長が大きくなってしまう。このように、初期応力と破壊強度の非一様性は従来の破壊停止の考えとは全く正反対の効果をもたらすことがわかる。
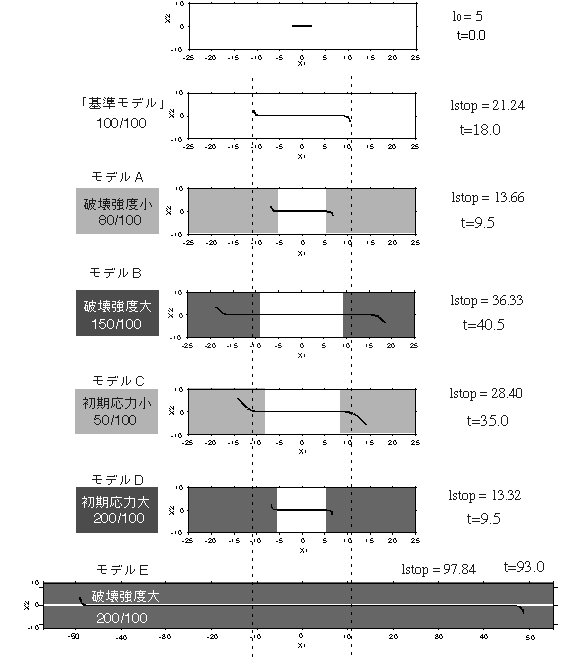 図5:破壊パラメタの分布に非一様性がある場合の最終亀裂長の比較(文献5)。灰色で表した領域の力学的性質は基準モデルと異なっており、基準モデルからの相違を百分率で示した。lstopは破壊が停止した時の亀裂長、tは停止時刻を示す。
図5:破壊パラメタの分布に非一様性がある場合の最終亀裂長の比較(文献5)。灰色で表した領域の力学的性質は基準モデルと異なっており、基準モデルからの相違を百分率で示した。lstopは破壊が停止した時の亀裂長、tは停止時刻を示す。
もう一つ、地震が起きる場所に特徴的な強度の非一様性について調べておく。地震は繰り返しおきることにより断層帯と呼ばれる厚さが数cmから数百mの破砕帯を形成する。断層帯内部の岩石は繰り返し破壊を受けることにより、外部の岩石よりも破壊強度が低くなっている。この断層帯を単純化して、強度の高い岩石に強度の低い断層面がサンドイッチされているとしたのが図5のモデルEである。この単純化は亀裂の長さが断層帯の厚さに比べて十分に大きくなった場合に意味を持つ。この場合、亀裂は曲がろうとしても周囲の破壊強度の高い部分に阻止され、なかなか曲がれない。したがって、弱面に沿って長く成長を続け基準モデルよりも大幅に大きい最終亀裂長lstop=87.84にまで達した。これは亀裂先端の応力集中が亀裂面から傾き、かつ、周囲の破壊強度の高い領域を破壊するには、亀裂が大きくなり破壊速度が十分に高速化する必要が有るからである。このように、断層帯の非一様構造は最終亀裂長を大きくしやすい性質を備えていることがわかる。ただ、注意すべきは、断層帯が力学的に弱く破壊が容易であるからではない。外側の強度が高く、曲がって止まることが難しくなるからである。
7. 自然断層の屈曲方向のパラドックス
先の計算では破壊面が枝分かれしようとしたとき、2つの成長方向のうち摩擦力が減り剪断破壊が起きやすい方向を選択して計算を行った。しかし、この時の破壊面の曲がる向き(図4)は鳥取地震の際の断層の曲がる向き(図2)とは反対になっている。日本の活断層の調査によると、鳥取地震の場合と同じく地震断層は摩擦力が増す方向に曲がっていることが普通であるということが報告されている(文献6)。断層が摩擦力が増す方向にわざわざ伸びる力学的なパラドックスはどうして起きるのであろうか?ここでは亀裂が分岐できるように条件をゆるめ、亀裂が枝分かれした後の亀裂面上に作用する摩擦力の違いが破壊面の形をどのように変えていくかシミュレーションにより調べてみよう。摩擦力が亀裂面に作用する場合、亀裂先端の応力集中が最大になり最も破壊が始まりやすい初期亀裂の方向は基準モデルの場合から少し傾く。この場合の破壊成長の様子を図6に示す。
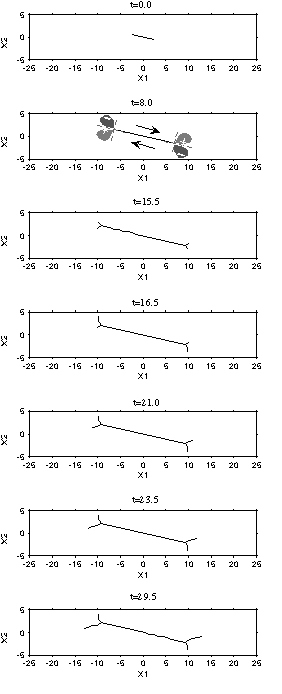 図6:摩擦力を考えた場合の破壊成長の様子(文献5)。
摩擦係数は0.5とした。破壊面は枝分かれした後、最終的には亀裂の作り出す応力場が圧縮(摩擦力が大きく、すべりを抑制する)の方向への成長が大きくなる。
図6:摩擦力を考えた場合の破壊成長の様子(文献5)。
摩擦係数は0.5とした。破壊面は枝分かれした後、最終的には亀裂の作り出す応力場が圧縮(摩擦力が大きく、すべりを抑制する)の方向への成長が大きくなる。
順を追って破壊成長の様子を見ていこう。t=15.5で初期亀裂の延長方向からずれた2方向で破壊強度を越える。そして破壊面が分岐する。t=16.5で亀裂の作り出す応力が引っ張りの方向に伸びた分枝では摩擦力が低く、ずれが起きやすくなり成長が促進される。圧縮の方向では、ずれにくくなるので亀裂の先端は伸びない。ここまでは、摩擦力が低い方向に破壊が進むと考えた「基準モデル」と同じ結果になる。しかし、引っ張り方向に伸びた分枝の進展はt=16.5以降その成長を停止してしまう。なぜなら、破壊が成長しやすいために亀裂面がすぐに大きく傾いてしまうからである。前に述べたように、大きく傾くほど成長に急激なブレーキ効果がかかる。一方、摩擦力が大きくなる方向の分枝では、成長しにくい為に亀裂面はあまり広角度に曲がらない(t=21)。したがって、成長を止める効果が相対的に小さくなり亀裂はしばらくの間成長を続け(t=23.5)、t=29.5にやっと停止する。こうして、最終的な分岐の長さは亀裂による応力場が摩擦力を増す方向に長くなる。一見すると力学的に矛盾している様に見える地震断層の屈曲方向が、実は摩擦法則に従う破壊成長の自然な結末であることを、我々の計算結果は示している。
8. 断層帯の形成と地震活動
長い地質学的時間の間に地震が繰り返し起きることにより断層帯は形成される。地質学的な時間で変化していく断層帯構造と地震活動の関係を、自発的に止まる地震破壊の性質から考えてみよう。
断層帯がまだ未発達の地殻は比較的一様な破壊強度分布をしており、地震破壊は自発的に曲がりすぐ止まってしまう。断層が無い所に大地震が起きないことがわかる。このような地震が起き続けるにつれ、小規模の既存破壊面が増えていく。こうなると破壊成長の最中に他の既存破壊面と結合することができるようになり、中規模な準直線的な破砕帯構造が次に構築されていく。それぞれの破壊過程において破壊停止端では分岐、屈曲の枝構造を作り出すが、これが若い断層帯に存在するステップ構造(破壊面の雁行配列)の成因の一つとして考えられる。この後、さらに繰り返し地震がおきると断層帯のステップ構造は次第に平滑化されなめらかな(直線的な)弱面が構造が形成される。断層帯が成熟するにつれ内部物質と周辺岩石との破壊強度のコントラストが高くなっていく。こうなると上に示したように破壊が非常に止まりにくい条件になり、断層帯全体を破壊する大地震が起きるようになると考えられる(図5E)。
9. おわりに
地震破壊の停止機構への理解への大きな一歩が踏み出され、破壊の始まりから停止までシミュレーションをすることが可能になり、原理的に地震の規模予測ができるところに到着したといえる。今回我々が考えた破壊の状況は単純であるが地震破壊の性質そのものを抽出することに適していた。しかし、現実の断層帯で発生した地震破壊に適用する場合はより実際的な破壊過程をモデルに含める必要がある。例えば、断層帯内の亀裂同士が合体する場合だとか、破壊強度の高い塊に亀裂先端がぶつかったときにそれを避けるようにして破壊が進む場合などである。もう一つ克服すべき課題として現実の断層の破壊パラメタの非一様分布をシミュレーションで必要な精度で知ることが可能かということがある。こちらに関しては地震学のみならず他の地球物理学的な手法による断層の詳細構造の解明が不可欠である。
10. 文献
(1) 宇津徳治:地震学, 共立出版(1977)
(2) M.I.Husseini et al. : The fracture energy of earthquakes, Geophys. J. R. astr. Soc.,42, 367, (1975)
(3) 佐藤良輔:日本の地震断層パラメタブック、鹿島出版会(1989)
(4) E.H.Yoffe: The moving griffith crack, Philosophical Magagine, 42, 739, (1951)
(5) 亀 伸樹:東京大学大学院理学系研究科学位論文(1997)
(6) 松田時彦:日本の地震学の概観、地震第20巻記念特集号、230, (1967)
戻る