研究解説
これまでの主な仕事の解説 -ナノの世界から地球を考える-
岩石中の粒界構造研究には、いささか屈曲した歴史がある。1980年代に透過電子顕微鏡法の研究結果をもとに、厚い水和した粒界あるいは変形作用によって構造が乱された粒界の存在が多くの人に考えられていた(例えばUrai et al., 1986)。工学材料と比べ、岩石は様々な元素の集合体からなり、生成史も複雑であるため、工学材料でしばしば見かけられる不純物層や粒界すべりに伴うボイドの形成と対比されていた。極端な場合、粒界の厚さが100ナノメーターと推定してるのもある。
しかし、適当なTEM法を用いると、この推測が誤りであることが判明した (Hiraga et al. 1999 & 2001)。粒界構造解析に不可欠な高分解能電子顕微鏡像を得るには一つの困難が付きまとう。粒界が電子線損傷を受けアモルファス化をし易いのである。特に、石英や長石においてそれは著しい。
当初、著者も粒界・界面に見られるアモルファス層をもって岩石中の粒界・界面の本質を見たと考えた時期があったが、観察下でアモルファス層の厚さが時間とともに増大することが認められたのである。詳細をはぶくが、電子線照射量を著しく下げた条件下で粒界・界面を観察すると、そのアモルファス層は全く見出せないことが分かったのである。従来厚いとされた岩石中の粒界・界面は、電子線照射の損傷域を見ていたのである。
これ以外にも、電子顕微鏡下のディフォーカス条件で粒界に生じたフレネル縞(= fresnel fringes)を粒界相と誤認した例もある (De Kloe et al. 2000)。 固体材料の分野でも電顕法により粒界の直接観察が不可能であった時期、粒界は隣接粒子との結合を緩和するような薄いアモルファス層からなるとされていたことがある。<この考えは、高分解能電子顕微鏡法による観察によって否定された。
しかし、後にセラミックス焼結体にアモルファス構造を持つ粒界相がしばしば見られることも知られるようになった。 これに対し、適切な観察条件下で岩石中の粒界・界面を観察すると、ほとんどの粒界・界面において隣接粒子が粒界相を挟まず直接接することが分かってきた(図1)(Hiraga et al. 1999)。
この結論は、当初、天然の変成岩を数多く観察した結果から導いたものであるが、その後、実験室で部分溶融させた条件下でも粒界構造は基本的に変わらないことが明らかになり(Hiraga et al. 2002a)、ほとんどの鉱物や様々な地質条件下でも、図1で見るような粒界・界面構造が一般的であると当人は考えている。
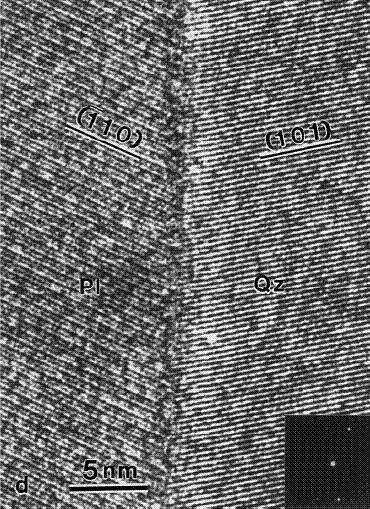
図1 石英ー長石の異相界面(サンプル:畑川マイロナイト)
粒界・界面エネルギーは、表面エネルギーと同様、粒界・界面において結晶構造の「断続」もしくは「歪」によって生じる過剰エネルギーである。通常、エネルギー値は単位面積あたりのエネルギー(例えばmJ/m2)を採用しており、単位長さあたりの力、つまり張力に等しい。この値は、粒界構造を反映しており、また岩石中の粒子成長の重要な駆動力である。粒界・界面エネルギーの値より、はじめて粒界・界面構造の安定性の議論が可能になり、またエネルギーが粒界・界面の物性と密接に関係していることから、この値を求める試みが工学材料の分野では精力的に行われている。鉱物に関しては、これまで石英、斜長石およびカンラン石のみから得られている(Cooper & Kohlstedt 1982; Duyster & Stockhert 2001; Hiraga et al. 2002a)。
粒界・界面エネルギーを直接求めることは困難である。通常、表面エネルギーとの比または粒界三重点における他の粒界との比という形で求められ、表面エネルギーや双晶界面のエネルギー値が得られていると粒界・界面エネルギーが実測可能になる。ここで泥質片岩中の粒界・界面エネルギーを求めた例を紹介したい(Hiraga et al. 2002a)。
この岩石は、主に石英およびアルバイトからなり、転位の配列からなる石英の小傾角粒界およびアルバイト粒子中にアルバイト双晶やペリクリン双晶が発達してくる。これらをTEM下で観察すると、これらの粒界・界面がその他の粒界・界面と交わる箇所、三重点では、界面張力のバランスをとるような構造をとっていることが分かる(図2)。これら界面間の釣り合い角度により、粒界・界面エネルギーの比を求めることが可能となる。単純な刃状転位を含む小傾角粒界の場合、転位列のエネルギーそのものが粒界エネルギーとなる。この場合、小傾角粒界エネルギーが120±45 mJ/m2が得られた。ここに三重点における角度を界面張力の釣り合いの式に代入すると石英粒界、アルバイト粒界、石英・アルバイト界面エネルギーが求まる。石英粒界、アルバイト粒界、石英・アルバイト界面エネルギーとして、それぞれ270±110 mJ/m2、300±150 mJ/m2、250±120 mJ/m2が得られた。粒界・界面エネルギーはしばしば1J/m2と仮定されることが多いが、得られたエネルギー値はそれと比べ小さい。一般的に粒界・界面エネルギーを下げるとされる粒界偏析(= grain boundary segregation)がその役割を担っていると考えられる。特定元素を抽出し合成された工学材料と比べ、自然界にはありとあらゆる偏析物質が用意されているからである。
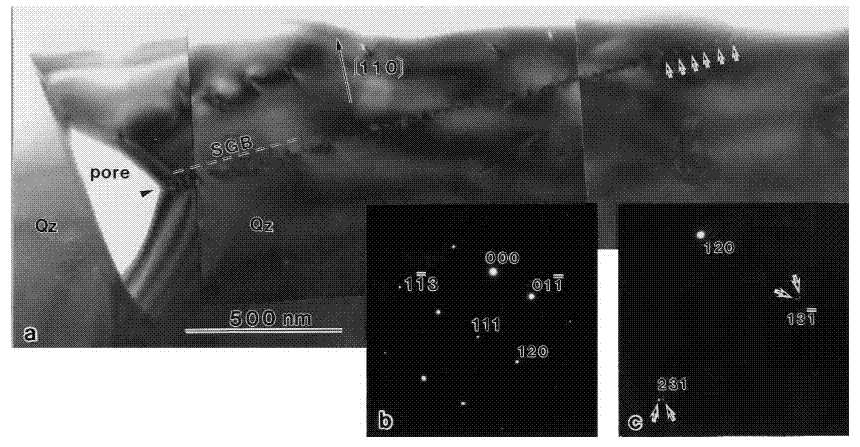
図2 石英の小傾角粒界(SGB)と粒界ポアが作る二面角 (サンプル:三波川泥質片岩)
粒界・界面における流体(メルト・揮発性流体)の存在形態は、地球内部の流体移動機構を決定することから、これまで精力的に研究されている。流体の岩石中での体積比において10%に満たないものが集積し、マグマを形成もしくは揮発性流体の移動が起きていることが、様々な間接的証拠から示されている。そのような状態では、流体は粒界・界面三重点をつたって浸透流という形で移動することが予想されている。これまで、実験下での流体と粒子間に発達する二面角を測定することで、この移動メカニズムが実現か否かが議論されてきた。体積分率にもよるが、二面角60度というのがしきい値になっている。果たして実験下で予想されている構造が天然のサンプルにおいて見られるのかを検討したのが、Hiraga et al. (2001) である。
観察に用いたサンプルは、三波川変成帯の低変成度の泥質片岩である。岩石の最高変成温度条件は250-300度と推定されている。岩石の微細構造を観察する際にとりわけ気をつけなくてはならないのは、微細構造がいつの地質ステージで形成されたかを知ることある。我々が岩石を採取できることは、降温降圧のステージを岩石が経験していることであり、現在見られる微細構造は、岩石の相平衡条件と同一の条件とは限らない。特に、粒界・界面のナノスケールの構造形成は、原子の大規模な拡散を必要としないので、この恐れは特に大きい。低変成度の岩石を用いることで、その構造は少なくとも低変成条件から室温条件という限られた温度圧力範囲以内で形成されたという制約をつけるこができる。泥質片岩では、ナノメーターサイズの粒界ポアが観察される(図3a)。このポアを埋めているのは水であることが顕微赤外分光法により判明している。つまり、観察されるポアは、粒界に存在する流体包有物である。包有物を結ぶ粒界は、通常の「狭い」粒界構造を持つ(図3b)。粒界にナノオーダーの厚さを有する薄膜水が存在(二面角=ゼロ度)し、圧力溶解や破壊に大きな影響を与えるという考えがあるが、その存在は否定される。ポアは、レンズ状の構造を取り、界面エネルギー最小の理想的な構造を取っている。
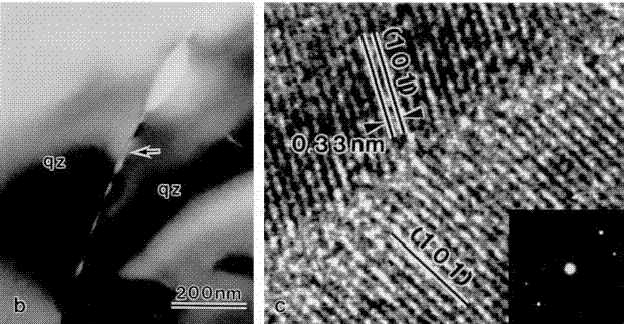
図3 石英粒界に見られる粒界ポア (b) は(a)での矢印における高分解能電子顕微鏡像
図4では、粒界三重点のポアと粒界ポアが隣接しているが、双方に見られる二面角は等しい。つまり前述したが、等しい界面張力の釣り合いによって、そのポアの形が決定されていることが分かる。多くの二面角の測定により、サンプル中では、ある特定の角度に集中し、また、同じ変成条件下の岩石でもカルサイトを含む岩石中の二面角と含まないもので異なることが分かった。測定された二面角を実験的に得られたHolness (1993)と比較した。
彼女の結果では、4 kbarの圧力条件で温度が下がるにつれて二面角が下がる。また、CO2が水に入ってくると二面角は上がる。観察を行ったサンプルの変成温度条件に彼女の結果を外挿すると、観察された二面角がうまく説明される。これまで、彼女の低温領域(400-500度)からの実験結果は、構造平衡に達しているものからのかという危惧もあったが、天然の観察事実は彼女の結果を支持している。実験では決して作れない低温下での構造平衡を天然は見事に作ってくれているのである。
自然界では、つまり300度以下の低温でも、流体の分布構造を界面エネルギーで議論することができるのである。これまで、二面角に基づく流体の移動機構は高温領域でのみ達成されるという前提があったが、上部地殻でも流体は界面エネルギーの支配のもと移動している可能性が出てきた。
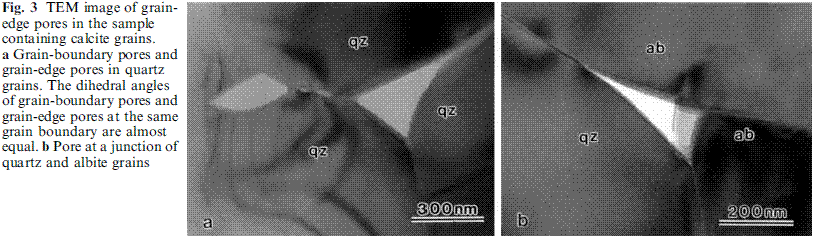
図4 石英の粒界と粒界三重点に位置するポア(サンプル:三波川泥質片岩)
もう一つの岩石―流体の重要な系は、海洋地殻を最終的に形成するペリドタイトーバサルト系である。ここ15年ほどバサルトがオリビン粒界を濡らすか濡らさないかという大きな議論が行われている。特に、ここ数年ANUやUltrechtのグループが部分溶融した系においてオリビン粒界をナノオーダー(<10 nm)の厚さを持つメルトフィルムが存在することを主張しはじめた(Drury & FitzGerald 1996; De Kloe et al. 2000)。もし濡らすことができると、岩石のレオロジー、地震波速度および電気伝導度に大きく影響を与えることが予想される。この議論に最終的に決着をつけたのがHiraga et al. (2002) であるので、ここで簡単にそれを解説したい。粒界フィルム構造は焼結を経た共有結合性多結晶体にしばしば観察される。粒界での不純物の濃集もしくは共有結合は大きな異方性を持つため隣接粒子間の結合を緩和するために存在すると考えられている。高分解電子顕微鏡法でオリビンーバサルト系のオリビン粒界の観察を行った。その結果が図5で、全くアモルファス層(フィルム状)の構造は見られない。これまで、粒界に幅数ナノのコントラストをもったバンドがメルトフィルムとされてきたが、電顕下でしばしば観察されるポテンシャル差によって生じるフレズネル縞の誤認であることが確かめられた。もう一つの、フィルムの存在の強い証拠として挙げられたのは、粒界における組成異常である。特に、CaやAlが濃集てくることが分析電顕法により確認されたのである。これは、次に述べる粒界偏析の誤認である。フィルムの存在は完全に否定された。
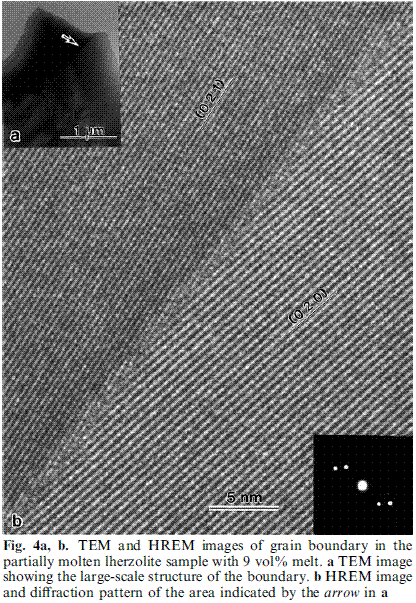
図5 オリビンーバサルト系中のオリビン粒界
Hiraga et al. (2003)は、オリビン粒界における元素の濃集パターンが、天然の粒界および合成された試料すべてに共通することを走査型透過電子顕微鏡・特性X線エネルギー分光法より見出した(図6)。合成試料は、系内で化学平衡に達するに十分な合成時間および水クエンチを与えていることから、平衡偏析の存在が確認された。オリビン粒界においてCa, Al, Tiが濃集してくること、それに対しMgが減少し、Fe, Ni, Mn, O, Si はほとんど変化しない。Mgの減少分とCaの濃集分はおおよそ一致しており、CaはMgを粒界において置換していると考えられる。
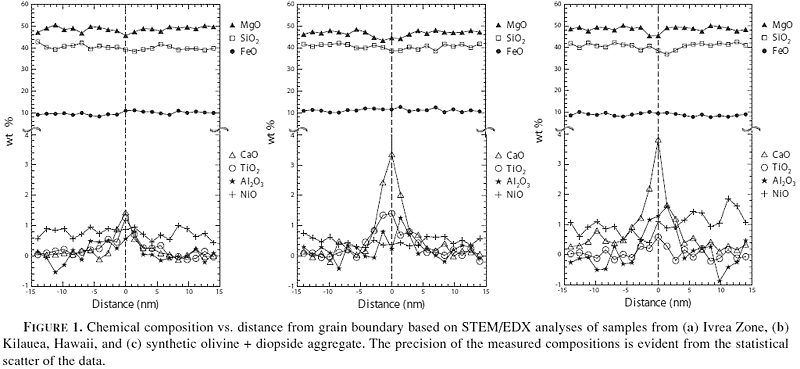
図6 オリビン粒界のケミカルプロファイル。右:イブレア産ペリドタイトマイロナイト;
中央:ハワイ産玄武岩中のオリビン斑はん晶;左:1200度で焼結したオリビン粒界
オリビンのCaのXGM (=粒内濃度)とXGB (=粒界濃度)をプロットしたのが、図7である(Hiraga et al. 2003)。色や記号は、それぞれの鉱物組み合わせ、合成温度を表している。天然サンプルの結果も加えてある。観察された粒界でのCaの濃集は、粒界原子層一面において生じていると仮定した。実際に、MgOでの対応粒界においてCaがそのような分布をしていることがZ-contranst法により分かっている。観察される粒界近傍でのプロファイルは5ナノメートル程度の幅を持っているが、これは入射電子線が試料中で広がり、検出される特性X線は広がりを持った領域からのものである。粒子内の分析は波長分散型のマイクロプローブによっておこなった。一見して分かるように、XGMとXGBには正の相関があること、分配係数DGM/GBは濃度および温度依存性があり、それらと負の相関がある。これらは、すべてMcLeanモデルから予想されることに見事に一致する。偏析エネルギーをCaがオリビン格子内に入ることによって生じる格子歪みエネルギーに等しいとした場合得られる理論分配曲線が図7に示されている。かなりの良い一致を見るのが分かる。この結果は、ホスト原子と価数が同じである場合は、容易にイオン半径から単純にDGM/GBが求まることを示している。Hiraga et al. (2004)は、このモデルを大きなイオン半径を有する元素に適用し、マントルにおいて、粒界・界面が液相濃集元素の主たる貯蔵庫になりうることを示した。
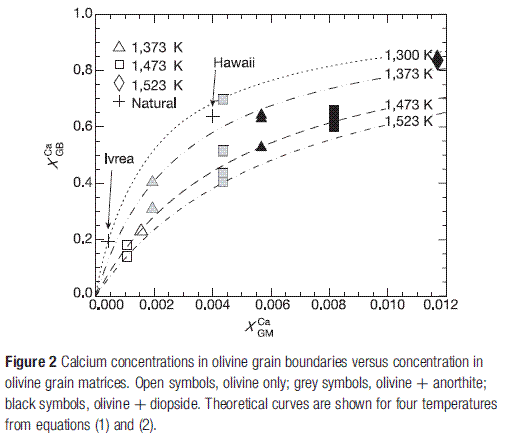
図7 Caのオリビン粒内での濃度(横軸)vs 粒界での濃度(縦軸)。
点線は、各温度での熱力学モデルから予想される分配曲線。