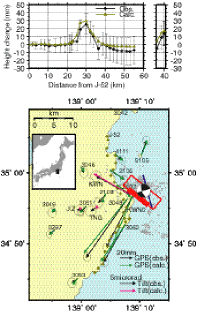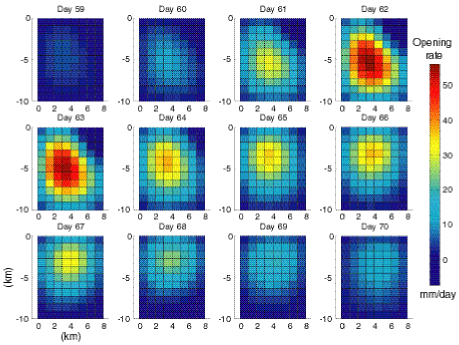目次へ 次へ
6-5.GPSによる総合観測研究
GPS(Global Positioning System)は極めて応用範囲の広い技術であり,数km程度の広がりの火山体の地殻変動から地球全体の変形まで,様々なスケールの地球表層の変動現象を明らかにすることができる.このためGPSは測地学・地球物理学の分野で基本的な観測手段として急速に導入されつつある.地震研究所のGPS研究グループは,全国の関連研究者と共に1988年頃「GPS大学連合」を結成し,日本列島の地殻変動の観測や周辺のプレート運動の観測など,多数の受信機と研究者を必要とするような大規模なプロジェクトを企画立案し,国内外の研究者と共同して,観測研究を実施してきた.
特に力を注いできたのは,西太平洋〜東アジアにかけての地域におけるGPS観測網の構築(5-3
海半球計画の項参照),伊東市周辺域における稠密アレイの構築,及び地震・火山活動に伴う臨時観測の実施,などである.図1,
2は伊東市東方沖に発生した1997年3月の群発地震に関するGPSデータ等を解析して得られた断層面上の開口速度の時間発展を示したものである.このような地殻変動の数理解析の他,キネマティックGPSを応用した海底地殻変動の検出やGPS津波計の開発あるいは,大気遅延量推定を通じての気象学・気候学への応用など,GPSの応用分野はさらに拡がる可能性を秘めており,地震研究所では全国の研究者と共同しつつこれらの先端的・実験的研究を推進している.
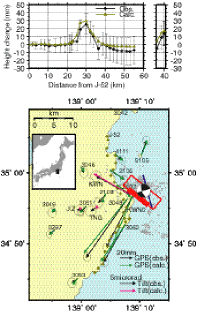
図1.伊東市東方沖に発生した群発地震に伴う地殻変動.矢印はGPSによる水平変位,折れ線グラフは水準測量結果を示す.観測値と計算値を重ねて示している.
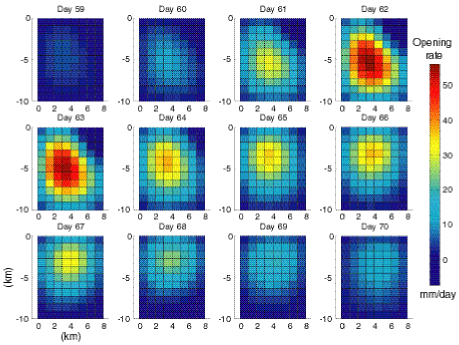
図2.西北西ー東南東走向の群発地震の断層面上の開口速度変化.最大開口位置が地表に向かって移動しているのが見える.
目次へ 次へ