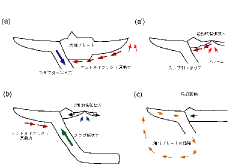
地球テクトニクス分野では,地球表面の各所でおきる多様なテクトニクスをグローバルな地球内部変動の視点から理解することを研究目標としている.地球内部の熱の排出にともなってなされる仕事の地表への現れがテクトニクスであるが,現在の地球ではこれはプレートテクトニクスの形態をとっていると考えられている.プレートテクトニクスは,プレート境界が力学的に弱いことで特徴づけられるが,その場合プレートをのせたマントル対流の形態は一様粘性の対流の形態に近い.しかし実際のプレートに働いている力を地震のメカニズムなどから見てみると,これからはずれることが多い.そしてはずれる場合に大陸分裂や背弧海盆拡大など活発なテクトニクスが起きている.このことは,むしろプレートテクトニクスからのずれが多様なテクトニクスをもたらしていることを示唆している(図1).現在の研究テーマは次の通りである.1)日本付近のプレート運動,2)プレート・スラブ内応力場,3)プレート運動原動力,4)スラブ地震の発生メカニズム,5)太古代のテクトニクスと環境変動.
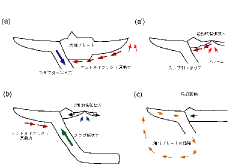
図1.テクトニクスの三つの形態:(a),(a')スラブ引っぱり力が大きく衝突力と釣り合っている.(b)負のスラブ引っぱり力=スラブ押し力が海洋プレートの駆動力とつりあっている.(c)プレートはスムースにマントル対流とともに循環しており,定常的な島弧変動が起きる.地表でめぼしいテクトニクスが起きるのは(c)からのずれがある場合である.
マグマ学分野では,岩石学や高温高圧実験(図2)の手法を用いてマグマに関する研究を行っている.個々の火山におけるマグマ組成の変遷を解明することによって,その火山で将来起こりうる噴火の様式を予測するための重要な手がかりが得られる.また,火山活動の源となるマグマの一部は上部マントルの部分溶融により生成され,部分溶融の程度や深さの違いなどによって多様性が生じているため,このようなマグマの研究を通じて地球内部の温度条件や化学組成などを推定することができる.さらに地球初期には地球の表面を覆う深いマグマの海が存在し,このマグマの海における結晶・固化の過程で現在の地球内部構造の大局が形成されたと考えられているので,地球の進化を理解するためにも,さまざまな圧力におけるマグマの挙動を理解することが不可欠である.以上のような観点からマグマに関する様々な研究を行ってきた.地球内部では水がマグマに似た振る舞いをすることを最近発見したので,高圧下での水も主要な研究対象となっている.最近の研究テーマとして次のようなものがある.(1)デカン洪水玄武岩の調査・研究.(2)洪水玄武岩マグマの発生に関する実験的研究.(3)マントル物質と共存する水の化学組成とその挙動.(4)伊豆大島火山,浅間火山,三宅島火山等のマグマ組成の変遷.(5)島弧マグマの結晶過程における水の役割.(6)三宅島2000年噴火マグマの岩石学的研究.

図2 超高圧発生装置(PREM).内部に8個の超硬合金製のアンビルが組み込まれており,中心部の2-10mm3の正八面体の容積に25GPaまでの圧力と2500°Cまでの高温を発生できる.
地球物質進化学分野では,グローバルな規模で生じる火山活動や地球深部における揮発性元素の存在とその役割,物質循環を含む地球内部での物質移動などやそれらの過程を明らかにすることを通じて,地球における物質進化を解明することを目指している.地球内部における揮発性元素の存在がマントル物質などの物性に与える影響は大きく,その存在度や化学・同位体組成などは地球の進化過程を強く反映している.地球物質の進化の過程を明らかにするため,岩石や鉱物の化学・同位体(希ガス,ベリリウム10/ベリリウム9)組成,放射年代(カリウムーアルゴン、アルゴンーアルゴン、放射性炭素14法),鉱物組成の解析などを手段として,各種の噴出岩や捕獲岩として得られるマントル構成岩石・鉱物,さらには地球初期物質の状態を推定するために隕石などの地球外物質なども対象として研究を行っている(図3).現在は以下のような課題を分野としての研究テーマとして研究を行っている.1)地球内部の揮発性元素の存在と地球進化との関係,2)キンバーライト中の揮発性元素の成因,3)ホット・スポット火山とマントル・プルームとの関係,4)地球内部における物質循環と地球内部の化学的構造,5)洪水玄武岩の生成とマントル・プルームの関連,6)拡大系における地球内部からの物質移動とその化学的特徴,7)ベリリウム10を用いた日本列島下のマグマへの堆積物の寄与の実証.
地球化学グループは,火山の諸現象や地球の物質循環・進化などを探求する研究を,行っている.現在の中心課題は1)マグマの発生から移動の諸現象にタイムスケールをつけることと,2)火山岩中の微小部分,例えば個々の斑晶鉱物やメルト包有物,更には鉱物結晶の累帯構造の各部分に残された記録を読みといて,マグマの生成から移動,マグマ溜り内での貯留,さらに噴火にいたるメカニズムを解明することである.1)についてはウラン238放射壊変系列の核種の放射能非平衡現象を利用した研究を行っている.島弧の火山活動は沈み込むスラブからの脱水が重要な寄与を果たしていると考えられているが,その際に初生マグマに流体とともに移動しやすいウランが付け加わる.こうして生じたウラン238-トリウム230間の放射非平衡を利用すればマグマが生じてから地表に達するまでの時間に制約をつけることができる.本所に設置された多重検出器磁場型ICP質量分析計(図4)による,ウラン238-トリウム230放射非平衡の分析技術を確立した.本法を伊豆島弧をテストフィールドとして適用する研究を開始した.2)についてはレーザーアブレーションICP-MSによる微量元素分析技術を確立するとともに,班晶の微小部分の同位体測定技術を開発している.これらを雲仙の試料に適用し,マグマ溜まりの化学進化の解明に用いる研究を行っている.その他に沈み込み地域での物質循環の解明のためにリチウム,鉛同位体をトレーサとした研究を目的として分析技術の開発を行い手法を確立した.また初期地球におけるコマチアイトの成因を考察するためのLu-Hf同位体トレーサ系の分析技術,コア‐マントル相互作用を検証することを目的とした白金族元素の微量分析技術の開発にも取り組んでいる.
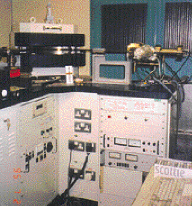
図3.希ガス同位体分析用質量分析計(VG5400).
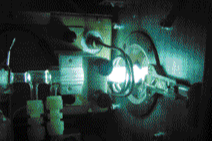
図4.磁場型ICP質量分析計(Micromass IsoProbe)のイオン源.本装置をTh, Pb, Li, Srなどの同位体測定に使用している.ICPイオン源により10ng程度の微量トリウムの同位体測定が可能になった.