(1) 課題番号:0702
(2) 実施機関名: 東京大学・大学院理学系研究科
(3) 実施課題名: 東海及びその周辺地域における地下水観測研究
(4) 本課題の5ヵ年計画の概要とその成果
(4-1) 「地震予知のための新たな観測研究計画の推進について」(以下、建議)の項目:
㈽、2、(2) 特定域地殻活動モニタリングシステム
(4-2) 関連する「建議」の項目 (建議のカタカナの項目まで、複数可):
2 (2) ア、イ
(4-3) 5ヵ年計画全体の目標:
これまでの地下水観測研究は、帯水層から揚水した地下水の溶存イオン成分やガス成分の計測が主流で、この方法では水位観測と両立できないばかりか、帯水層を乱すことによって高感度測定に問題があった。また、溶存ラドンの成果ばかりが強調されており、ラドン変動のメカニズムを明らかにするためにも他のガス成分を同時に測定する必要が指摘されていた。そこで、5カ年計画では、循環[ft1]型の地下水溶存ガス測定システムを開発し、東海などで行なっている既存の観測点に導入し、地震に関連する地殻内の化学変化を地下水に溶解するラドンだけでなく他のガス成分の変化からも検知することを目標とした。
(4-4) 5ヵ年計画全体の実施状況の概要と主要な成果:
まず、循環型の地下水溶存ガス測定システムの設計を行ない、東海及びその周辺地域の既存の地下水観測点3地点5観測井に設置し、運転を開始した。この観測システムの特徴は、(1)揚水した地下水から溶存ガスのみを気体交換モジュールを用いて抽出し、その水は再び帯水層に戻す、(2) 高感度で多種のガス成分の分析を短い時間間隔で行うために、四重極質量分析計を使用する、(3)半導体検出器を使ったポータブルなラドン計測装置を使用する、点にある。さらに、各観測点で得られたデータを一元的に解析し、リアルタイムで公開できるデータ収集解析システムの構築も行なった。
試運転を重ねるにつれ、本システムの問題点が明らかになり、それらの解決に時間と手間を要した。主な問題点は、(1)地下水からガスを抽出するための気体交換モジュールの強度の問題、(2)抽出ガスの主成分である水蒸気の結露の問題、(3)揚水に伴う発泡により揚水が停止してしまう問題、(4)データ転送システムの不整合に伴う欠測の発生、などであるが、(1)揚水速度の調整ができるようにした、(2)気体交換モジュールの設置方法を工夫し、結露水を減圧系から取り除けるようにした、(3) 地上部の配管のジオメトリとポンプ位置を工夫した、(4)転送システムを再構築した、ことによって解決することができた。
新しいシステムでの成果は、次の2点である。(1)御前崎観測井において、メタンをはじめとして酸素や窒素などの地下水溶存ガスが、2週間にわたって潮汐応答を示した。(2)竜洋観測井において、溶存ガス成分のうち二酸化炭素に潮汐応答が観測された。これらは、地震前からの歪みの蓄積を反映する変化が地下水溶存ガス成分に出ることが期待される結果である。
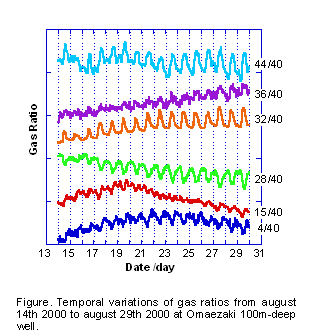 (成果とデータ)
(成果とデータ)
ここでは、御前崎観測井で観測された溶存ガスの潮汐応答について述べる。
地下水揚水速度はこの期間中1.3±0.4L/minであり、測定インターバルは1秒で、1分間の積算結果を連続的に記録した。ガス抽出は永柳工業の気体交換モジュールを使用し、抽出ライン内はおよそ30Paまで減圧している。測定対象のガスは質量数で4,5,15,18,28,32,36,40,44であり、データは質量数5のデータをベースラインとし、40Arで規格化して使用した。右の図には2000年8月14日から8月29日までに観測された御前崎100m井の地下水から抽出されたガスの時間変化を示す。縦軸は比較が容易になるように適当にシフトさせてある。
もっとも特徴的なのはHe/40Ar比とCH4/40Ar比に明確な半日周期と一日周期が見られることである。これは周波数解析、BAYTAP-G解析から確認された。CH4は溶存ガスの第二主成分で17%もあり、大気中の濃度に比べ5桁以上も高い。つまり、CH4などの地殻内から供給されたと考えられるガスの濃度が、地殻の歪変化を反映して変動することを期待させるものである。もしそうならば、地震前にはガス濃度の大きな変動が期待できることになる。
その他のガスには明確な半日周期変動成分は測定誤差と同等なレベルでしか認められず、一日周期が卓越していた。N2の一日周期の位相はCH4とほぼ同期しているが、CO2とO2の一日周期の位相はCH4とN2に対して180度ずれていることがわかった。
先に述べたCH4の変動も含め、これらの変動が生物活動に関係したものであるならば、生命活動に関係ないN2には変化が現れないであろうし、CO2とO2は逆位相になると考えられる。また、気体交換モジュールの抽出効率は温度によって変動するが、御前崎100m井の場合水温はおよそ20度でほとんど変化しないと考えられ、効率の変化ではガス濃度の変動は説明ができない。つまりこれらの変動は、地殻の歪変化とそれに関係した地下水のダイナミクスによっておきるものであると考えるのが自然である。
このように、地下水溶存ガスが地殻の変化を反映して変動する可能性が示され、本システムが地球化学的な見地から地震予知に貢献できることが証明された。
(4-5) 5ヵ年計画で得られた成果の地震予知研究における位置づけ:
地下水観測によって、地震に関連した変化が検出されることは疑いのないことであるが、変化のメカニズムの理解は必ずしも進んでおらず、未だに事例の蓄積の段階から脱していない。その原因の1つは、水位なら水位だけ、ラドンならラドンだけで閉じて議論され、地下水のダイナミクスを包括するメカニズムが考えられていないことにある。本システムが本格的に稼動することにより、自然水位および精密水温測定との両立が可能となり、地下水に含まれる異なった起源、挙動、化学的性質の多成分のガスを同時に観測し、変化を統一的に解釈できることから、地震直前過程の解明へつながることが期待される。
(4-6) 当初目標に対する到達度と今後の展望:
5カ年計画の初期の段階で東海及びその周辺地域の既存の地下水観測点3地点(竜洋、御前崎、鎌倉)の5観測井に、循環型の地下水溶存ガス測定システムを導入した。試運転段階で確認された問題点の解決に当初の予想を超えた時間と手間が必要であったが、何とか実用的なシステムの完成にこぎつけ、観測システムの実用性を前進させた。さらに、新システムから興味あるデータも取れはじめ、地震に関連する地下水研究への貢献が行なわれつつある。
当初の計画では5観測井につづき、地殻化学実験施設でラドン観測を行なっている東海及びその周辺地域における地下水観測点を新たなシステムに変える予定であったが、最初の5観測点以外は予算化されず、今日に至っている。地殻化学実験施設が展開している観測システムとしては、旧式の揚水型ラドン測定と新式の循環型多成分測定が混在するため、はなはだ具合が悪くなっており、第2次の計画に引き継いで要求を行なっている。
(4-7) 共同研究の有無:
なし
(5) この研究によって得られた成果を公表した文献のリスト
(5-1) 過去5年間に発表された主要論文(5編程度以内):
Tsunomori,F., Kawai,K. and Igarashi,G., Tidal variations of gas composition in
groundwater. Geochim.
Cosmochim. Acta 67, A495
(2003)
Tsunomori, F., Development of Continuous and Multi-component Gas
Monitoring System for Groundwater, in
Proceedings of Japan-Taiwan International Workshop on Hydrological and
Geochemical Research for Earthquake Prediction (eds. Koizumi, N., Matsumoto,
N., and Shieh, C-L.), Geological Survey of Japan
Open-File Report, No.384, The National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology pp.4 (2002)
伊藤貴盛、角森史昭、五十嵐丈二、竜洋観測井で観測された二酸化炭素の潮汐応答、
日本地球化学会年会3C11(2001)
Ito,T., Seismo-geochemical
anomalies of He/Ar ratio of gas bubbles at Hoshina
spa near Matsushiro,
(5-2) 平成15年度に公表された論文・報告
Tsunomori,F., Igarashi,G. and Notsu,K., Effects of circular pumping method on
groundwater observation. 2004
(6) この課題の実施担当連絡者(氏名、電話、FAX, e-mail):
野津憲治 電話:03-5841-4624 FAX:03-5841-4119
e-mail: notsu@eqchem.s.-u-tokyo.ac.jp