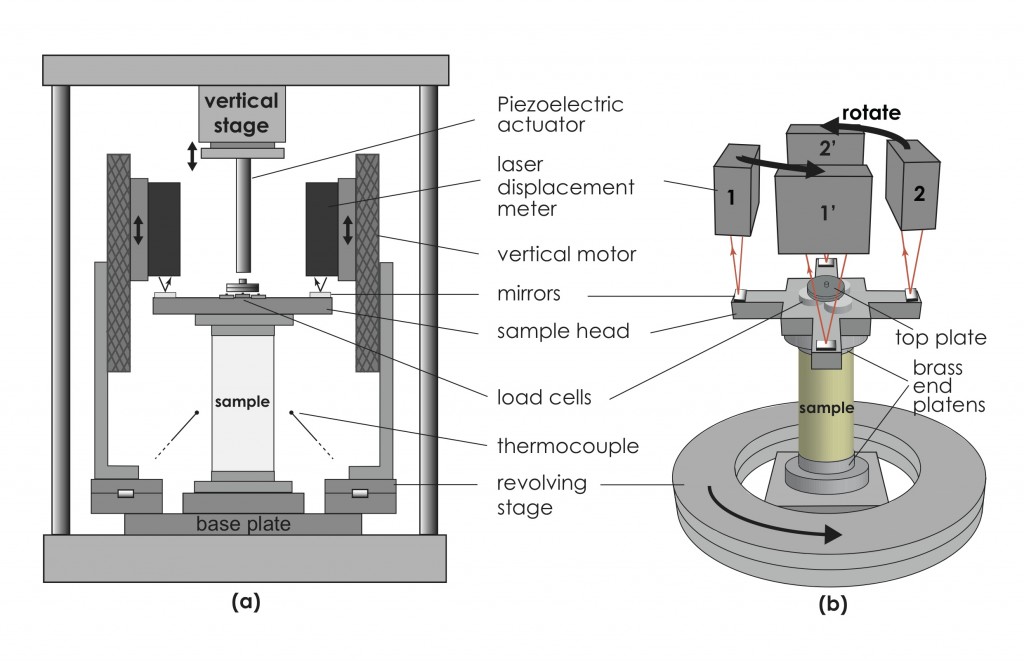「部門・センターの研究活動」カテゴリーアーカイブ
3.4.1 被害地震の震源過程と強震動の生成過程
(1)三次元グリーン関数を用いた震源過程解析
震源過程解析の精度にはいろいろ要因が影響しているが,中でもグリーン関数の精度が大きな影響を与える.グリーン関数は地下構造モデル内の単位震源に対して理論的に計算されるので,地下構造モデルは通常用いられる一次元構造モデル(水平成層構造モデル)より現実に近い三次元構造モデルを用いる方がグリーン関数の精度を大きく高める.こうした三次元グリーン関数の計算手法の研究を進めるとともに,1923年関東地震,1952年と2003年の十勝沖地震,1995年兵庫県南部地震などに対して,三次元グリーン関数を用いた震源過程解析を行った.
(2)国内外の被害地震の震源モデル
強震動(災害につながる強い揺れ)の研究とは,地震の震源の破壊過程・地震波が地球を伝わる現象(波動伝播)・地面が揺れる現象(地震動)といった一連の現象を理解することである.強震動をともなう地震は,他の自然災害に比べて稀にしか起こらないため,起こった地震の詳細な震源モデルを着実に蓄積することに格別の重要性がある.これらの震源モデル群からは海溝型地震のスケーリン則グなどが見出された.また,2018年北海道胆振東部地震をはじめとする被害地震の震源過程を検討した
(3)ネパールヒマラヤ巨大地震とその災害軽減の総合研究
プレート衝突帯に位匿することにより巨大地震の発生と山岳地形の形成という危険にさらされているネパールにおいて,ヒマラヤ前面における地震発生シナリオの作成,カトマンズ盆地の地下構造モデル構築や表層地質の影響評価などを行い,その巨大地震によるカトマンズ盆地のハザード2を016年度から約5年間総合的に研究し,その後も観測・技術移転および成果のとりまとめを継続している.特に,地震観測システムや,地震学の高等教育,耐震政策への提言などを検討し,それらを通した研究成果の社会実装を目的としている.
3.3.5 高温マグマプロセス解明に向けた物質科学的研究
プレート収斂域での火成活動において,部分溶融によるメルトの発生からメルトの上昇・冷却・定置といった一連の過程がどのような時間スケールで進行するのかを明らかにすることは,大陸地殻-マントル間での物質的・化学的分化の過程を理解する上で重要である.こうしたマグマ活動の中でも,特に高温(>600℃)でのプロセスに時間軸を設定する上で鍵となる手法が高い閉鎖温度(約900℃)を持つジルコン鉱物のウラン・トリウム系列年代測定法である.物質科学系研究部門・坂田研究室ではジルコン鉱物から得られる時間情報の高精度化を進めると共に,従来法では得ることのできなかったメルトの発生から鉱物晶出までの期間を定量化する新たな年代測定法の開発を進めている.さらに,マグマ溜まり中での温度や化学組成の変化を追跡する目的で鉱物中の微小領域(15-30μm)からチタンや希土類元素を精確に定量する技術を確立した.こうした年代・元素分析に加え、火山岩中の全岩238U-230Th-226Ra同位体比の新規分析手法を現在開発中である。これらの分析法を国内の第四紀火山噴出物(三瓶火山,戸賀火山,霧ヶ峰等)や箱根・富士火山の試料に適用し,日本列島地下で起こっている地球化学的プロセスの解読を進めている.
また,現存する物質的記録が極めて少ないとされる地球誕生から最初の5億年間(冥王代)の地殻の化学進化を解明する研究も進めている.西部オーストラリアより採取した礫岩より500粒子以上の冥王代ジルコンを発見し,高精度のU-Pb年代測定や化学組成の分析を進めている.特にこれまで冥王代ジルコンでも報告数の少なかった42-44億年前のジルコンも数十粒子集積しており,報告されている最古の地球ジルコン(約44億年前)と同等の年代を持つものも発見した.現在冥王代ジルコンの年代、化学組成を用いて独立成分解析を行うことで44-40億年前の地球最初期の表層・地殻の環境を変化させる機構についての推察を行っている.