領域概要A02 測地観測班(課題番号 JP16H06474)
測地観測によるスロー地震の物理像の解明代表:神戸大学 都市安全研究センター 廣瀬 仁
研究目的
近年、沈み込み帯を中心としたプレート境界域で様々なスロー地震が発生していることが見出されてきた。西日本の南海トラフおよび琉球海溝沿いでは、世界中で最も多彩なスロー地震活動が検出されてきている。しかしながら、その活動の地域性の原因や、地域間の相互作用、異なるタイプのスロー地震間の関連性など未解明な点が多い。そこで本計画研究では、各種スロー地震のなかで最も規模が大きく、それゆえ他のスロー地震の大局的な活動パターンやプレート間のすべり様式を規定していると考えられるスロースリップイベント(SSE)の活動様式を、発生頻度の高い西日本の複数地域にて、GNSS・傾斜・歪・重力等の測地学的観測手段によって詳細に捉え、地域ごとのプレート間のすべり特性、それを規定している地球科学的要因、隣接地域との相互作用、SSE発生と地殻流体との関連性などを明らかにする。さらに他計画研究の観測データ・室内実験結果・数値モデルからの知見と融合することで、スロー地震の理解を通して地震現象の再定義を目指す。
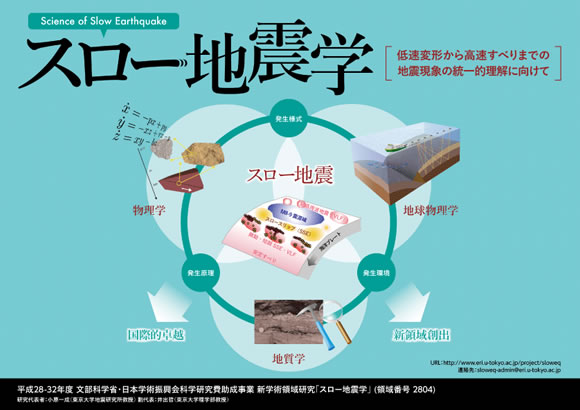
研究内容
測地学的観測手法に基づき、下記の3つのテーマを一体的に推進する。
-
- (A) SSEのすべり範囲特定とその相互作用の解明
- 豊後水道SSEのすべり過程および、これに連動した隣接地域でのSSEの活動パターン変化を詳細に捉えるため、新たにGNSS連続観測点を設置する。これと既存のGNSS観測網・傾斜観測・歪計のデータを統合することで、各SSEのすべり範囲の特定、すべり速度・摩擦特性を明らかにし、隣接SSE間の相互作用を解明する。
-
- (B) SSE発生様式の環境要因の検討
- 年1~2回の頻度でSSEが孤立的に発生している2地域: (1) プレート境界浅部でのSSEが捉えられている沖縄本島周辺域; (2) プレート境界深部のSSEが発生している八重山諸島; をモデル地域とし、GEONETでカバーされていない島嶼部でのGNSS連続観測を行う。それらの地域でのSSE活動様式(発生間隔、すべりの継続時間、深さ範囲等)を明らかにすることで、プレート境界でのすべり特性を規定している要因を解明する。
-
- (C) SSEに関連した地殻流体移動の検出
- 地下深部のSSE発生域に存在する地殻流体が、どのようにSSEの発生と関わっているかを明らかにするため、可搬型かつ連続的に観測できる重力計を導入し、SSE発生・進展に伴う重力変化の検出を試みる。この時間分解能を高めた観測により、流体挙動の同定精度を飛躍的に高める。
メンバー
- 研究代表者
-
- 廣瀬 仁神戸大学 都市安全研究センター
- 研究分担者
-
- 宮崎 真一京都大学 大学院理学研究科
- 松島 健九州大学 大学院理学研究院
- 田部井 隆雄高知大学 教育研究部 自然科学系 理学部門
- 山崎 健一京都大学 防災研究所
- 高木 涼太東北大学 大学院理学研究科
- 田中 愛幸東京大学 大学院理学系研究科
- 木村 武志防災科学技術研究所 地震津波防災研究部門
- 板場 智史産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門
- 研究協力者(教員・研究員)
-
- 西村 卓也京都大学 防災研究所
- 太田 雄策東北大学 大学院理学研究科
- 矢来 博司国土地理院 地理地殻活動研究センター
- 今西 祐一東京大学 地震研究所
- 名和 一成産業技術総合研究所 地質情報研究部門
- 小河 勉東京大学 地震研究所
- 加納 将行東北大学 大学院理学研究科
- 中田 令子東北大学 大学院理学研究科
- 大園 真子東京大学 地震研究所/北海道大学 大学院理学研究院
- 飯沼 卓史海洋研究開発機構 海域地震火山部門 地震津波予測研究開発センター
- 木下 陽平筑波大学 大学院システム情報工学研究科
- 伊東 優治東京大学 地震研究所
研究サブテーマ
- 分担者課題
-
- 廣瀬仁・宮崎真一・松島健・田部井隆雄・山崎健一・西村卓也 「GNSS連続観測による西南日本のスロースリップイベントに伴う地殻変動の観測」
- 高木涼太 「GNSSデータ解析によるスロースリップイベントの検出と微動活動との相互作用の解明」
- 田中愛幸・今西祐一・名和一成・小河勉 「スロースリップ域における精密重力・電磁気観測」
- 木村武志 「傾斜観測(仮)」
- 板場智史 「歪観測(仮)」

