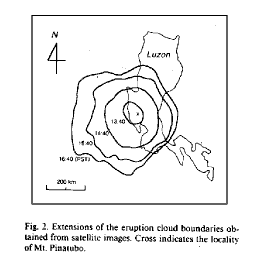
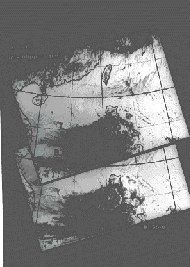
火山学的な意味
火山の噴火では、噴煙が高速度(時速500km以上)で火口から飛び出し、成層圏(上空10km以上)にまで届くような、とても大きな噴火が起こることがあります。噴煙は周囲の大気を取り込みながら、ある高度で水平方向に広がります。その様子が、まるで傘の形に似ていることから、傘型噴煙と呼びます。成層圏に達するような巨大な噴煙の場合には、傘型噴煙は人工衛星ひまわりなどで観測することが出来るほど、広範囲に広がります。たとえば、フィリピンのピナツボ火山1991年の噴火では、直径1000kmに達する巨大な傘型噴煙が9時間以上にわたって観測されました。
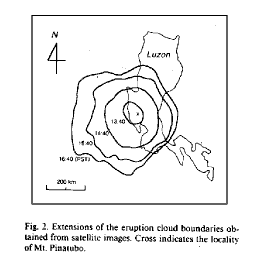
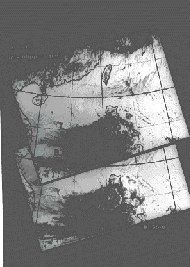
この実験は、そのような巨大な噴煙の拡大を再現する実験です。食塩水の入った水槽の上部から、噴流ジェットで水を注入して、その様子を観察します。とても簡単な実験ですが、傘型噴煙の拡大の様子を正確に予想するためには、とても大切な実験です。
なぜなら、周囲の大気の取り込みのメカニズムは、いまだよく解明されておらず、またそれが、どのように運動に影響しているのかの予想は、実験でしか確かめることができないからです。