課題番号:7009
平成21年度年次報告
(1)実施機関名
気象庁
(2)研究課題(または観測項目)名
活動的火山における全磁力観測
(3)最も関連の深い建議の項目
- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進
- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化
- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域
(4)その他関連する建議の項目
- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進
- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化
- ア.日本列島域
(5)本課題の5か年の到達目標
マグマの貫入に伴う地下の熱的活動の推移を把握するため、雌阿寒岳、草津白根山、三宅島、伊豆大島、阿蘇山等の全国の活動的な火山において、全磁力連続観測および繰り返し観測を行い、観測点の特性調査、解析手法の改善、遠隔データ収集の導入等を通じて、活動的な火山のモニタリング機能の高度化を図る。
(6)本課題の5か年計画の概要
雌阿寒岳、草津白根山、三宅島、伊豆大島、阿蘇山等の全国の活動的な火山において、地磁気の時間変化をより精密に捉えるために地磁気全磁力連続観測を実施し、並行して定期的な全磁力繰り返し観測を行い連続観測点の分布を補いつつ、空間分布において局所的変化として現れる地下の熱的活動の推移を評価する。火山活動に伴う地磁気変動を把握するために、観測点の地形変化の影響や年周変化等の特性調査、並びに解析手法の改良を行い、火山性磁場変化の検出精度の改善を図る。また、火山地帯における観測環境や岩石の磁化を示す全磁力の変化を考慮して、全磁力計の配置の見直し等を適宜行うとともに、遠隔データ収集の導入等により、火山のモニタリング機能の向上に取り組む。
(7)平成21年度成果の概要
雌阿寒岳、草津白根山、三宅島、伊豆大島、阿蘇山において、全磁力連続観測および繰り返し観測を実施し、火口地下の熱活動の経過を分析した。
○雌阿寒岳では、参照点の検討を行い、連続点のテレメータ化を実施し準リアルタイムでのモニタリングを開始した。 2008年11月の噴火以降の火山体内部の熱活動については、年度途中10月から連続点のテレメータ化を実施したので、準リアルタイムにモニタリングし評価できるようになった(図1)。
○草津白根山・伊豆大島については、観測点の特性調査の一環として年周変化等の原因調査のための地中温度測定を継続した。草津白根山では、連続観測点の再配置の検討を行った。伊豆大島では、連続点の地中温度補正の効果にやや改善が見られた(図2)。三宅島については、黒潮の影響による全磁力変化を調査し、三宅島と黒潮の流軸の距離と沿岸付近の新澪池跡の全磁力変化には、定性的に負の相関があることを示した。
○阿蘇山については、地形変化の著しい連続観測点の移設場所の選定と磁場調査を行い、熱活動の推移を容易に把握するために、取得データについて時系列的に磁気双極子解析を行った(図3)。
(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)
- 火山噴火予知連絡会会報第104号
(9)平成22年度実施計画の概要
雌阿寒岳、草津白根山、三宅島、伊豆大島、阿蘇山において、全磁力連続観測および繰り返し観測を行うとともに、モニタリング機能の高度化に必要な連続点のテレメータ化、観測点の見直し、年周変化等の原因調査、データ解析手法の検討等を行う。
(10)実施機関の参加者氏名または部署等名
気象庁地磁気観測所
他機関との共同研究の有無
無
(11)問い合わせ先
- 部署名等
気象庁地磁気観測所調査課 - 電話
0299-43-6909 - e-mail
kakioka@met.kishou.go.jp - URL
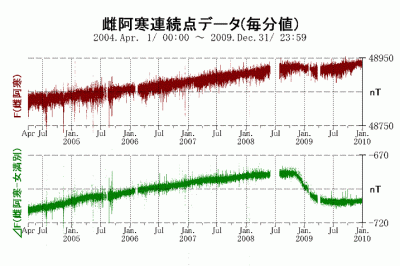
2004年4月~2009年12月の雌阿寒岳山上連続点(上)と参照点(女満別)との差(下)の比較図

伊豆大島連続観測点の全磁力日平均値と参照点(OSM)との差、及び観測点近傍の地中温度変化(上)、並びに地中温度補正後の変化(下)
地中温度測定は予備もふくめ5点あるが、各点で変動も異なり、どのデータを補正に使用するかを検討し補正に使用する地中温度データを抽出し補正を試みた。その結果補正の効果にやや改善がみられるものの、依然としてそれ以外の変動が残る(下)。現在の補正でも、火山活動により2点同時に影響が表れるような顕著な変化はとらえられると考えられる。
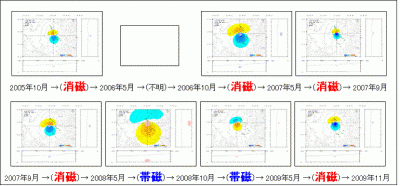
磁気双極子解析結果(阿蘇山)
前回値(約半年前)との差から求めたが、一部の期間については、信頼しうる解析結果を得ることができなかった(不明の部分)。消磁の解析結果に比べ帯磁の解析結果の方がやや深い場所に位置が決まる傾向にあったが、その原因については今後の検討課題となった。