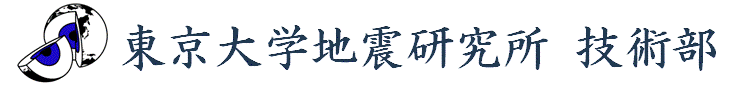「浅間山」特集(その1;臨時観測点と保守)

浅間山は、たびたび噴火を繰り返している活発な火山です。地震研究所は、1933年に日本で2番目の火山観測所として浅間火山観測所を設立しました。以来、日本の火山観測研究の最前線に立ち続けており、火山研究のみならず火山防災にも貢献しています。
| 左側: | 浅間山山頂域での臨時地震観測。火山活動を理解するために、時には臨時観測点を展開します。短期間であれば鉛蓄電池の電力量で十分ですが、数ヶ月から半年の長期間の観測には太陽電池パネルを併用します。 (2008/10/17撮影) |
|---|---|
| 中央: | 積雪期の黒斑山にて。火山活動の監視のために必要であれば、雪中行軍をしてでも観測点の保守に向かいます。さすがに厳冬期は無理ですが、初冬や春先であれば精鋭部隊が作業に行きます。 (2009/03/11撮影) |
| 右側: | 雪に埋もれた湯の平観測点の掘り起こし作業中。積雪による発電量不足と通信障害を解消するために作業をしているところです。雪のない時期には、太陽電池パネルは人の背丈ほどの高さがあります。 (2009/03/11撮影) |
「浅間山」特集(その2;山頂作業)

| 左側: | 火口縁に立って、内部の様子を観察・撮影する技術職員(矢印)。作業で登頂する度に同じ場所から同じ構図で撮影して、火口内の変化を記録します。 (2008/08/12撮影) |
|---|---|
| 中央: | 観測機材を背負って足場の悪い急斜面を登る。火山観測では車輌や機械が入れない場所が多く、人力で機材運搬や設置作業を行います。20kgほどの荷物を背負って歩くのは一苦労です。 (2009/05/11撮影) |
| 右側: | 浅間山山頂火口縁観測点の外に立つ技術職員。一歩踏み外せば250m下の火口底まで真っ逆さまなので、安全のために命綱を付けて作業に当たります。 (2009/05/20撮影) |
「浅間山」特集(その3;定常観測点)

| 左側: | 浅間山山頂火口縁にある観測点の内部。火口縁にはこのような観測点が2箇所あり、地震、GPS、傾斜、空振、可視・赤外画像、火山ガスなど様々な観測をしています。 (2008/10/17撮影) |
|---|---|
| 中央: | 浅間山山頂火口縁にある観測点の外観。この観測点では、観測に必要な電力は太陽電池パネルで発電しています。積雪期には、パネルへの積雪や着氷で発電効率が下がるので電力不足になることもあります。 (2009/05/20撮影) |
| 右側: | 浅間山中腹にある全磁力観測点。岩石は僅かに磁気を帯びていて、マグマの熱の影響を受けてその強弱が変化します。それを連続観測して火山活動の盛衰を判断する材料の1つにします。 (2009/10/14撮影) |
「伊豆大島」特集

| 左側: | 伊豆大島のカルデラ内で全磁力測量。磁力計の高さが変わらないように担いで、ひたすら計測して歩き回ります。測量中は磁場を乱さないように、磁性を持つ物は何も身に着けてはいけません。 (2008/03/05撮影) |
|---|---|
| 中央: | 落雷で故障した観測機器。観測点の直近に落雷があり、ケーブルに誘導電流が流れて観測機器がお亡くなりになりました。この時は、地震計を除いてほぼ全ての計測器が故障してしまいました。地震・火山観測は雷との戦いでもあります。 (2009/08/19撮影) |
| 右側: | 三原山近くの観測点。島内には地震、電磁気、GPSなどの観測点が数十ヶ所あります。地震研究所だけでなく気象庁や防災科学技術研究所、国土地理院も観測点を持っているので、全ての観測点を合計すると80ヶ所を越える世界有数の稠密な観測網が展開されています。 (2009/08/27撮影) |
「無人ヘリ火山観測プロジェクト」特集

活発に噴火活動をする火山に近付くことは危険で、多くの場合は行政機関によって立入禁止措置がとられています。また、険しい地形と脆い地質のために、山頂や火口に接近することが物理的に困難です。しかし、火口近傍に観測機器を設置することができれば、解析精度の向上や近くでしか見えない現象の観測が期待されます。これらを実現するために、無人機での設置や回収が可能な火山観測装置の開発に取り組んでいます。
| 左側: | 桜島で飛行する無人ヘリコプタ(矢印)。地震研究所では、無人ヘリコプタで設置・回収可能な火山観測装置の開発に取り組んでいます。この技術が実用化されると、立入禁止区域や危険な火口近傍での火山観測が可能になります。 (2010/11/12撮影) |
|---|---|
| 中央: | 無人ヘリコプタで設置・回収可能な火山観測装置。この装置を無人ヘリコプタで立入禁止地域の中に設置します。地震計と通信機器を内蔵していて、定期的に地震波形データを送ってきます。 (2010/11/06撮影) |
| 右側: | 無人ヘリコプタ。10kgの荷物(ウインチ等を含む)を抱えて5km先まで飛んで行き、装置を設置して帰ってくることができます。発着場と観測点上空の間は、事前に組んだ飛行プログラムに従って自律飛行します。 (2009/11/04撮影) |
「南極」特集(その1;地震観測点)

2007/3/1〜2009/3/1は国際極年2007-2008でした。その観測計画の一つに南極大陸での広帯域地震観測があり、国際共同観測チームの一員として地震研究所の技術職員が参加しました。東南極の南緯78〜85度、東経38〜130度の範囲に約90km間隔で28点の地震観測点を展開して2年間の観測を行いました。
| 左側: | 南極氷床上の地震観測点。雪面上にあるのは太陽電池パネルとアンテナ類だけで、周囲には100km以上何もない雪原が広がっています。1年ぶりの保守作業に訪れた我々を、幻日が迎えてくれました。幻日とは、弱い風の中を一様に漂うダイアモンドダストによって太陽の上下左右に光が現れる現象のことです。 (2009/12/27撮影) |
|---|---|
| 中央: | 観測点の広帯域地震計。通常は堅固な岩盤の上や観測抗の中に広帯域地震計を設置しますが、氷床上では雪面を1mほど掘り下げた穴の底に設置します。設置した後は、断熱材や保護用のドームで覆って完全に埋め戻します。 (2009/12/22撮影) |
| 右側: | 南極氷床上の地震観測点。広大な南極大陸に観測点が多数展開されているので、キャンプ地と観測点の間は航空機(DHC-6)で移動します。100〜1,000kmも離れているので、片道で40分〜5時間のフライトになります。 (2009/12/31撮影) |
「南極」特集(その2;基地・南極点)

| 左側: | 南極最大の観測基地、マクマード基地(アメリカ)。マックタウンとも呼ばれます。ニュージーランドの南方3,500km、ロス海に浮かぶロス島の南端(南緯77度51分)にあります。夏期は1,000人以上の隊員が昼夜と無く働いていて、冬期でも200人の隊員が滞在しています。 (2009/12/07撮影) |
|---|---|
| 中央: | アムンセン・スコット南極点基地(アメリカ)。南極点のすぐ脇(南緯89度59分)に位置しており、マクマード基地からは1,300km離れています。ここへ来るには、マクマード基地からLC-130輸送機で物資と共に運ばれてくるのが一般的です(パトリオットヒルズ基地からDC3で飛んでくる観光ツアーもあります)。後ろに見えるのは3代目の基地建物で、氷雪に埋もれないように高床式になっています。2009年12月に訪れた時は、2代目のドーム型基地は解体作業中でした。 (2009/12/11撮影) |
| 右側: | 南極点(南緯90度)を示すポール。この付近の氷床は年に数mずつ動いているので、毎年1月1日にGPS測量で南極点を求めてこのポールを立てます。 (2009/12/11撮影) |
「北マリアナ諸島」特集(その1;移動風景)

北マリアナ諸島は小笠原諸島の南に位置しており、Saipan島やTinian島など14の島々からなる弧状列島です。その北側の島々は火山島で、中でもAnatahan島は2003年の噴火以来火山活動が続いています。調査・観測の為にAnatahan島、Alamagan島、Pagan島、Asuncion島、Maug島、Uracus島を訪れました。Anatahan島とUracus島では火山調査、他の島々ではフィリピン海プレートの動きを捉える為のGPS観測を行いました。
| 左側: | 北マリアナ諸島を巡る船旅。遊漁船をチャーターし、2週間を掛けてAnatahan島からUracus島までGPS観測、地震観測、火山地質調査を行いました。写真は噴煙を上げるPagan島。 (2008/07/02撮影) |
|---|---|
| 中央: | Anatahan島に向けて離陸するヘリコプタ。Anatahan島はSaipan島からヘリコプタで1時間の距離にある無人の火山島です。軽量化のために全てのドアが取り外されています。 (2009/07/03撮影) |
| 右側: | SaipanからAnatahanへ向かうヘリコプタの機内。軽量化のためにドアを全て外したキャビンは、素晴らしく開放的です。飛行中はシートベルトをしっかりとお締め下さい。 (2009/01/21撮影) |
「北マリアナ諸島」特集(その2;Anatahan島)

| 左側: | Anatahan島のカルデラ内での火山調査。Anatahan島は、2003年の噴火以後活発に活動する火山です。時には120km離れたSaipan島まで火山ガスが流れて来ます。 (2009/07/03撮影) |
|---|---|
| 中央: | Anatahan島での地震観測。地表は2003年噴火の噴出物で覆い尽くされています。島内の5ヶ所で1年間の臨時地震観測をしました。 (2009/01/20撮影) |
| 右側: | Anatahan島の斜面。厚く堆積した降下物の層が激しい浸食を受け、海岸から山頂まで非常に険しい地形になっています。上陸できる地点は数ヶ所しかなく、この島ではヘリコプタが唯一の実用的な交通手段です。 (2009/01/20撮影) |
「北マリアナ諸島」特集(その3;GPS観測)

| 左側: | Maug島でのGPS観測。Saipan島の北540kmにある無人の火山島で、3つの三日月型の島が円を描いています。 (2008/06/28撮影) |
|---|---|
| 中央: | Uracus島山頂で一休み。北マリアナ諸島最北の島で、Saipan島の北600kmにある無人の火山島です。この島で火山地質調査とGPS観測を行いました。 (2008/06/29撮影) |
| 右側: | Asuncion島でのGPS観測。Saipan島の北500kmにある無人の火山島です。米国USGSが設置した金属標識の直上で観測を行いました。 (2008/07/01撮影) |

| 左側: | 東南海沖で実施された「海底地震計の設置・回収及びエアガン発破観測」における船上作業。海底地震計(オレンジ色の球)を投入する前に、時刻校正をしているところです。このオレンジ色のチタン球の頂部に付いているコネクタ接続用のチタンブロックは、技術開発室にて製作されました。 (2007/07/21撮影) |
|---|---|
| 中央: | 2007/03/25(日)に発生した能登半島地震(Mj6.9)の臨時余震観測の保守作業。地震発生直後に設置した観測装置の電池交換、ディスク回収、及び動作確認をしているところです。ブルーシートに覆われている箱にデータ収録装置と電池が入っており、その左側の園芸ポールには頂部にGPSアンテナが取り付けられています。地震計は、更に左側の橋台の上に据え付けられています。 (2007/04/16撮影) |
| 右側: | タイ王国マヒドル大学構内にある地磁気観測点における地磁気絶対観測。FT型磁気儀を用いて、地磁気の方角を測定しているところです。観測点は直射日光や風雨を避けるために東屋(あずまや)風の建物で囲まれていますが、地磁気の観測に影響を出さないために、建物は木材や葉や紐などの非磁性体だけで作られています。 (2009/01/19撮影) |

| 左側: | 岐阜県南部に構築した衛星テレメータ地震観測点(月尾谷観測点:E.BTKO)の設置作業。本観測網は「濃尾地域震源域の内陸地震合同観測」の一環として構築されました。写真中央には、地上高約2mの位置にパラボラアンテナがあり、観測された地震波形データは衛星経由で常時リアルタイムで地震研究所に送信されています。 (2009/12/07撮影) |
|---|---|
| 中央: | 岐阜県南部における、臨時地震観測点の設置作業。本観測は「濃尾地域震源域の内陸地震合同観測」の一環として、約90点からなる臨時地震観測点を約1km間隔で稠密にアレー配置して、約半年間実施されたものです。写真は、データ収録装置の設定を行っているところです。 (2009/06/03撮影) |
| 右側: | 地震研2号館地下1Fにある地震計博物館で稼働している煤書き式地震計。この地震計は半世紀以上前に開発された「萩原式変位地震計」であり、左側が東西成分、右側が南北成分の記録を示しています。地震波形は、煤が付いた紙を針で引っかくことで描かれており、数時間前に発生した地震が記録されているのが分かります。この地震計博物館の運用や煤付け作業などに、技術部は関わっています。 (2009/02/27撮影) |

| 左側: | 2007/03/25(日)に発生した能登半島地震(Mj6.9)の臨時余震観測時の保守作業。地震発生直後に設置した臨時地震観測装置の電池交換、ディスク回収、及び動作確認をしているところです。 (2007/04/12撮影) |
|---|---|
| 中央: | 東南海沖で実施された「海底地震計の設置・回収及びエアガン発破観測」時の船上作業。1年間の海底での自然地震観測を終えた海底地震計(オレンジ色の球)を船上に回収し、清水で洗っているところです。 (2007/07/21撮影) |
| 右側: | トンガ王国にある地磁気観測点におけるプロトン絶対磁力計の保守作業。磁力計センサーは、地面による磁気擾乱を避けるために地上高約1.8mに設置されています。この観測点にはフラックスゲート型磁力計(相対磁力計)も設置されており、土地調査天然資源環境省(MLSNRE)と協力して運用がなされています。 (2010/09/08撮影) |
「臨時地震観測用機材の準備状況」特集

| 左側: | 新潟県で実施された「中越沖地震余震域の発破観測による構造探査」時における、臨時観測機材の準備作業。約200台の白山工業製臨時地震観測装置(LS-8200SD)に対して、これから電池詰めと観測スケジュールの設定作業を行うところです。これらの装置は、3日間かけて約300m間隔でアレー状に設置され、小規模なダイナマイト爆破を数ヶ所で実施してその地動記録を収録後、回収されました。 (2007/09/13撮影) |
|---|---|
| 中央: | 中国東北部における大規模機動地震観測網(NECESSArray)プロジェクトで使用する広帯域地震観測機材を、北京大学の研究室にて開梱して動作確認を行っているところ。NECESSArrayは約80km間隔で120点の臨時広帯域地震観測網を構築して2年間観測するプロジェクトであり、この動作確認後、約35人のメンバーが8台のSUV車と4台のトラックに分乗して、約2週間かけて設置を行いました。(2009/09/09撮影) |
| 右側: | 岐阜県南部における、臨時地震観測網設置前の機材の準備作業。本観測は「濃尾地域震源域の内陸地震合同観測」の一環として、約90点からなる臨時地震観測点を、約1km間隔で稠密にアレー配置して約半年間実施されたものです。それらの機材に電池を詰める作業をしているところです。 (2009/06/11撮影) |
「NECESSArrayプロジェクト」特集(その1)

NECESSArrayとは「中国東北部における大規模機動地震観測網(North East China Extended SeiSmic Array)」の略で、約80km間隔で120点の臨時広帯域地震観測網(東西約1,500km×南北約600km)を中国東北部に構築して2年間観測するプロジェクトのことです。
| 左側: | NE31観測点。NECESSArrayではセキュリティの観点から、観測点は民家の敷地脇や建物内に設置されています。この観測点は35点あるソーラーパネルの観測点の中の1点で、その他はAC230Vを民家からもらっています。写真中央のソーラーパネルの左奥に、地震計とデータ収録装置が埋められています。 (2009/09/13撮影) |
|---|---|
| 中央: | NE52観測点の設置作業。左側の発泡スチロール板に覆われた箱の中に地震計が設置されており、右側の白い箱の中にデータ収録装置が入っています。両者共に気温変化を抑えるために地中に設置されています。 (2009/09/16撮影) |
| 右側: | NE72観測点の設置作業。写真奥には、モンゴルの広大な平原が広がっています。この観測点では、家畜の馬・豚対策のために、この後2重のフェンスを建てて観測点を囲いました。 (2009/09/05撮影) |
「NECESSArrayプロジェクト」特集(その2)

| 左側: | 小諸地震火山観測所における地震計埋設実験。本プロジェクトでは、気温変化による影響を抑えるために地震計は地中に埋めて設置します。その埋設方法の実験を、中国での本番設置前に国内で行いました。地震計は、モルタル土台が乾いた後に青い筒の中に設置され、蓋をした後に砂で埋め戻されます。 (2008/04/17撮影) |
|---|---|
| 中央: | 小諸地震火山観測所における地震計埋設実験。モルタルも現場でこねて作りました。 (2008/04/17撮影) |
| 右側: | NE55観測点の保守作業。NECESSArrayでは、データの回収のために半年に1度現地に訪問する必要があります。この写真は、設置後2度目のデータ回収時のものです。気温がマイナス20℃を下回ることもある現地の過酷な環境の影響で、地震計にトラブルが発生していたために、地震計を埋設した穴(深さ1m弱)を掘り返してメンテナンスをしているところです。 (2010/04/19撮影) |
「南アフリカ金鉱山」特集

本プロジェクトでは、ムポネン金鉱山の地下3.2kmにある坑道脇に、岩脈をまたぐ形で計9台のボアホール地震計を設置しました。その目的は、採掘作業に伴う応力変化によりこの岩脈が断層となって地震を発生させる時の動的成長過程を極至近距離で観測することです。実際に、更に約200m地下にある坑道脇に2007年に設置したAEセンサー観測網では、2007年12月27日(木)に観測網からわずか6mの場所でM2.1(断層長100m規模)の地震が発生し、その本震・余震活動の詳細な分析により、活動の推移や空間的広がりについて多くの知見を得ることが出来ました。
| 左側: | セメントペーストをこねているところ。ボアホール地震計をボアホール内で固定させるために、地震計設置前にボアホールに入れられます。 (2008/06/13撮影) |
|---|---|
| 中央: | ボアホール地震計の設置作業。地震計は長さ1.522mの白いパイプに取り付けられており、そのパイプを何十本も繋げることで最大地下90m近くにまで下ろして行き、先に投入しておいたセメントペーストの中に貫入させます。そしてセメントペーストが固まる数日後に再度訪問し、地震計と地震計に繋がっている数本のパイプのみをセメントペースト内に残して残りのパイプを外すことで、地震計設置は完了となります。 (2008/04/04撮影) |
| 右側: | ボアホール地震計を設置する場所の測量をしているところ。 (2008/04/01撮影) |
岐阜県南部における「臨時稠密アレー地震観測」特集

本観測は「濃尾地域震源域の内陸地震合同観測」の一環として、約90点からなる臨時地震観測点を約1km間隔で稠密にアレー配置して、約半年間実施されたものです。
| 左側: | NB41観測点(岐阜県本巣市)の設置作業。青い箱はデータ収録装置と電池を格納する箱で、その左側の園芸ポールには頂部にGPSアンテナが取り付けられています。地震計は、ガードレール端の下に、石に囲まれて設置されています。 (2009/06/03撮影) |
|---|---|
| 中央: | NB61観測点(岐阜県関市)の設置作業。地震計を埋設する穴を掘っているところです。 (2009/06/04撮影) |
| 右側: | NB67観測点(岐阜県関市)の設置作業。雨が降っていても作業は続けられます。擁壁や堰堤は、構造物として大きく重量があり、また岩盤や基盤岩と繋がっていることが多いので、臨時観測時には地震計の設置によく利用されます。 (2009/06/05撮影) |
岐阜県南部に構築した「衛星テレメータ地震観測網」特集

本観測網は「濃尾地域震源域の内陸地震合同観測」の一環として構築されました。
| 左側: | 大桑観測点(E.BOOG)の設置作業。スペクトルアナライザを見ながら、パラボラアンテナによる衛星電波の受信状況を確認しているところです。 (2009/12/09撮影) |
|---|---|
| 中央: | 千疋観測点(E.BCBK)の保守作業。衛星テレメータによるデータ通信に欠測が頻発していたため、予備機材と交換するために訪問しました。この程度の積雪ならば、作業は行われます。 (2010/02/16撮影) |
| 右側: | 徳山ダム観測点(E.BTOK)の設置作業。地震計を設置して、ビニール袋でカバーしているところです。地震計は更に、コンクリート枡によって完全に覆われます。 (2009/12/15撮影) |
- 3枚並べた画像サイズは1,200x300pxです。1枚あたりだと400x300px(=縦横比4:3)です。
Copyright © 地震研究所技術部 All Rights Reserved.