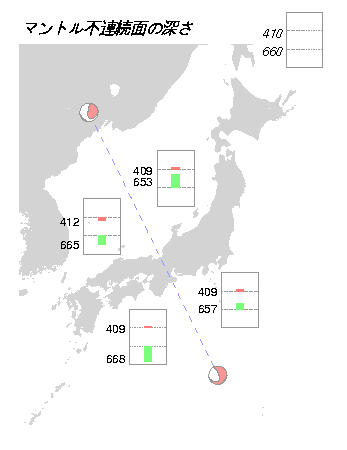
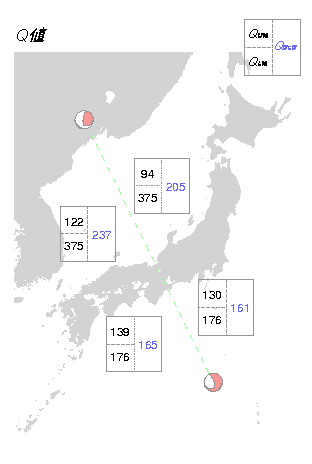
Chapter 4. 解析結果
スタック波形から求まったパラメタを示す (UM=上部マントル、LM=下部マントル)。
*不連続面のパラメタ
*層のパラメタ
マントル不連続面の深さとQ値を地図上に示したのが下図。
注目すべきは、660km不連続面は領域Aで最も深くなっていることである。 隣の領域Bと比べると約10km深くなっている。また、日本海でも 西側が深いことが認められる。 一方、410km不連続面の深さに特に傾向は見られない。
またQ値は各セルの右側に、求まった値から計算されるQScSの値も示した。 このQScSの値の平均(185)は、過去の研究と調和的であるが、 太平洋側が日本海側よりも低い(すなわち高減衰)。 得られた下部マントルのQ値は日本海側と太平洋側で大きく異なっている。 下部マントルは上部マントルに比べ、水平方向の変化が少ないと考えられて いて、しかもごく近傍でこれだけ異なるとは考えにくいから、 この結果はちょっと疑わしい。このようになる要因をいくつか 考えることができるが、今回の解析ではどこに原因があるかは断定できない。 しかし、Q値の構造が太平洋側と 日本海側で違うということは、間違いない。
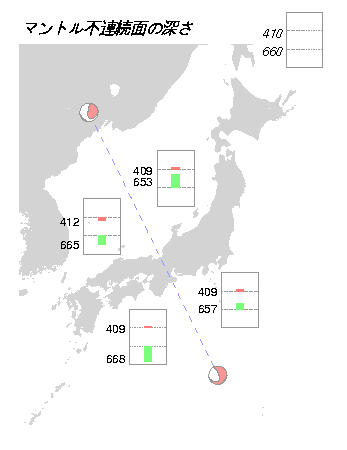 |
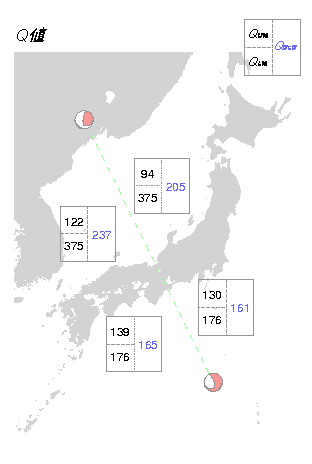 |
またiasp91の不連続面の反射係数は、410km不連続面が4.8%、 660km不連続面が6.7%であるが、データから得られた値も同程度で あった。 PREMの660km不連続面の反射係数は7.8%であるが、 これよりも有意に低い。
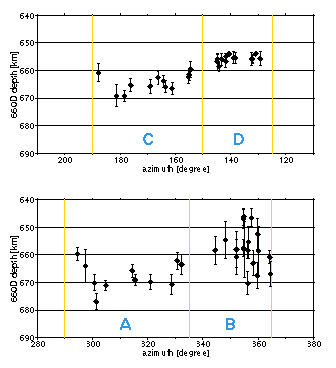
ところで、さらに空間分解能をあげて660km不連続面の形状を決定 できるのではないかと考え、個々の観測点のデータを調べた結果が 左図であるが、不確定性が大きくて、議論することはできなかった。 さらなる分解能の向上は今後に期待したい。
また以上では410kmと660kmの不連続面のみ考慮してきたが、
さらに他の不連続面が存在するかを考えた。
スタック波形に対して、グリッドサーチから求まった層構造を仮定し、
さらに410km・660km以外の不連続面をひとつ挿入した場合に、
相関がより改善されるかどうかを調べた。
パラメタはこの不連続面の深さと反射係数である。
サーチをした結果、領域Aで2750kmの深さに+3.5%の反射係数を
持つ反射面があると、より波形を説明できることがわかった。
2750kmは、CMB直上250kmの深さに相当するので、この
反射面は
D”層の上面だと考えられる。一方で、他の領域ではこのような
兆候は見られなかった。これは、D”層の起伏が激しいことを意味しているのかも
しれない。
また、 沈み込み帯の中部マントルに、何らかの不連続面が存在する という研究結果も出されているが、この反射面の存在を積極的に肯定する結果も、 残念ながら得られなかった。反射面はあったとしても反射係数が小さく、 反射波は微弱だと考えられる。 今回の解析の範囲においては、検出は難しいだろう。