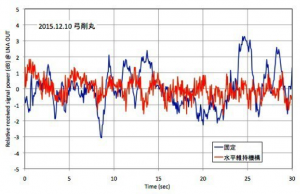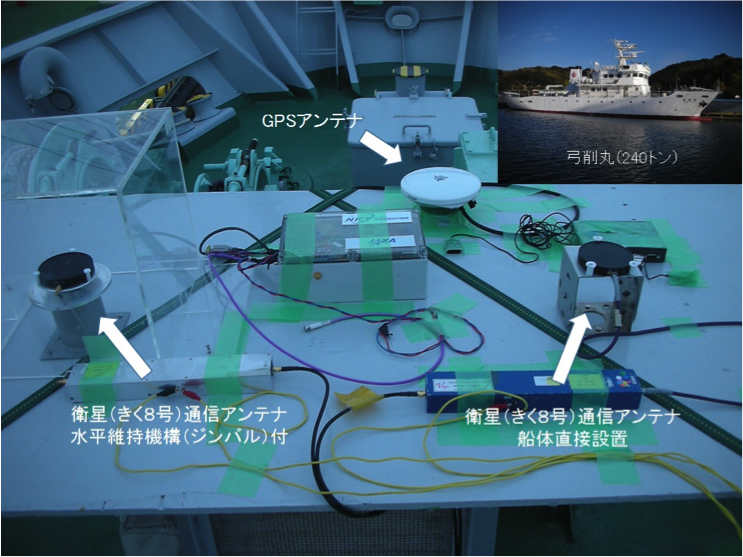カテゴリー別アーカイブ: 部門・センターの研究活動
3.1.4 大気・海洋現象が引き起こす固体地球の弾性振動現象
大量の地震計・気圧計・水圧計などのデータを丹念に解析し,ノイズと思われていた記録の中から新たな振動現象を探り当て,その謎の解明を目指している.その際,大気-海洋-固体地球の大きな枠組みで現象を捉える事が重要である.
(5-1) 常時地球自由振動の励起スペクトルの推定
グローバルに展開されている広帯域地震網のデータを使い,常時地球自由振動の励起スペクトルを推定した.周期200秒より短周期の帯域では,地表付近に分布するrandom shear tractionで励起を説明できるが,長周期側では圧力擾乱が存在しなくてはならない事を明らかにした.この結果は,長周期帯域では大気擾乱も励起に寄与していることを示唆している.
(5-2) 常時地球自由振動の相互相関解析によって明らかにされた,全球的に伝わる実体波
地震波干渉法の研究では,地震波の中でも主に表面波(Rayleigh波,Love波)によって内部構造が調べられてきた.しかし表面波を使う場合には,どうしても上部マントルより深い領域の構造を調べることは難しい.深い領域を調べるには実体波を使うことが非常に有効であるが,信号が小さいために技術的な困難がともなうためである.本研究では,全世界的に展開されている高品位・長期間かつ多量のデータを地震波干渉法解析することにより,初めて全球的に伝播する実体波の抽出に成功した.また大西洋で2014年12/9発生した爆弾低気圧によって励起された脈動P波・S波の検出にも成功した.
(5-3) 西之島の空振モニタリング
2013年11月20日に海上保安庁により新島の形成が報告されて以来,小笠原諸島・西之島では活発な噴火活動が続いる。一般にアクセス可能な小笠原村父島であっても東に130km離れており,連続的な観測情報は非常に限られている。しかし気象条件が良ければ,空振 (人には聴こえない低周波音波)は100km以上離れていても伝わることがある.そのため,父島での観測から西之島火山の活動状況を把握できる可能性がある.そこで父島にオンライン空振観測点(EV.CHI)1点とオフラインの空振計3点(OGW1,OGW2,OGW3)を設置し,西之島火山の空振モニタリングを開始した.本研究では特に,オンラインの2点のみを使っても空振のモニタリングが可能であることを示した.
3.1.3 火山現象の数理的研究
発的噴火から溶岩ドーム噴火までの多様な火山噴火現象の統一的理解と,観測データに基づく噴火条件の推定手法の確立を目指し,理論的研究と数値実験を行っている.具体的な研究課題としては,火山噴煙・火砕流のダイナミックスを対象とした大規模シミュレーション研究,および,火道におけるマグマ上昇に関する理論的研究を進めている.
火山噴煙については,近年,気象レーダーや人工衛星を用いた観測によって噴煙高度やその拡大が高精度で測定されるようになってきた.そこで,これらの観測データから火口での噴出条件や噴火強度を推定するモデルの開発と,鍵となる物理過程を表すパラメータの決定を目的とし,3次元噴煙モデルを用いて様々な噴火条件・大気条件に関する数値実験を行った.また,野外調査で得られる火山灰分布から噴煙ダイナミクスと噴火条件を再構築するために,流体計算と粒子計算を組み合わせた火山灰輸送・堆積の高精度モデルの開発とそれによる大規模シミュレーションを進めている.更に,実際の噴火で多項目的に得られた観測データ・野外調査データを整合的かつ定量的に説明することを目的として,大規模噴火のフィリピン・ピナツボ火山の1991年噴火事例,中規模噴火のインドネシア・ケルート火山の2014年噴火事例,小規模噴火の霧島山新燃岳の2011年噴火事例,水蒸気噴火の御嶽山2014年噴火事例,マグマ水蒸気噴火の口之永良部島2015年噴火事例といった幅広い代表的噴火事例に関する再現シミュレーション研究を進めている.
火道流については,1次元火道流モデルを用いて,爆発的噴火における噴火様式の推移に対する火口形状の影響,および溶岩ドーム噴火から爆発的噴火への遷移に対するマグマの脱ガスや結晶化の影響を系統的に評価した.また,火道流モデルと噴煙柱ダイナミクスモデルを組み合わせることによって,噴煙柱崩壊による火砕流の発生条件を解析的に決定した.さらに,火山周辺の地殻変動観測や噴出率観測と1次元火道流モデルを組み合わせることによって噴火の推移予測を行うデータ同化の理論的枠組みの構築を進めている.
3.12.8 国際共同研究
IPGP との共同研究として,琉球列島におけるサンゴ・マイクロアトールの調査を行った(3.12.7参照).このために,2月にIPGPの研究者が,2-12月に特任研究員が,6-7月には技術職員が来日して,調査地域の選定・サンプルの採取を行った.
JSTによる戦略的国際共同研究プログラム(SICORP)の日米共同研究「ビッグデータと災害」の研究を継続した.米国側はアリゾナ州立大学の研究チームである.2016年度の成果としては,首都直下地震が発生した時の携帯電話網の被害状況を,内閣府の首都直下地震の推定震度情報による停電地域のモデル化と,東日本大震災の際の各基地局のバッテリー保持時間の統計情報による基地局停波の確率予測に加えて,国土地理院による土地建物利用情報を用いた地震時の停電と復電の確率モデルの構築,クラウドソーシングによる基地局情報の活用と,それらのすべてのデータを用いて,時間的・空間的に分析する方法を開発し,その結果をGISを用いて可視化することに成功したことが挙げられる.この成果は,ウイーンで開催されたIEEE ICT-DM2016 国際会議において発表され,本会議における最優秀論文賞を受賞した.
2016年2月12日~14日に地震研究所で国際研究集会を開催した(地震研究所所長裁量経費による).タイトルは「Symposium on Subduction zone earthquakes in Nankai Trough & Japan Trench」であり, 8名の国外研究者を招聘し,合計26件の講演及び32件のポスター発表を行った(参加者約90名).
2016年6~7月にかけて,インド工科大学の学生インターン(理学部によるUTRIP招聘学生),および台湾中央大学の大学院生インターン(JSTさくらサイエンスプログラム)の2名とともに,南海トラフ巨大地震発生帯における深部掘削データと3次元地震探査データを統合し,地下の3次元間隙率および熱伝導率分布を計算した.その結果分岐断層直下の低速度層(高間隙率層)が一様に広がるのでないことが明らかになった.成果を地震学会(10月5日,名古屋)で発表した.
国際深海科学掘削計画(IODP)による南海トラフ地震発生帯掘削(NanTroSEIZE)のプロジェクト調整会議(12月,サンフランシスコ)に委員として参加し,掘削計画の打ち合わせ,および掘削時に実施予定の3次元垂直地震探査(3D-VSP)について、昨年に引き続き,日米欧の関係者で協議した.
3.12.7 古い地震・津波の研究
(1) 古い地震記録に基づく地震・津波の研究
地震研究所や気象庁などに保存されている古い地震記録を用いて過去に発生した大地震の研究を行っている.日本海東縁部で20世紀に発生した大地震について地震・津波波形記録を用いて断層パラメータの推定を行った.また,1944年東南海地震と1946年南海地震に対して,地震後に東京帝国大学が行ったアンケート調査の資料から,震度分布の検討を行った.最近の地震観測網による地震学データとの比較に基づき古い地震の震源・メカニズムを決定する新たな手法を構築し,明治・大正期の大地震に適用した.
(2) 史料に基づく古地震・津波の研究
地震研究所では『新収日本地震史料』等の史料集を刊行してきたが,これらは電子化されておらず検索などが困難である.明治期以降に編纂された二次資料が同時代に書かれた史料と同様に扱われていたり同時代史料でも省略や誤記が含まれていたりするなどの問題点があった.そこで,史料集を電子化した上で,原本もしくは翻刻した刊本を参照して点検する校訂作業を行っている.
関東地方の地震については,1600年代から1800年代の地震までの史料の電子化・校訂作業を行い,データベースとして公開する準備を行った.また,1855年安政江戸地震に関して,関東地域で新たな史料調査を行ったほか,全国スケールでの震度分布を推定した.再検討した震度分布と三次元減衰構造を考慮した震度計算との比較から,この地震は地殻内地震・太平洋プレート上面・太平洋プレート内部で発生した可能性は低く,フィリピン海プレートに関連する地震であった可能性が高いことを明らかにした.
(3) 地質痕跡に基づく古地震・津波の研究
三陸沿岸宮古市において津波堆積物の調査を行い,浜堤背後の湿地で過去2000年間に発生した17層のイベント堆積物を発見した(図3.12.7).2011年東北地方太平洋沖地震の津波堆積物の特徴を考慮して,これらのイベント堆積物の起源を推定した.福島県南相馬市でも2011年及び過去に発生した津波堆積物を調査し,粒度分析・化学成分分析・年代測定などを行って,これらの起源を検討している.千葉県九十九里町において,古文書・地図に基づいて津波堆積物調査を実施し,複数枚のイベント砂層を検出し,その発生年代を推定した.琉球海溝沿いの与論島・沖縄本島で,サンゴのマイクロアトールの形状・年代から過去の水面変動を復元するための調査を行い,分析を行っている.
3.12.6 巨大地震・津波の研究
津波データや測地データ,地震データを用いて,世界の巨大地震の断層運動の詳細や津波の発生過程について調査している. 南米で発生した2010年マウレ地震,2014年イキケ地震,2015年イヤペル地震,2016年エクアドル地震について,遠地地震波や津波データなどから断層面上のすべり分布と破壊伝播速度の推定や太平洋を横断する津波の特性の解明を行った. この他,2015年にソロモン諸島で発生した地震や2016年にインド洋で発生した横ずれ断層地震について,遠地実体波及び津波波形の解析を行って津波の発生過程を調べた.インド洋マカラン沈み込み帯で1945年に発生した地震について,断層運動及び副次的な海底地すべりが起源であることを定量的に示した.米国カスケード沖に展開された海底地震計アレイに附置された水圧計データの解析を行い,2010年ハイダグァイ島地震からの津波波形の解析とデータ同化を試みるとともに,分散性を考慮した津波伝播の影響を調べた.2011年東北地方太平洋沖地震について,遠地での津波波形記録から,津波伝播時の分散性を考慮して波源の特性を調べている.
日本海の自由振動について,その特性を調べて分類したほか,日本海東縁部の断層について,モード解を用いてそれらの津波励起特性を調べた.分散性のある津波の波線追跡法とグリーンの法則を改良した波源での波高推定法を開発し,2015年に発生した鳥島で発生した火山性津波地震の海底水圧計アレイ記録に適用した.
2011年東北地方太平洋沖地震,2010年マウレ地震,2004年スマトラ・アンダマン地震の断層モデルから,実際に発生した地震のメカニズム解を受け手側の断層としてクーロン応力変化を計算し,少なくとも2011年と2004年の地震については,活発化した地震活動の多くが本震による応力変化で説明できることを統計的に示した.
3.12.5 日本列島の地震活動を予測するモデルの作成(CSEP-Japan)
地震カタログデータに基づく確率論的な予測を行うために,すでに先行して同種の研究CSEP (Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability)を世界規模で実施しているSCEC (Southern California Earthquake Center) と連携を図り,2008年にCSEPテストセンターを立ち上げ,日本における地震発生予測検証実験を実施している.テスト領域として日本,内陸日本および関東,テストクラスとして1日,3ヶ月,1年および3年の合計12のテスト環境が実現され,提案されている地震予測モデルは160を超え,CSEPに参加している研究機関の中でも最多である.当センターでも地震活動評価に基づく新たな評価手法の開発を行っている. 2011年3月の東北地方太平洋沖地震後の地震予測においては,関東領域および日本領域において大森宇津則を適用することにより地震数の予測が高精度化されることがわかった(図3.12.5).
3.12.4 高密度強震観測データベース
(1) 首都圏強震動総合ネットワークSK-net の構築と運用
首都圏強震動総合ネットワーク(SK-net)は,首都圏の10 都県の14 観測網から,合計932 観測点(図3.12.4)の強震波形データを収集するシステムである.これらの観測網のデータ収集方式やフォーマットはそれぞれ異なるので,一旦共通フォーマットに変換してデータベース化し,加速度,速度,変位を求めて,最大値,SI (Spectral Intensity) 値,速度応答スペクトルなどとともにSK-netウエブサイトで一般に公開している.オリジナルの波形データは,全国の大学等の研究者の利用を可能にしており,2016年度は54名の利用申請を受け付けた.データは,1999年1月から2017年3月までに収集されたデータを順次利用可能にしている.
自治体の震度計の更新により収集システムも更新が必要となり,5県については,新しい波形収集装置を開発してオンライン収集を継続し,残りの県についてもオフラインでデータ提供して頂いている.最近では,横浜市が約150点の強震観測点を42点の震度観測点に更新したことから,サイトを介したオンライン収集方式に変更した.
東北地方太平洋沖地震については,本震や余震の波形データ量が膨大なため,一部の県でオンライン収集が困難な事態が発生した.現地の震度計からのデータ回収を実施してデータベースに格納した結果,783の観測点からの波形データがホームページで公開されている.
SK-netの開発当初から最近までの,首都圏の10 都県の14 観測網からの波形データ収集の現状については,2014年度末に地震研究所技術報告2014に詳細を報告し,2015年度の地震学会秋季大会においてその概要を発表した.
(2) IT 強震計の開発
IT強震計は,最近のIT技術を利用して,従来の強震計より高密度な観測を可能にすることを目的として開発された.震度0~1程度の地震動から観測可能で,身近な場所の日頃の弱い揺れを観測して地域の地盤や建物の特徴を探り効果的な防災対策にも活用可能である.
本センターでは,IT 強震計のプロトタイプを開発し,地震研究所の各建物内に設置し,弱い地震時の記録から,それぞれの建物の揺れの特徴をとらえたり,耐震補強前後の振動特性の変化をとらえたり,東北地方太平洋沖地震の前後の建物剛性の変化をとらえることなどに成功している.2009年度より情報学環総合防災情報研究センターと共同で学内の建物にも設置を開始し,2011年より以下のホームページ(学内限定)IT強震計東大プロジェクトにおいて有感地震時の観測データを公開して利用可能にしている.さらに,2013年度からは,3キャンパスの9棟に設置された.各キャンパスの地盤と建物の揺れを携帯電話などにメール配信する「学内地震速報」メールを提供している.2016年度は引き続き,これらシステムの内容の充実を行っている.なおIT強震計の産学連携共同研究組織「 IT強震計コンソーシアム(代表は,2015年9月から災害部門の楠浩一准教授に交代)」の運営サポートも行っている.
3.12.3 地震データ解析とその公開
本センターではWWWサーバを立ち上げ,地震・火山等の情報提供を行ってきた.アウトリーチ室(現広報アウトリーチ室)が設置されてからは,本センターはそれをサポートしている.また,観測開発基盤センターとともに年2回,気象庁において地震波形自動処理の技術移転のための研修を行っている.
(1) 地震カタログ解析システム等
研究者向け情報としては,日本や世界の地震カタログをデータベース化し,地震カタログ検索・解析システムTSEISを開発し,地震活動解析システムとして公開している(図3.12.3) .
利用可能な地震カタログは,国立大学観測網地震カタログ(JUNEC) ,防災科学技術研究所地震カタログ,気象庁一元化地震カタログ,グローバルCMT地震カタログ,ISC 地震カタログなどで,多くの研究者に活用されている.また,我が国の地震や世界の地震について気象庁やNEIC などが速報として提供したものを,国内の研究者にメール配信している.気象庁の一元化震源については,そのミラーサイトを運用し,大学等の研究者に提供している.2011年からは,International Seismological Centre (ISC)で維持・管理されているISC Bulletinデータベースのミラーを構築・維持している.2014年には,JUNECのデータから初動メカニズムを決定したJUNEC FM2を利用可能とした.
(2) 長周期波動場のリアルタイムモニタリングGRiD MT
全国地震観測データ流通ネットワークJDXnet で提供されている広帯域地震波形データを利用して,震源速報等の地震情報を必要とせずに,地震の発生・発震機構(MT 解)・大きさ(モーメントマグニチュード) をリアルタイムに決定する新しい地震解析システムGRiD MT (図3.12.4)を開発して,その解析結果をWeb やメールでリアルタイムに情報発信している.現在までに得られた,解析結果についてはGRiD MTウエブサイトで公開している.巨大地震や津波ポテンシャルをW-phaseにより評価するイベント駆動型のシステムを開発し,解析結果を世界中の地震のサイトおよび日本の地震のサイトにて公開している.
(3) 古い地震記象の利活用
地震研究所には各種地震計記録(煤書き) が推定で約30 万枚ある.この地震記録を整理し利用しやすい環境を作るため,本センターが中心となって所内に「古地震記象委員会」が設置され,1) マイクロフィルム化,2) 検索データベースの作成,3) 原記録の保存管理などが行われている.煤書き記録については,約22 万枚のマイクロフィルム記録のリスト,WEB 検索システム(日本語・英語)を作成し,国内外のユーザーの利用に供している.津波波形記録については,マイクロフィルムと,スキャナーでスキャンしたデジタルデータが津波波形データベースシステムで公開されている.
このほかに,20 世紀の巨大地震の世界各地での地震記象を入手しており,それをスキャンし,画像データとして保存し公開すべく作業を進めている.劣化が始まっているWWSSN フィルムの長期保存のための表面処理とファイリングないしはリール分割や筑波地震観測所HES記録の修復作業も行っている.また,濃尾地震や鳥取地震等の過去の大地震のアンケート調査や報告書などの資料のPDF化を行い,公開すべく準備を行っている.今年度は,平成28年(2016年)熊本地震の発生を受け,明治22年(1889年)熊本地震に関する報告書を公開した.