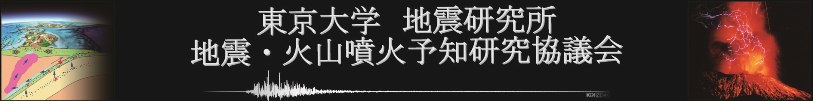
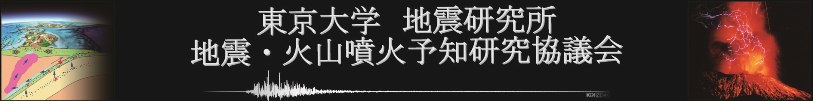 |
過去のお知らせ
|
最新ホームページはこちら 「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」平成25年度成果報告シンポジウム平成21から25年度まで実施してまいりました「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」の平成25年度(最終年度)成果報告シンポジウムが下記の要領で開催されます.皆様のご参加をお待ちいたします.主催:「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」成果報告シンポジウム実行委員会 共催:地震・火山噴火予知研究協議会 後援:文部科学省 日時 平成26年3月12日(水)10:10 ~ 14日(金)13:00 場所 武田先端知ビル 5F 武田ホール・ホワイエ (東京メトロ千代田線「根津」駅徒歩5分, 東京メトロ南北線「東大前」駅徒歩8分) 参加無料。事前登録不要。 プログラムは以下からご覧になれます. 口頭発表 , ポスター発表 (最新のものに随時更新しています)。 課題別報告書 次期研究計画「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進について」が建議されました平成25年11月8日に開催されました科学技術・学術審議会において,平成26年度から平成30年度までの期間に実施予定の次期の研究計画「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進について」が,文部科学大臣をはじめ関係大臣に建議されました。学術フォーラム「地殻災害の軽減と学術・教育」の開催東日本大震災を経て,地震研究の在り方が問われております。次期研究計画では,災害科学の一部として地震・火山の観測研究を推進する方針に転換しました。その推進のため,地震学や火山学を中核とし,理学,工学,人文・社会科学の連携が強く望まれています。その趣旨に沿って,地震や火山噴火などの地殻災害をテーマとして,文理の連携と融合の実現をめざす学術フォーラム「地殻災害の軽減と学術・教育」が,以下の通り開催されます。皆様の参加をお待ちします。日時 平成25年11月16日(土) 10:00~17:00 場所 日本学術会議講堂(東京メトロ千代田線「乃木坂」駅すぐ) 参加無料。事前登録不要。 詳しくはここをご覧ください。 次期研究計画「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」の意見公募平成25年8月29日に開催されました科学技術・学術審議会測地学分科会において,平成26年度から5ヶ年実施予定の次期研究計画案(中間まとめ)が承認されました。この計画について,国民の皆様のご意見を広く伺うため,意見公募(パブリック・コメント)を開始しました。パブリック・コメントは9月4日~10月3日の期間,以下のURLで行われております。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000653&Mode=0 次期研究計画の策定状況について現行の「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」が平成25年度末で終わることから,科学技術・学術審議会測地学分科会地震火山部会は,次期研究計画検討委員会(主査:末廣潔,主査代理:加藤尚之,西村太志)を設置し,昨年の12月末から次期研究計画の検討を開始しました。次期研究計画の策定においては,昨年10月にまとめられた外部評価報告書,見直し計画策定の際の意見,科学技術・学術審議会総会でまとめられた「東日本大震災を踏まえた今後の科学技術・学術政策の在り方について(建議)」の指摘を真摯に受け止め,「社会の中の科学」と言う視点が重視されました。 また,次期計画検討委員会には,これまでの計画の中心を担ってきた地震学,火山学,測地学の分野の研究者や関連研究機関や行政官庁の担当者の他に,防災社会学や歴史学の研究者も加わり,8回にわたり熱心な議論が行われました。 次期研究計画案は7月8日の委員会で取りまとめられ,7月13日開催の地震火山部会で内容が検討され,若干の修正が加えられました。その後,7月26日開催の測地学分科会で審議され,計画の名称を「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究(仮称)」とすることが決まりました。8月2日の科学技術・学術審議会総会では,審議経過報告として次期計画案が提出されました。 今後,測地学分科会,地震火山部会で審議が重ねられ,計画案に修正が加えられます。また,9月上旬から意見公募が行なわれる予定です。最新の計画案を適宜文書記録に更新しておきますので,ご参照ください。 平成24年度成果報告シンポジウム開催平成25年3月6日~8日に, 東京大学武田先端知ビル5階武田ホール において「地震及び火山噴火予知のための観測研究」平成24年度成果報告シンポジウムを開催します。( プログラム) 「地震・火山噴火予知研究協議会外部評価報告書(平成25年1月)」地震・火山噴火予知研究協議会の平成18~23年度の活動に関する外部評価が行われ,外部評価報告書がまとめられました.この提言を尊重して,今後の予知協議会の運営に活かす予定です.地震・火山観測研究における年次基礎データ(平成24年度版)平成24年12月19日に開催された科学技術・学術審議会測地学分科会地震火山部会 観測研究計画推進委員会が開催され,大学以外の機関を含む日本全体の地震・火山観測研究関連の予算,研究者数の推移を調査した基礎データが公表されました.「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の見直しについて」平成23年3月11日発生した東北地方太平洋沖地震の発生により,現行の研究計画で不足していた研究を推進するため「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の見直しについて(建議)」が策定され,平成24年11月28日に科学技術・学術審議会で審議を経て,文部科学大臣をはじめ関係大臣に建議されました.この策定の過程でパブリックコメントの募集を行い,国民の皆様から広く意見を頂戴しました。寄せられました意見の中には,この研究計画と政府の行う地震調査研究についての混同が多く見受けられましたので(回答抜粋),丁寧な説明を試みました. 「地震及び火山噴火研究の将来構想シンポジウム」開催平成24年7月5日~6日に, 東京大学鉄門記念講堂 (本郷キャンパス医学部教育研究棟14階) において「地震及び火山噴火研究の将来構想シンポジウム」を開催します。(詳細は こちら) 平成23年度成果報告シンポジウム開催平成24年3月6日~8日に, 東京大学伊藤国際学術研究センター において「地震及び火山噴火予知のための観測研究」平成23年度成果報告シンポジウムを開催します。(一般向け講演会・ 日程表・ プログラム) 東北地方太平洋沖地震シンポジウムの開催平成23年8月20日に、仙台市において「地震及び火山噴火予知のための観測研究 平成23年東北地方太平洋沖地震に関する成果報告シンポジウム」を開催します。 本シンポジウムは、終了しました。 平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震についての声明文平成23年4月16日
地震・火山噴火予知研究協議会 議長 平原和朗
2011年3月11日14時46分、東北地方の太平洋沖を震源とする超巨大地震(マグニチュード9.0)が発生したことにより、最大震度7に達する強い地震動と高さ15mを超える大津波が東日本の各地に甚大な被害をもたらしました。これにより13,000人以上の方が亡くなられ、今なお14,000人以上の方が行方不明となっています。亡くなられた方々のご冥福を心からお祈りするとともに、被災され不自由な生活を強いられている皆様が一日も早く平常の生活に戻られるようになることを願ってやみません。
我が国では、1965年の「第1次地震予知研究計画」以来、地震予知の研究が組織的に行われてきました。1995年の兵庫県南部地震の発生を契機として、それまでの地震の前兆現象の捕捉に主眼をおいた地震予知の戦略を見直し、観測や実験によって地震現象を科学的に解明し、地震発生モデルの構築を進めるとともに、予測シミュレーションの実現を目指した研究に重点を置くこととしました。この考え方に基づき、1999年に「地震予知のための新たな観測研究計画」をスタートさせました。また、2009年には火山噴火予知計画と統合して「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」を策定し、今日まで本協議会が中心となって、地震・火山噴火に関する観測研究を続けてまいりました。この間の研究の結果、プレート境界地震の発生機構についてはかなり理解が進みました。プレート境界にはアスペリティとよばれる固着域があり、海洋プレートの沈み込みに伴ない、陸側プレートとの境界に力が蓄積されていき、それに耐え切・黷ネくなったときにアスペリティがはがれて地震が起きるという考え方に基づくものです。単独のアスペリティの活動によるマグニチュード8以下の地震については、このモデルが概ね成り立っており、地震の規模や発生時期の大まかな予測が可能になりつつあると考えていました。
しかし、今回の東北地方太平洋沖地震のように、極めて広範囲の断層運動が引き起こす超巨大地震が、日本海溝沿いに発生する可能性を追究するまでには至っておりませんでした。これまでの研究で、複数のアスペリティが連動して発生する大地震が存在し、時として個々のアスペリティが単独で活動して規模がひとまわり小さな地震が発生することもあることを明らかにしてきました。マグニチュード7級の地震を起こすアスペリティが連動破壊して、マグニチュード8級の地震発生に至る過程を再現する数値シミュレーションを基に、南海トラフ沿いや北海道東岸沖における巨大地震の発生の可能性も検討していました。また、宮城県沖ではそう遠くない将来にマグニチード7.5程度の大地震が発生するとの予測をしておりました。東北地方では過去に巨大地震が発生したことを示唆する津波痕跡の報告もありました。しかし、喫緊と思われた宮城県沖でのマグニチード7.5級の地震発生の検討に集中し、今回の超巨大地震発生の可能性については十分に検討するに至っておりませんでした。これが地震予知研究の現状です。
このような事実を真摯に受けとめ、この地震の発生とそれに誘発された地震、火山活動を徹底的に解明し、その情報を社会に発信してゆくことが我々の責務であると思います。東北地方太平洋沖地震発生後は、震源域での余震活動はもちろん、震源域から遠く離れた内陸部でもこの地震に誘発された地震活動が活発化し、火山活動も影響を受けているなど、列島規模での地殻活動の活発化が見られます。過去の事例では、1707年の宝永大地震の49日後に富士山が噴火し、関東平野に多量の火山灰が堆積するなど大きな被害が出ました。また、1896年の明治三陸地震の2ヵ月半後に陸羽地震が発生し、200名以上の方が亡くなりました。同様の事例が他にも多数あります。今、地震研究者に求められていることは、超巨大地震がどのようなメカニズムで起こったのかを解明して、それに基づき今後このような地震の起こる可能性がある地域を明らかにすることであると考えます。さらに、この地震によ・チて誘発された地震活動や火山活動を注意深く調査観測し、これらの誘発事象を正しく理解することであると思います。観測研究、基礎研究、開発研究の分野で地震・火山噴火予知研究をおこなってきた研究者は、互いに協力して総力を結集し、この地震の発生機構の解明と、今後の地震・火山活動の推移の予測を目指した研究を推進し、これらを今後の地震防災に役立てたいと思います。それがこの地震と津波で犠牲となられた方々、被災された方々に対する我々の責務であると深く胸に刻んでまいりたいと思います。
以上
地震・火山噴火予知研究協議会について日本は世界有数の地震・火山国で、これまで多くの地震災害や火山災害に見舞われてきました。これらの災害から人命や財産を守り、安全で安心な社会を実現することは、日本国民ばかりでなく人類の共通の要望です。地震災害や火山災害の軽減のために、地震や火山噴火現象を解明してその予測を実現するために、全国の大学・研究機関の研究者は、地震予知研究と火山噴火予知研究を行ってきました。 平成21年度から、これまでそれぞれ独立に行われてきた地震予知研究計画と火山噴火予知計画が統合され、「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」が5ヶ年計画でスタートしました。地震と火山噴火は、一方が地下の岩石の脆性的な破壊現象であるのに対して、もう一方はマグマの上昇と噴出と言う本質的に異なる現象ですが、共に岩石の変形や破壊などが大きく関与する現象です。 また日本列島周辺では、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込むことにより、プレート境界や内陸で地震が発生し、また日本列島の地下の上部マントルではマグマが生成され火山活動に至るなど、地震と火山噴火は地球科学という共通のバックグラウンドを持っています。そのため、観測項目や解析手法の一部が共通であると同時に、長い発生間隔に適した長期の観測データを効率的に蓄積するデータベースが重要であるなど、両研究計画を統合して実施する利点が多くあります。相互の研究分野の長所を取り入れて研究の幅を広げることにより、地震及び火山噴火予知研究の両方を一層発展させることを目指して、両研究計画の統合が行われました。 この統合に対応して、これまで別々であった地震予知研究協議会と火山噴火予知研究協議会を平成18年5月に統合し、地震・火山噴火予知研究協議会が発足しました。この協議会は、地震及び火山噴火予知研究を行っている全国の大学・研究機関の連携と協力関係を強化し、「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」(科学技術・学術審議会測平成20年7月17日建議:以下「予知研究」)で立案された研究を推進することを目的に設立されました。 この建議に基づく予知研究全体を円滑に実施するため、地震・火山噴火予知協議会の下に研究計画の企画、立案、調整を行う企画部が設けられています。現在は、東京大学地震研究所の教員6名(内1名は予知研究流動的定員)のほかに、他大学所属の2名の客員教員が参加し、8名で構成されています。 更に、全国の大学の研究者が独自の発想で実施する個別研究を、建議に書かれた項目に区分し、項目毎に効率的かつ調和的に予知研究を推進するために、計画推進部会が設置されています。現在、12の計画推進部会が設置されています。 ※日本地震学会広報誌「なゐふる」に、地震・火山噴火予知研究計画についてのより詳細な説明が掲載されています。 (「なゐふる」73号) |