ウェブサイト立ち上げ:2025年7月30日
最終更新日:2025年8月1日
2025年7月30日08:25頃にカムチャッカ半島付近で起き、現在も津波警報が気象庁より発出されています。(7月30日15:30時点)
この地震について、こちらで情報を随時更新してまいります。
*報道関係の皆さまへ:図・動画等を使用される際は、「東京大学地震研究所」と、クレジットを表示した上でご使用ください。また、問い合わせフォームより使用した旨ご連絡ください。
掲載日:2025/08/01
カムチャツカ半島沖地震:津波シミュレーションとDART観測データの比較
(災害科学系研究部門:染矢 真好 大学院学生(D1)、古村孝志 教授
地球計測系研究部門:三反畑 修 助教、綿田 辰吾 教授)
概要
- 2025年7月30日に発生したカムチャツカ半島沖地震について、USGSの断層モデルを用いて津波シミュレーションを行った。
- 日本沿岸では、震源からの直接波に続き、天皇海山列で散乱された波が遅れて到達する様子が確認された。これらは津波警報などの解除に影響を及ぼす可能性がある。
- シミュレーション結果とDARTの観測データを比較すると、遠地津波の到達時刻が理論値より遅れる現象が見られた。こうした遅れは、海底の弾性変形などの効果をシミュレーションに取り入れることで説明可能であることを確認した。
2025年7月30日、日本時間8時25分ごろにカムチャツカ半島沖で発生した地震について、津波が太平洋を横断する過程を数値シミュレーションにより再現し、実際の観測データと比較を行った。以下に震源とDARTの海底津波計の位置を示す。
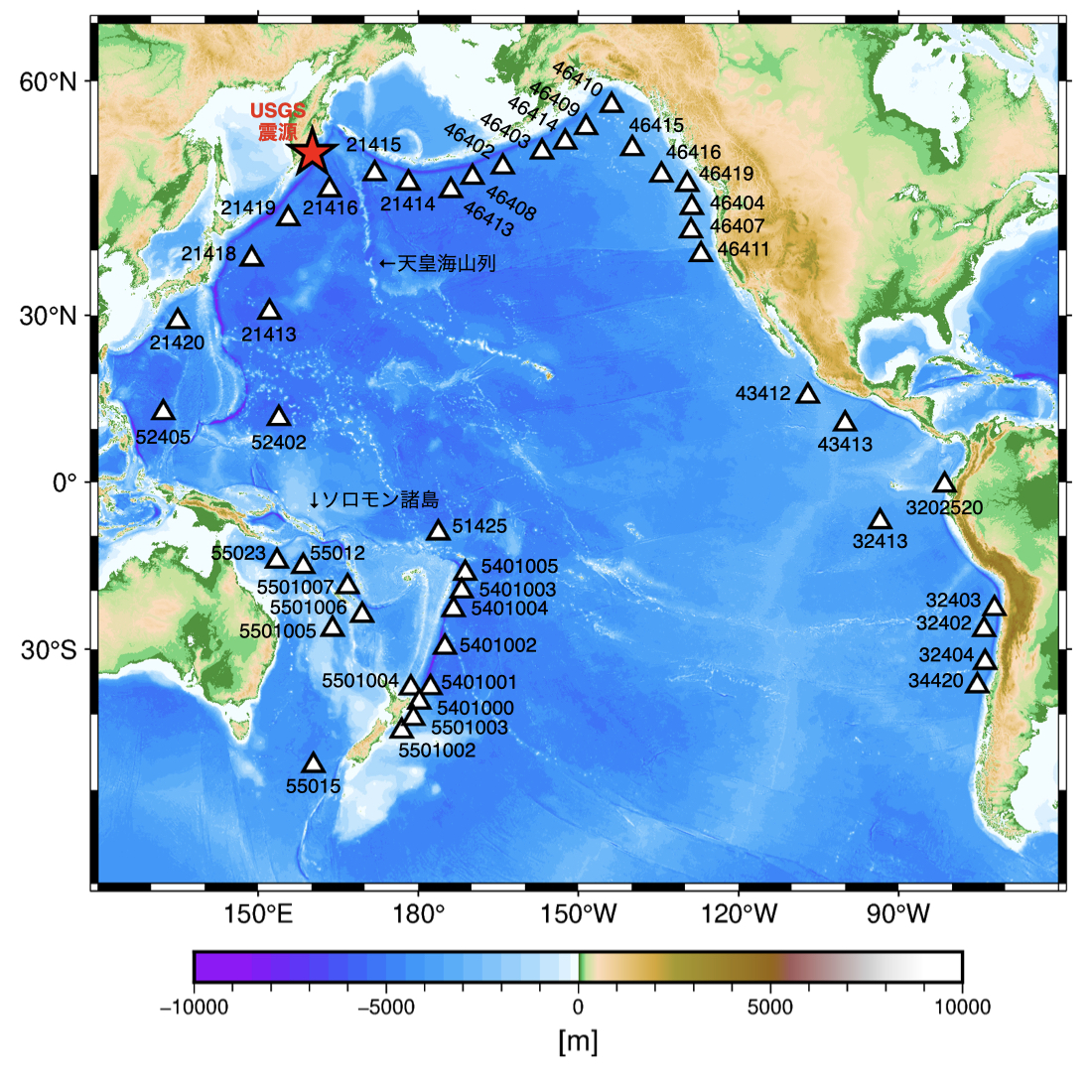
まず、アメリカ地質調査所(USGS)が遠地地震波から推定した有限断層モデル(https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw60/finite-fault 現時点はVer. 3が公開されているが、計算にはVer.2を用いた)を用い、Okada (1985) に基づき海底の鉛直変位を計算した。この変位を初期条件として、津波シミュレーションライブラリJAGURS(Baba et al, 2015)を用いて津波の伝播を線形長波方程式を用いて評価した。時間刻み幅は1秒とし、地震発生から24時間後までの津波の伝播を計算した。断層破壊の進行や立ち上がり時間を考慮せず、瞬時に海面変動が発生すると仮定した。
使用した水深データは、GEBCO 2024の15秒角グリッドを60秒角に間引いたもので、ネスティングは行わず単一のグリッド系を用いた。シミュレーションは東大情報基盤センターのスパコンシステムWisteria-aにおいて、MPI(4ノード・16プロセス)とOpenMP(18スレッド)によるハイブリッド並列計算により実施し、計算時間は約50分であった。
以下に示すアニメーションは、太平洋を横断する津波のシミュレーション結果であり、黒三角はDART観測点を表している。なお、t=1,000分以降に北米大陸西岸で確認できる大振幅の波は、実際の津波ではなく、シミュレーションの不安定性に起因する人工的なものである。 日本沿岸では、震源から直接到達する津波に加え、天皇海山列で散乱された波が遅れて到達する様子が確認できる。また、ソロモン諸島付近で反射した波が北方へ戻る様子も確認できる。このように遅れて到達する波は、津波警報などの解除に影響を及ぼす可能性がある。
続いて、各地点での最大波高を可視化した図を以下に示す。津波の伝播には明瞭な指向性があり、全方位に等しく伝播するのではなく、特に震源断層に対して垂直方向(南東方向)に大振幅の津波が広がる様子が分かる。
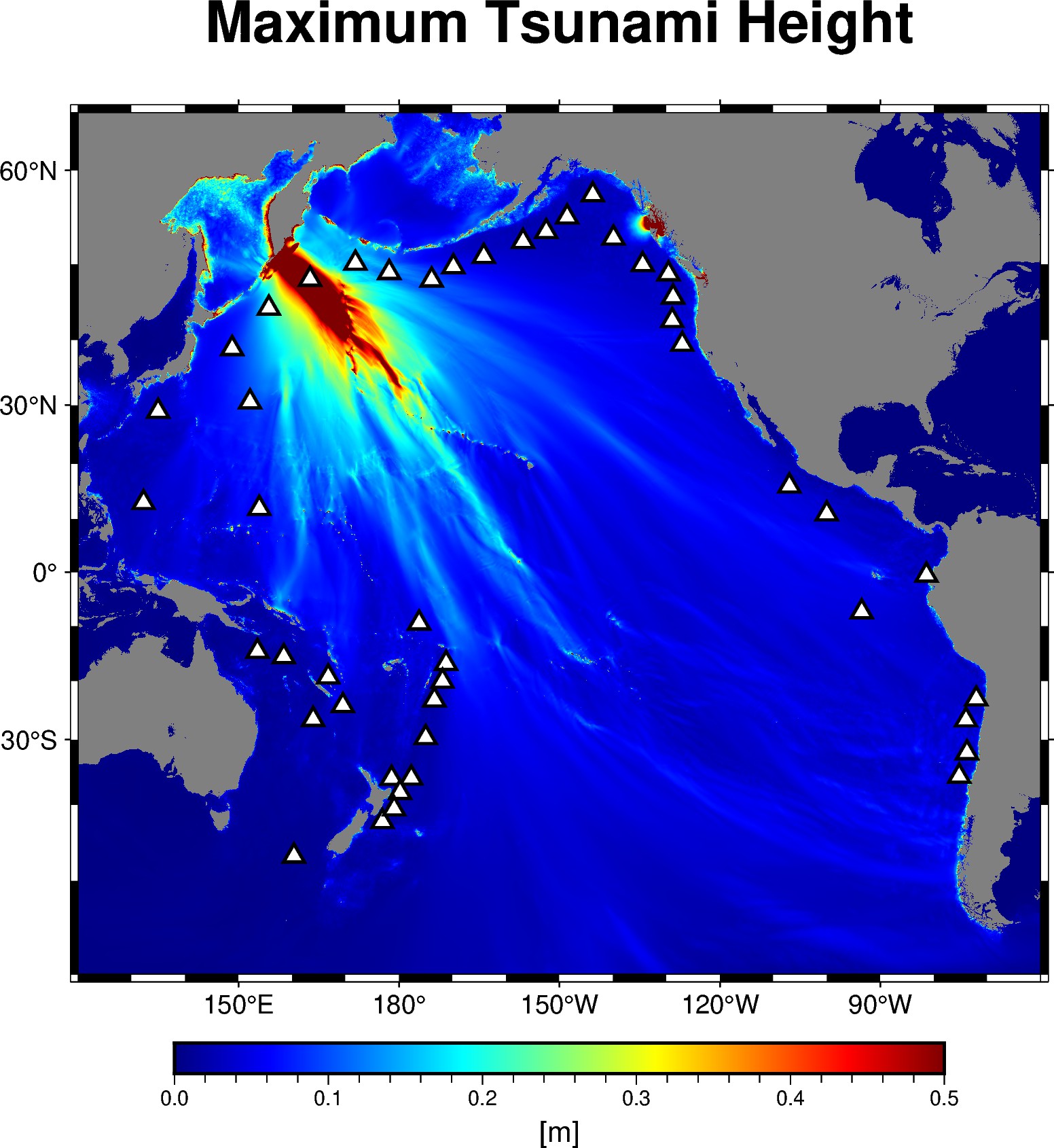
最後に、DARTでの観測波形とシミュレーション結果を比較した。DARTデータはUNESCO/IOCのウェブサイト(https://www.ioc-sealevelmonitoring.org/ )から取得し、次数15の多項式で潮汐成分を近似・除去したものを表示している。なお、観測・計算ともにフィルタリング処理は施していない。
DARTシステムは2004年のスマトラ島沖地震を契機に整備され、2010年のチリ地震や2011年の東北地方太平洋沖地震では、津波が太平洋を横断する様子を明瞭に観測した。これらのイベントでは、震源から数千km離れた観測点で津波の到達が理論値よりも数十分遅れることが報告されている。その後の研究で、従来の津波評価では無視されていた海底の弾性変形、海水の密度成層などの副次的効果を考慮することで、到達の遅れを説明できることがわかった(Watada et al. 2014など)。これらの効果を反映したシミュレーション手法はAllgeyer & Cummins(2014)によって開発され、JAGURSにも実装されている。 今回の津波においても、DART観測波形(黒)と線形長波方程式に基づくシミュレーション結果(副次効果を含まない、赤)を比較すると、遠距離観測点において計算波形が先行する傾向が確認された。

一方、副次効果を考慮したAllgeyer & Cumminsの手法を用いることで、到達時刻の予測精度は向上し、観測波形との時間的なズレは軽減された。
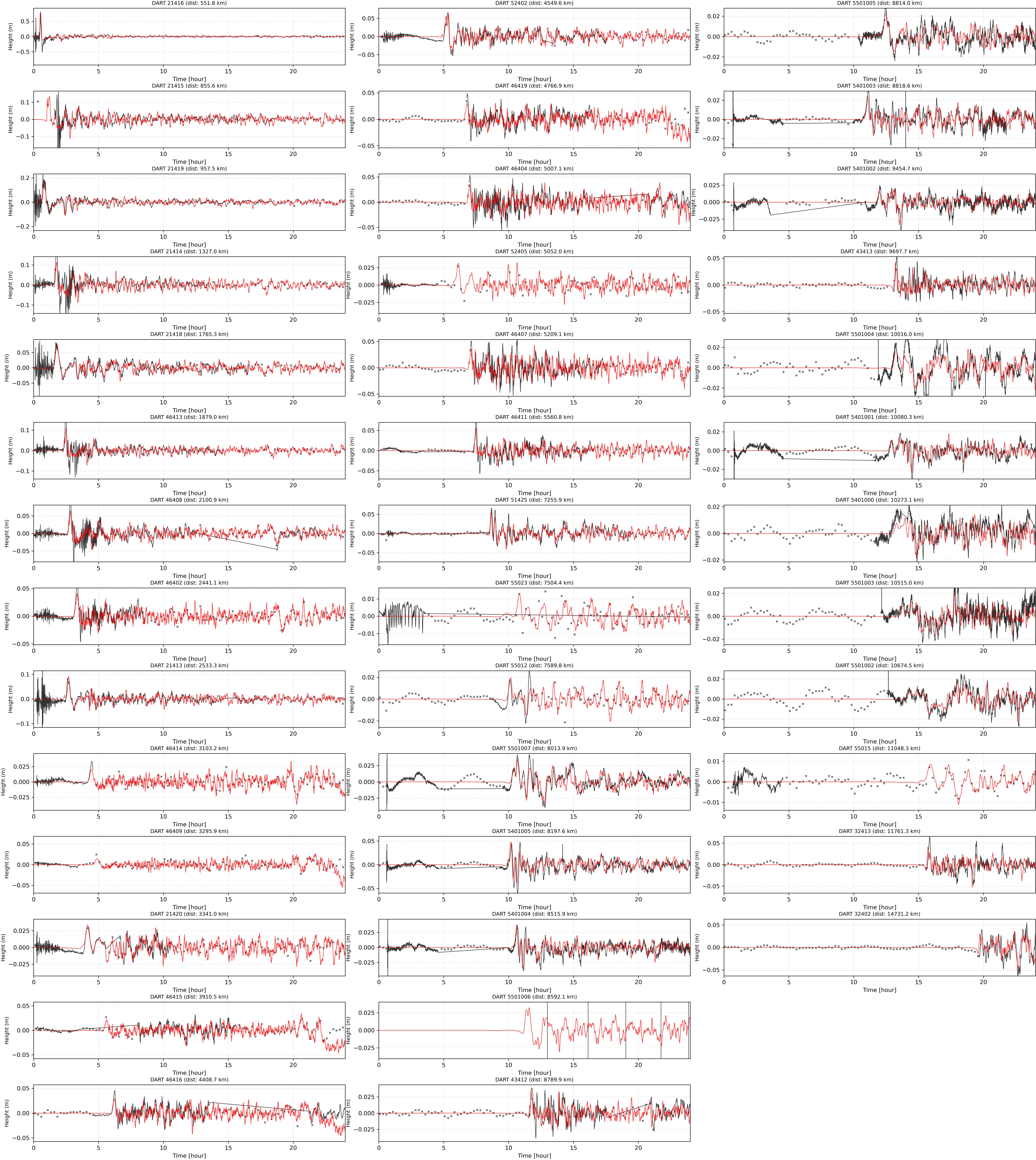
それでもなお、いくつかの観測点では位相の差異が残っており、これは今回のシミュレーションでUSGSの最新版断層モデル(Ver.3)ではなくVer.2を使用したこと、および断層破壊の進行や立ち上がり時間を考慮していないことが要因と考えられる。今後、これらの効果を取り入れたシミュレーションを行うことで、さらなる精度向上が期待される。
参考文献:
- Okada, Y. (1985). Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space, Bull. Seism. Soc. Am., 75, 1435-1154. doi:10.1785/BSSA0750041135
- Baba, T., Takahashi, N., Kaneda, Y., Ando, K., Matsuoka, D., & Kato, T. (2015). Parallel implementation of dispersive tsunami wave modeling with a nesting algorithm for the 2011 Tohoku tsunami. Pure and Applied Geophysics, 172(12), 3455-3472. doi:10.1007/s00024-015-1049-2
- Watada, S., Kusumoto, S., & Satake, K. (2014). Traveltime delay and initial phase reversal of distant tsunamis coupled with the self‐gravitating elastic Earth. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 119(5), 4287-4310. doi:10.1002/2013JB010841
- Allgeyer, S., & Cummins, P. (2014). Numerical tsunami simulation including elastic loading and seawater density stratification. Geophysical Research Letters, 41(7), 2368-2375. doi:10.1002/2014GL059348
掲載日:2025/07/30
W-phase解析結果 (モーメントテンソル解)
世界中で観測された,この地震による地震波の記録からW-phase(P波とS波との間にある,超長周期の実体波)を取り出し,Kanamori and Rivera (2008)の方法で解析した モーメントテンソルインバージョンによるメカニズム解になります.モーメントマグニチュードは,8.86と求まっています.
(日本列島モニタリング研究センター:鶴岡 弘 准教授)


参考文献:
Kanamori, H. and L. Rivera (2008): Source Inversion of W phases: speeding up seismic tsunami warning, Geophys. J. Int., 175, 222-238.

