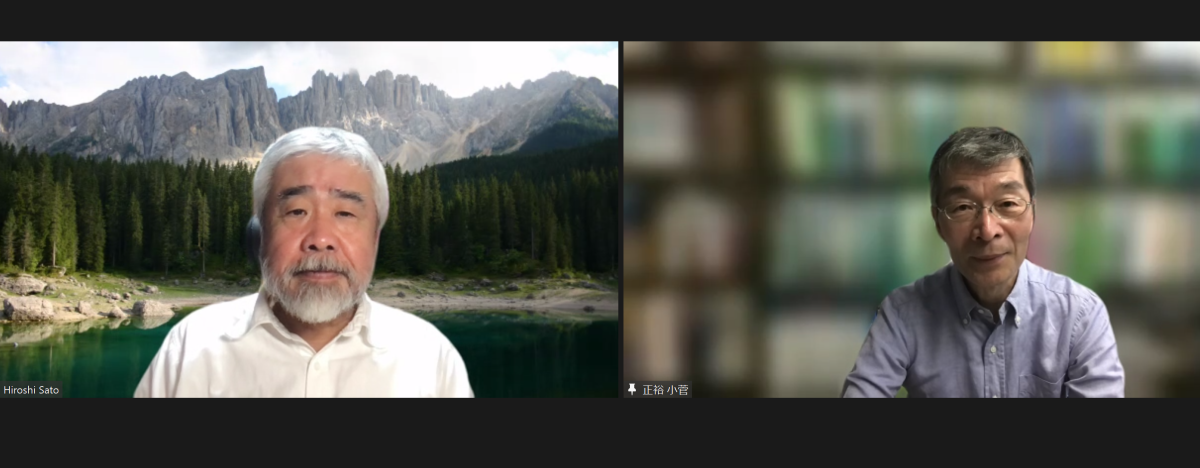下記のとおり地震研究所談話会を開催いたします。
ご登録いただいたアドレスへ、開催当日午前中にURL・PWDをお送りいたします。
なお、お知らせするzoomURLの二次配布はご遠慮ください。また、著作権の問題が
ありますので、配信される映像・音声の録画、録音を固く禁じます。
記
日 時: 令和5年6月16日(金) 午後1時30分~
開催方法: インターネット WEB会議
1. 13:30-13:45
演題:実際的な3次元電気伝導度構造モデルに対するMT応答関数順計算の不確定性評価について
著者:○馬場聖至
要旨:実際的な3次元電気伝導度構造に対するMT応答関数の順計算に含まれる不確定性を、水平座標軸の選択による偶然誤差の観点から評価する手法を提案する。
2. 13:45-14:00
演題:On the Development of Shear Surface Roughness
著者:○Manaska MUKHOPADHYAY、 Uddalak BISWAS(Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur)、Nibir MANDAL (Jadavpur University, Kolkata)、Santanu MISRA (Indian Institute of Technlogy, Kanpur)
要旨:We investigated a unique type of slickenside, studied the shear surface roughness from field as well as laboratory experiments using fractal dimensional analysis and proposed a possible mechanism for its formation using basic numerical simulations.
3. 14:00-14:15
演題:地震火山史料の整理と収集による近世日本の地震活動の把握 【所長裁量経費成果報告】
著者:○加納靖之・鶴岡 弘・前野 深・大邑潤三、榎原雅治・杉森玲子(史料編纂所)
○発表者
※時間は質問時間を含みます。
※既に継続参加をお申し出いただいている方は、当日zoomURLを自動送信いたします。
※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。
〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1
東京大学地震研究所 共同利用担当
E-mail:k-kyodoriyo(at)eri.u-tokyo.ac.jp
※次回の談話会は令和5年7月28日(金) 午後1時30分~です。