講演会開催のお知らせ
令和4年10月15日(土)は本学のホームカミングデイに当たります。当日は、本郷キャンパス及び駒場キャンパスにおいて様々なイベントが開催されます。
地震研究所では、以下講演会を開催いたしますので、参加を希望される方は、申込フォームよりお申し込みをお願いいたします。
記
【講演会】 光ファイバセンシング技術が拓く新しい海底地震観測 / 篠原 雅尚 教授
従来情報通信などに使用されている光ファイバ自身を、多数のセンサ群として振動を計測する光ファイバセンシング技術が、近年発展しています。この技術を光海底ケーブルに応用することで、少ない海底地震観測点を飛躍的にふやすことができます。三陸沖の光海底ケーブルに適用し、微小地震や深発地震の海底観測を行った例を紹介します。
【日時】令和4年10月15日(土)13時30分~14時30分
【場所】地震研究所1号館2階セミナー室
【対象】一般(定員50名:申し込み順) ※要事前申込
【申込方法】
申込フォームよりお申込みください。
※申込受付期間:令和4年9月26日(月)9時 ~ 10月13日(木)17時
【注意事項】
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、定員は50名(申し込み順)、とさせていただきます。申し込み状況により、お断りする場合がございますので、予めご了承願います。
・入構する際は、原則としてマスクを着用し、感染リスクの高まる行動は慎んでください。
・日頃から健康管理を行い、発熱等の体調不良がある場合は入構を控えてください。
・申込フォームに入力いただいた個人情報につきましては、本講演会実施の目的のみに使用いたします。法令などにより開示を求められた場合を除き、個人情報をご本人の同意を得ることなく業務に関与する者以外の第三者に開示することはありません。
【本件問合せ先】
地震研究所庶務チーム(庶務担当) 03(5841)5666
shomu[at]eri.u-tokyo.ac.jp ※[at]は@に置き換えてください


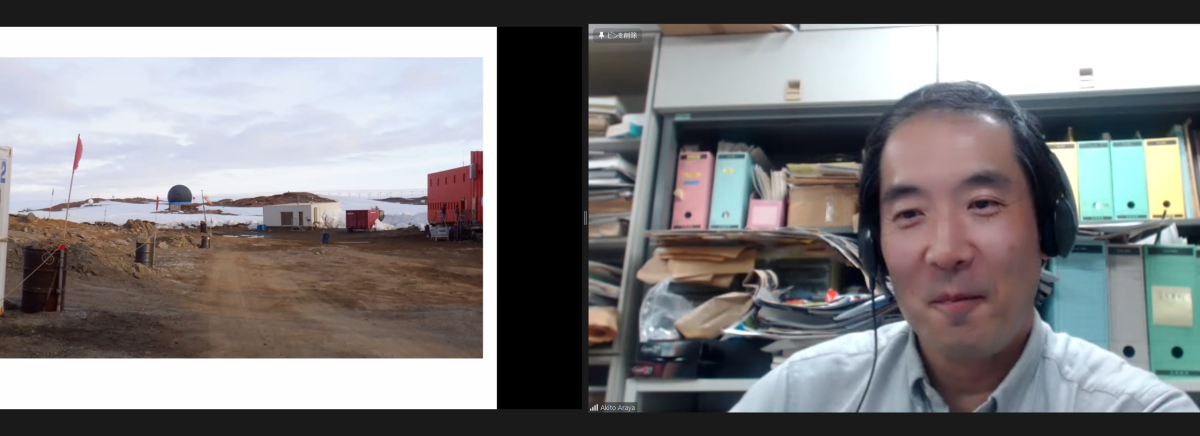
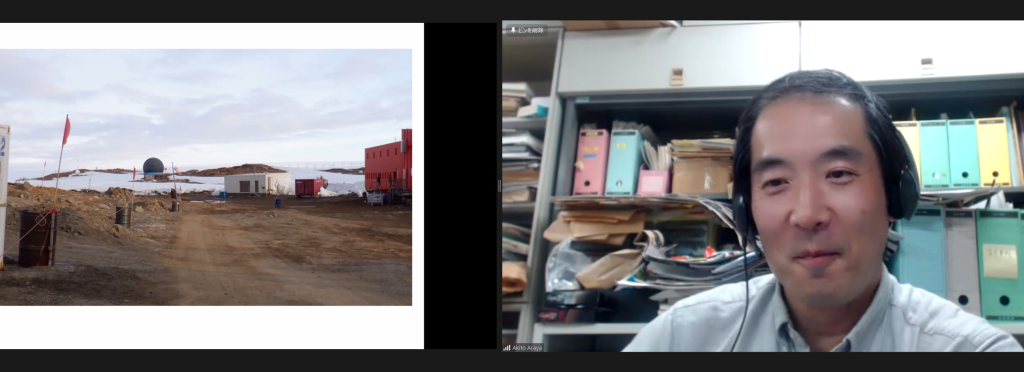
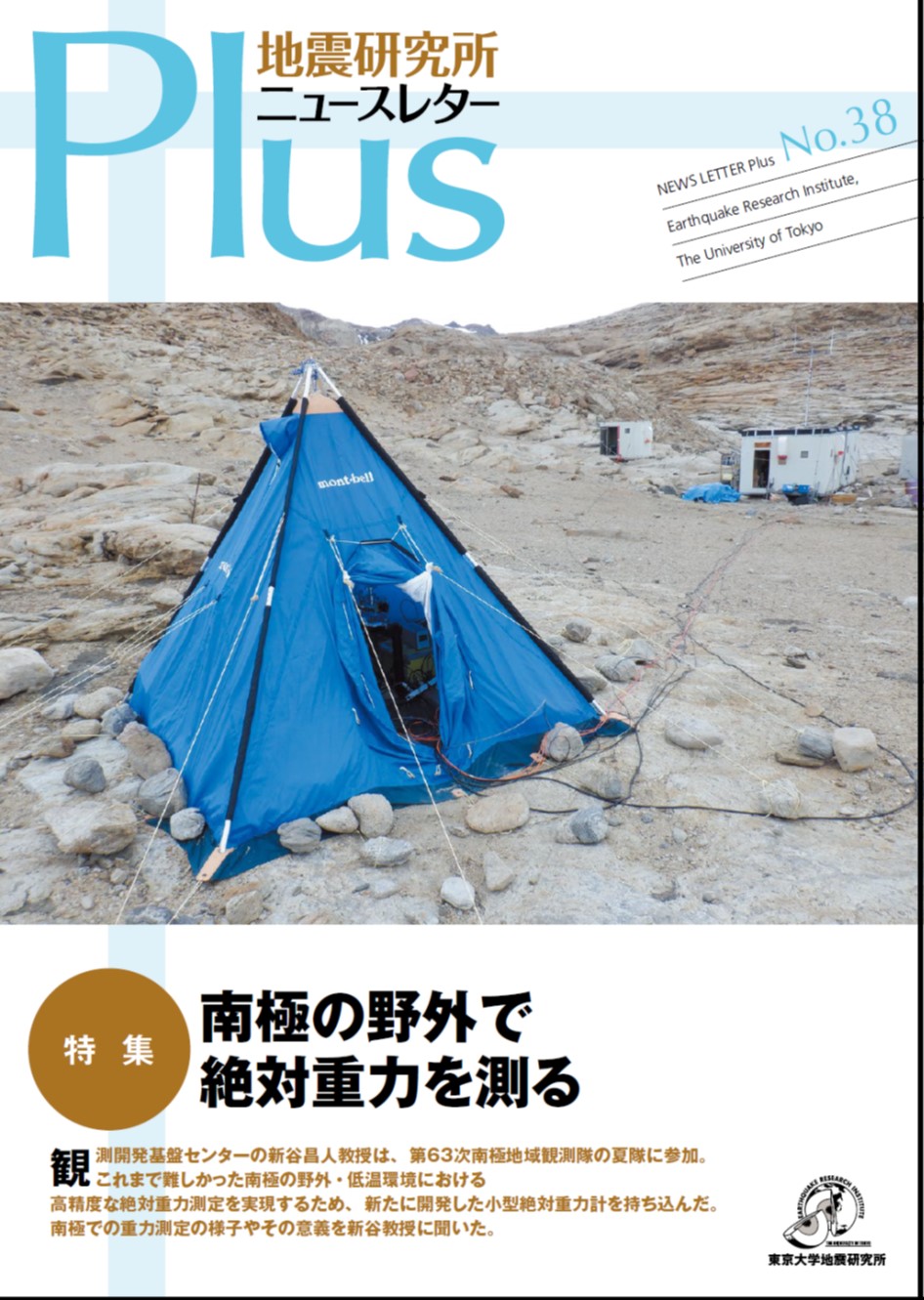
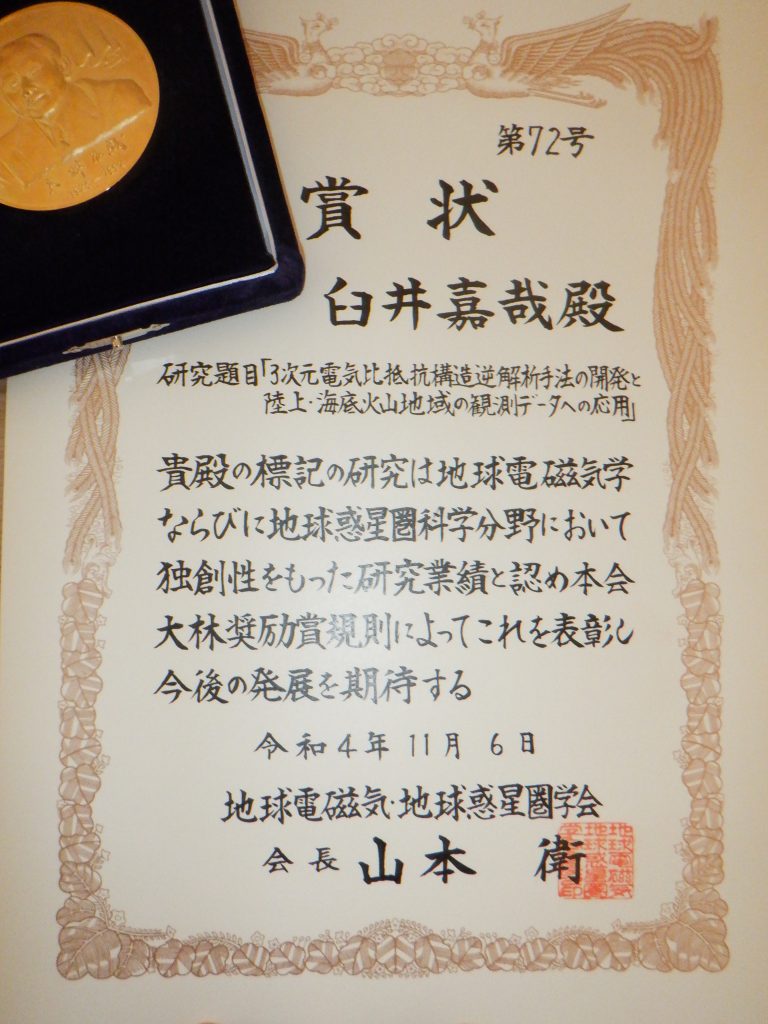
jpg.jpg)