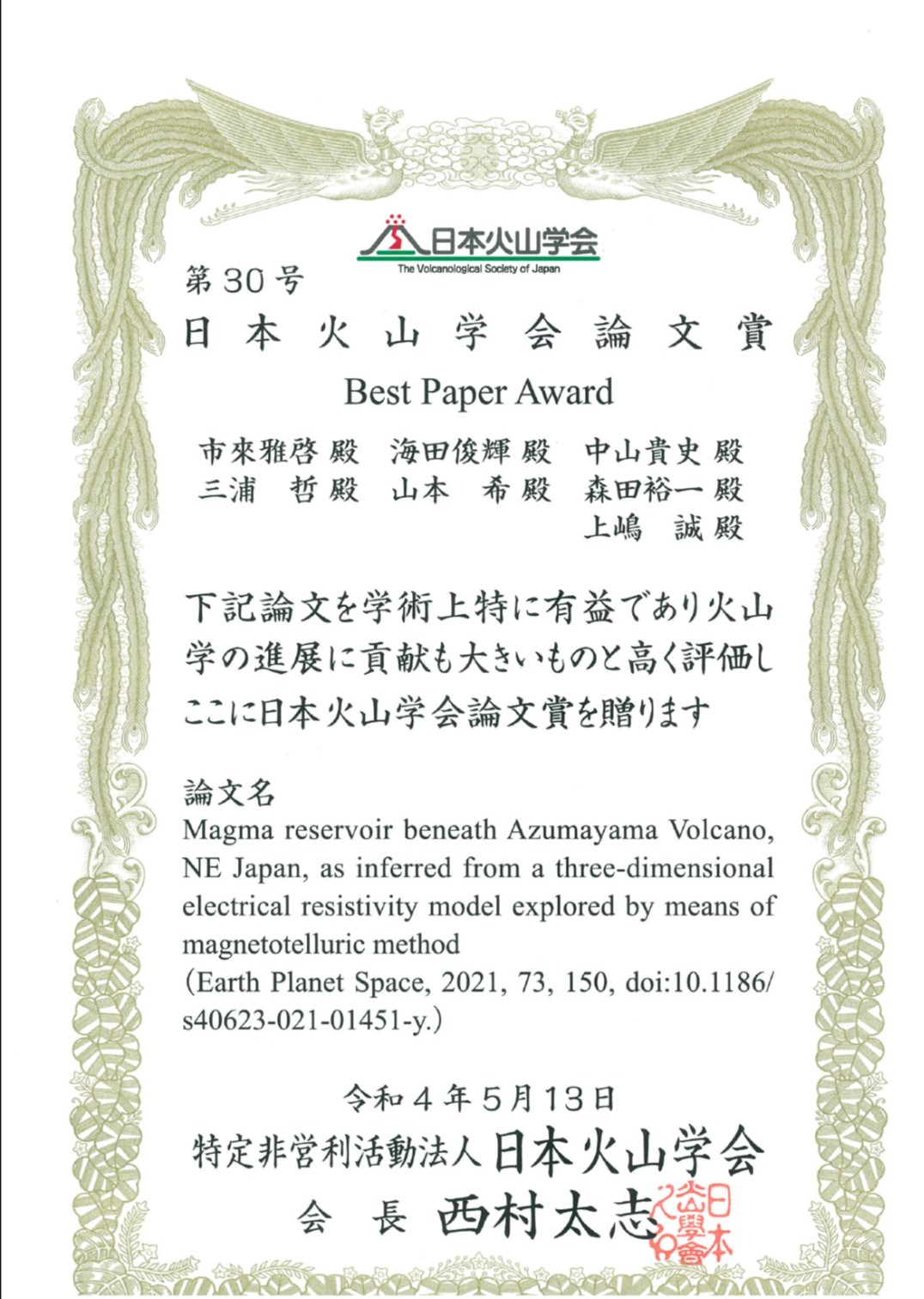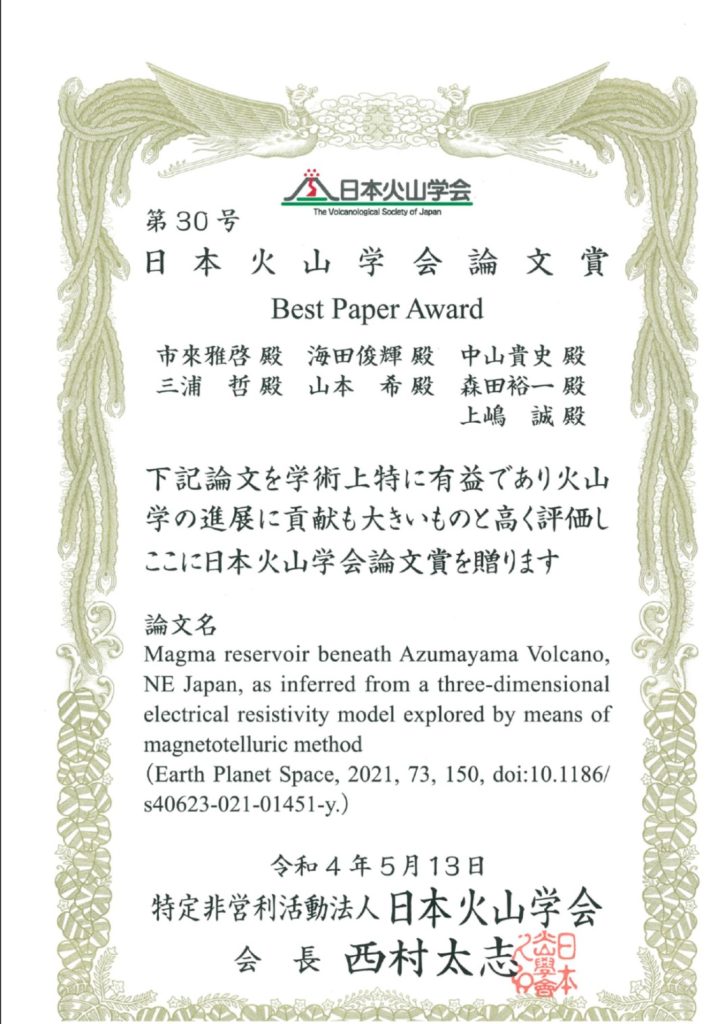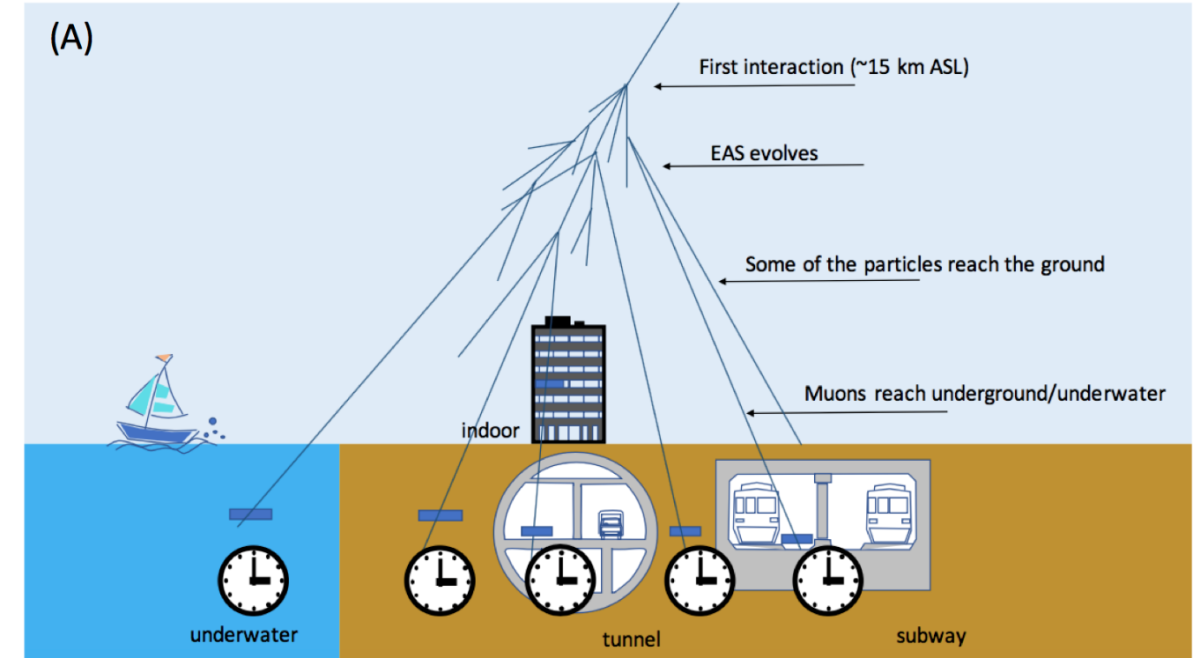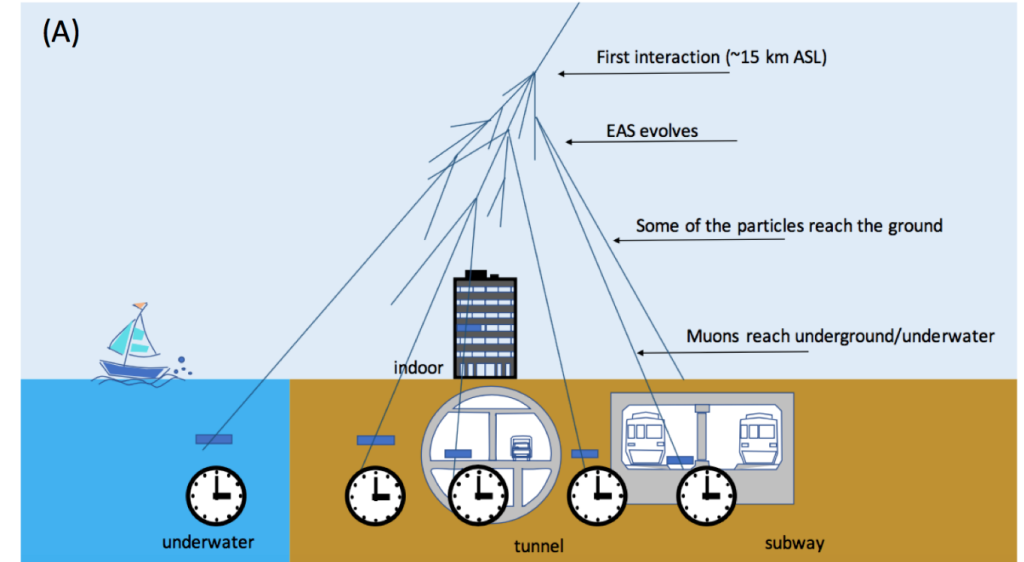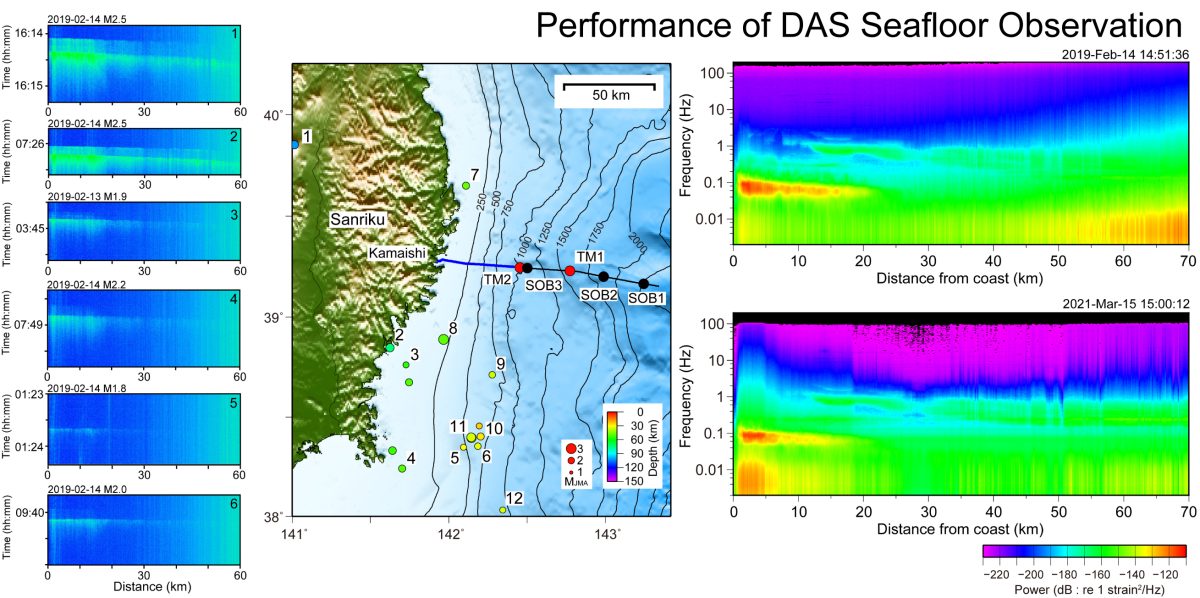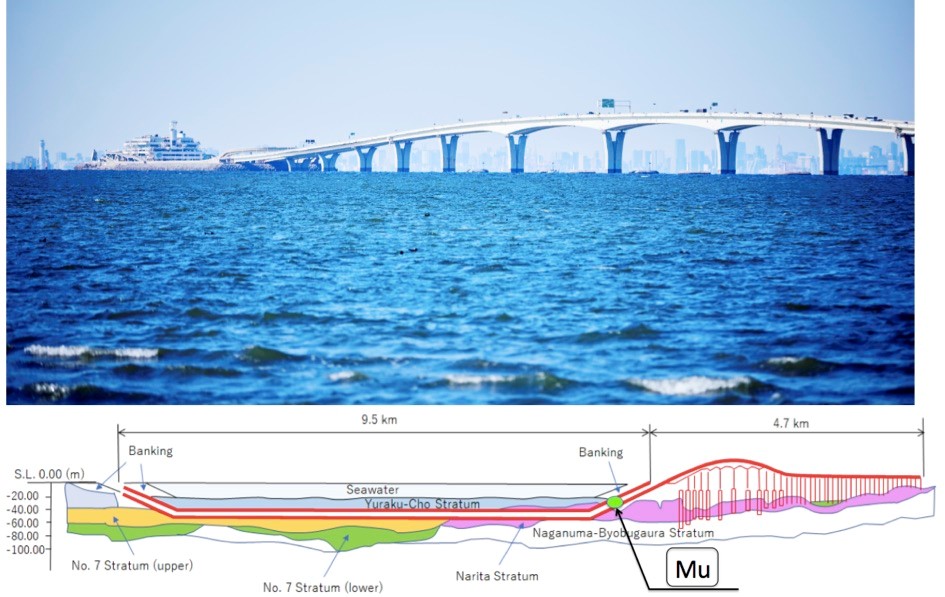下記のとおり地震研究所談話会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。今回は、コロナウィルス感染対策として、地震研究所の会場での開催は行いません。WEB会議システムを利用した参加のみとなります。参加に必要な設定URL・PWDについては、参加をご希望される方宛に別途ご連絡をいたしますので、共同利用担当宛(k-kyodoriyo(@)eri.u-tokyo.ac.jp)お問い合わせください。
なお、お知らせする設定URLの二次配布はご遠慮ください。また、著作権の問題がありますので、配信される映像、音声の録画、録音を固く禁じます。
記
日 時 令和4年5月20日(金)午後1時30分~ インターネット WEB会議
- 13:30-13:45
演題:Two-layered oceanic lithosphere beneath the Japan Basin, the Sea of Japan
著者:○Sanxi AI・Takeshi AKUHARA・Manabu MORISHIGE、Kazunori YOSHIZAWA(Hokkaido University)、Masanao SHINOHARA and Kazuo NAKAHIGASHI(Tokyo University of Marine Science and Technology) - 13:45-14:00
演題:Temperature-dependence of rate- and state-dependent friction with competing healing mechanisms【所長紹介(受入教員:福田淳一)】
著者:○Sylvain Barbot (University of Southern California)
要旨:We discuss how competing healing mechanisms at contact junction may affect the evolution of effective frictional properties with varying temperature. - 14:00-14:15
演題:Pn方位異方性により制約される海洋リソスフェアのオリビン選択配向様式【所長裁量経費成果報告】
著者:○竹内 希・一瀬建日・川勝 均・塩原 肇、杉岡裕子(神戸大学)、歌田久司
○発表者
※時間は質問時間を含みます。
※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。
〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1
東京大学地震研究所研究支援チーム
E-mail:k-kyodoriyo(@)eri.u-tokyo.ac.jp
※次回の談話会は令和4年6月17日(金)午後1時30分~です。