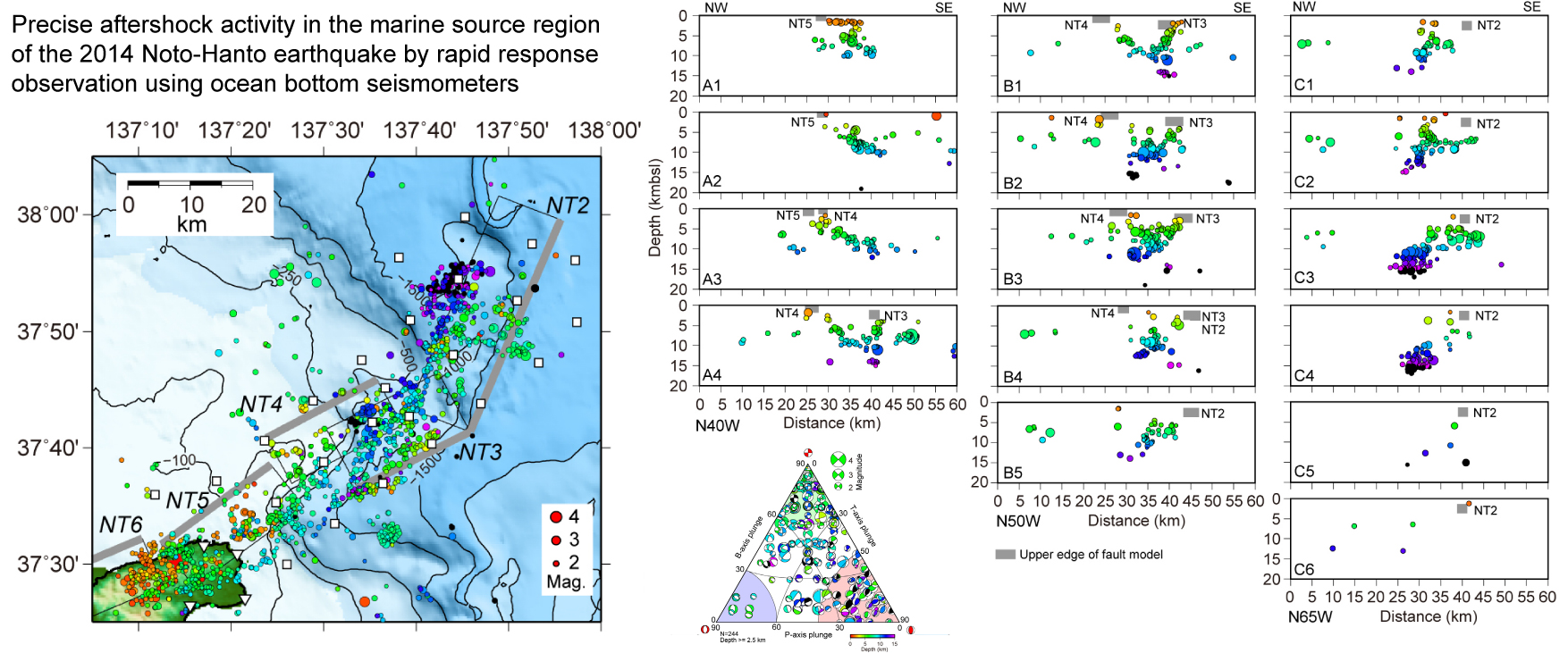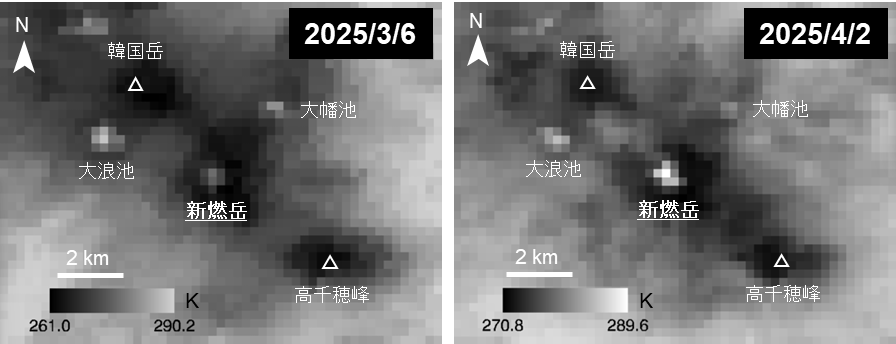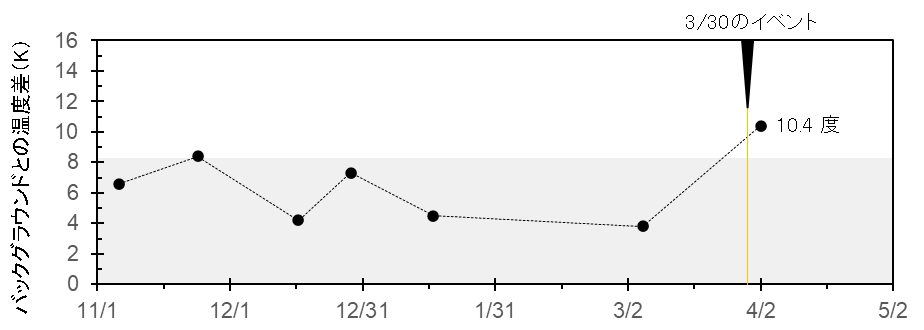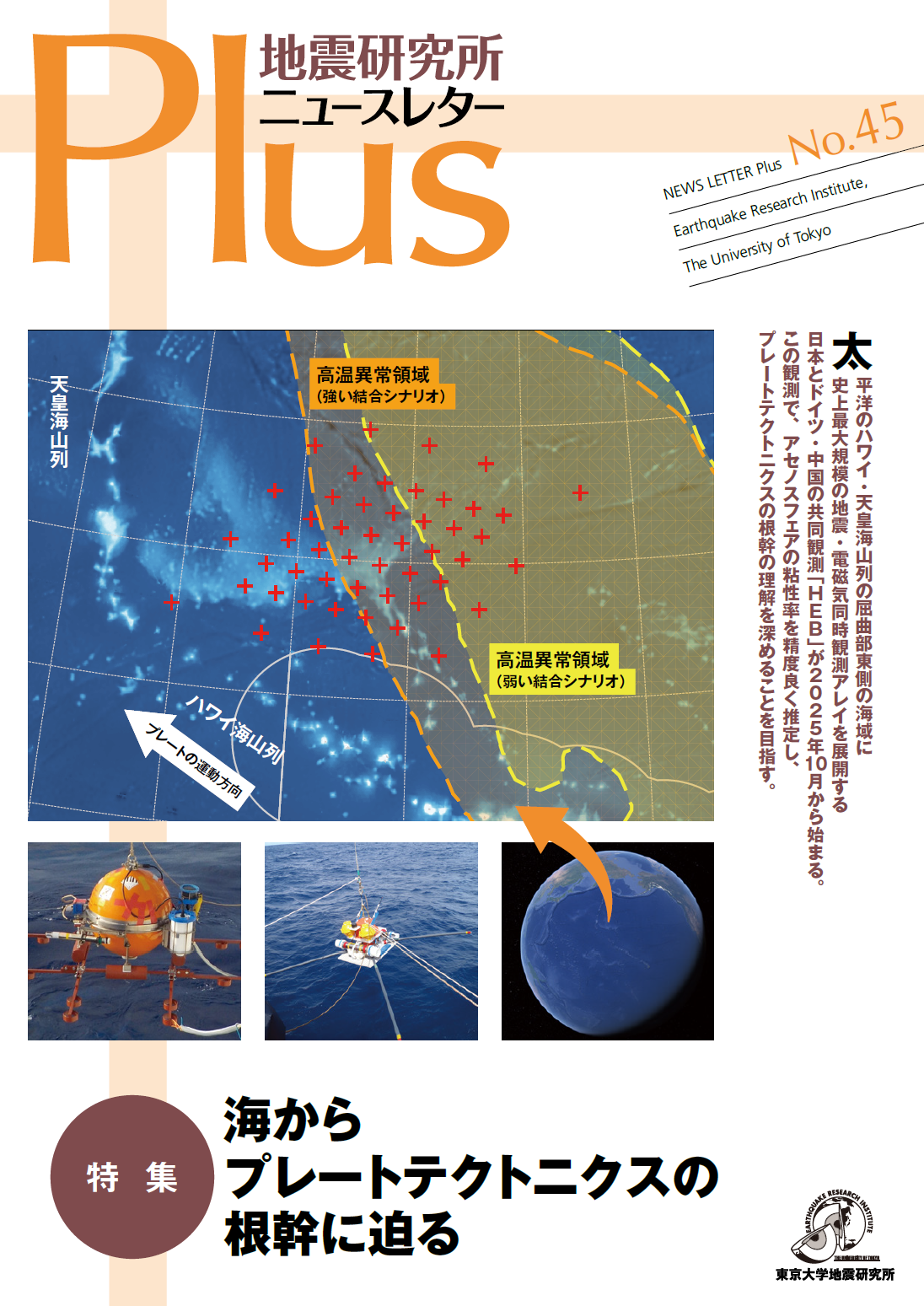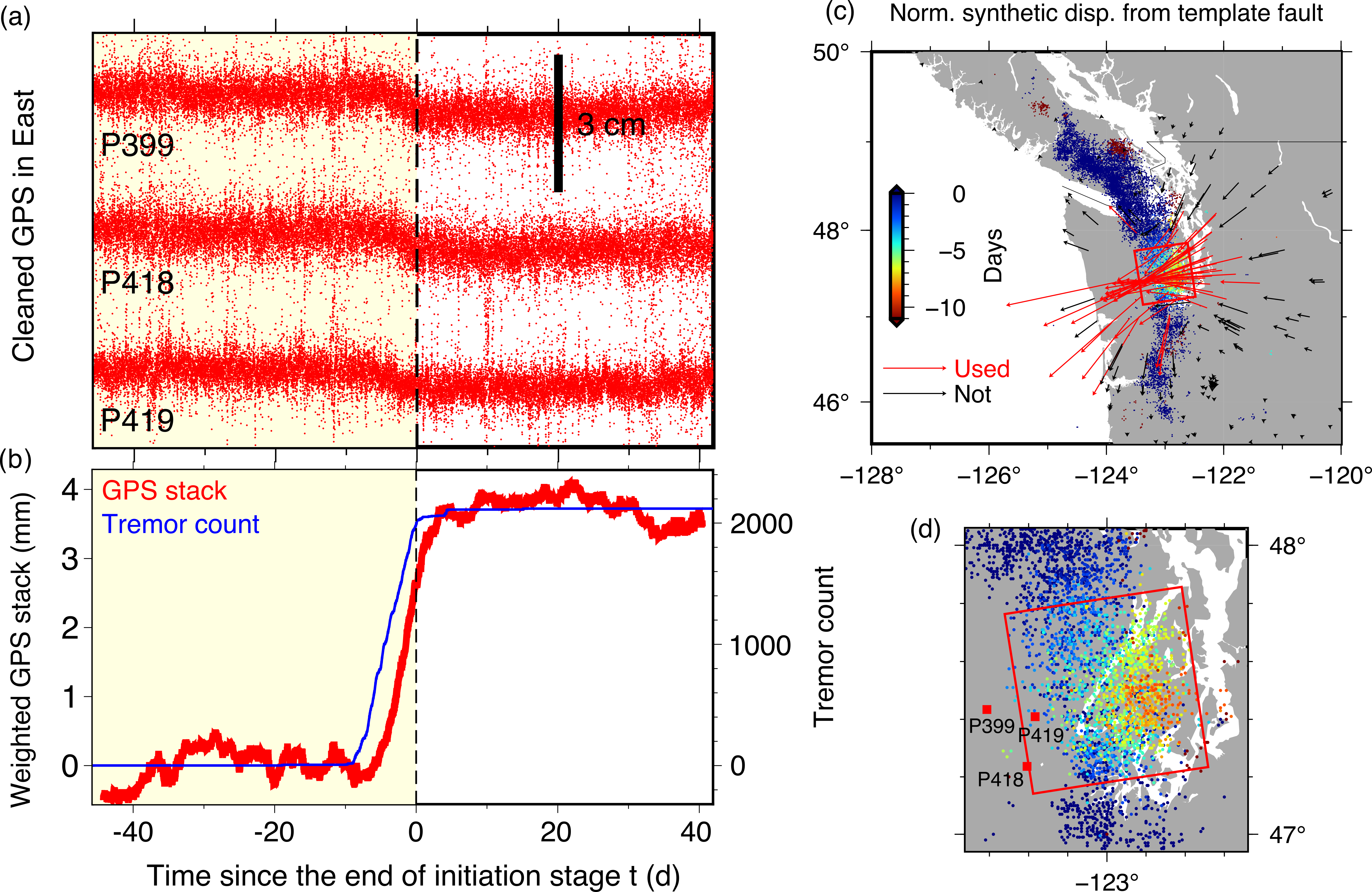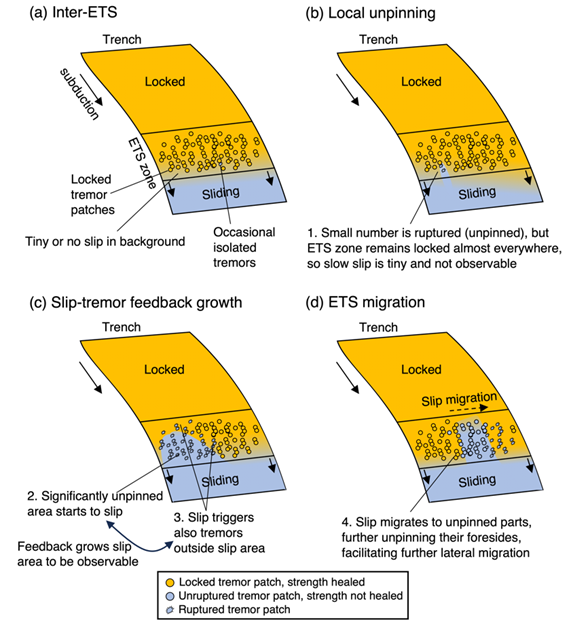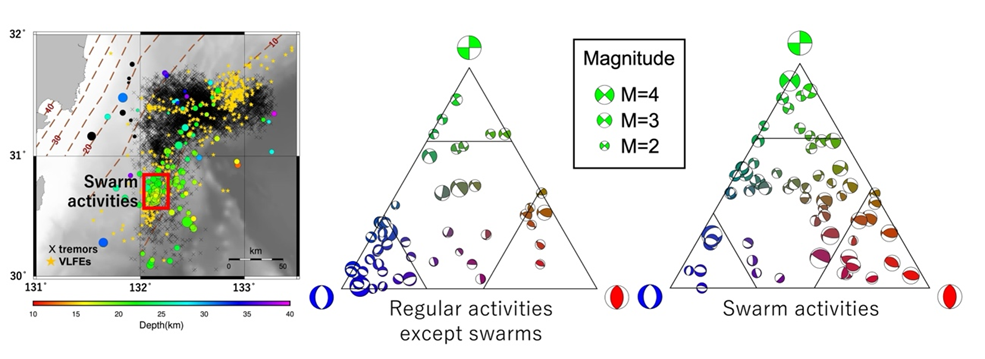矢野萌生(千葉工業大学)、安川和孝、中村謙太郎、黒田潤一郎、岩森光(東京大学)、池原実(高知大学)、加藤泰浩(東京大学/千葉工業大学)の研究チームは、現世の海洋とは全く異なる「酸素に乏しい海」(貧酸素/無酸素海洋) で生成したさまざまなレアメタル元素を含む堆積岩 (黒色頁岩) の化学組成データを統計的に解析し、貧酸素/無酸素海洋においてレアメタル濃集を引き起こした要素を分離・抽出することに成功しました。さらに、これらを新たな指標として、酸素に乏しい海洋がどのような環境であったかの推定に利用できることを示しました。
本研究の成果は、酸化的な海洋で生成するレアアース泥やマンガンノジュールとは全くタイプの異なる、酸素に乏しい海洋で生成したレアメタル資源の探査にも活用できると期待されます。これまで貧酸素/無酸素海洋で形成した堆積物の化学組成については、対象とする個々の時代や元素に注目した研究がなされていましたが、それらが互いにどう異なるのかや、堆積時の海洋環境と堆積物への元素濃集および海底レアメタル資源の生成との関係は明らかになっていませんでした。今回研究チームは、ペルム紀/トリアス紀境界、白亜紀海洋無酸素事変、現世という 3 つの異なる時代に形成した堆積物・堆積岩に対して多変量解析手法の 1 つである独立成分分析 (注 1; 図 1) を適用し、酸素に乏しい環境下での異なる元素濃集パターンを示す 4 つの成分を抽出することに成功しました。そして、抽出された成分の特徴の詳細な解析から、時代や海域ごとの黒色頁岩の化学組成の普遍性と特異性を初めて明らかにしました。この成果は、海洋の酸素が乏しい時代に形成された黒色頁岩における元素濃集のメカニズムの解明、さらにそれを生じさせた地球環境変動の解明に貢献する、重要な知見といえます。
この研究成果は、2025 年 4 月 7 日にアメリカ地球物理学連合 (American Geophysical Union)
の学会誌「Paleoceanography and Paleoclimatology」で発表されました。
キーワード:貧酸素海洋、独立成分分析、化学組成データ、ペルム紀/トリアス紀境界、白亜
紀海洋無酸素事変、黒色頁岩、レアメタル資源
これにつきまして千葉工業大学よりプレスリリースがされました。
詳細につきましてはこちらをご覧ください:https://chibatech.jp/news/20250408.html(千葉工業大学HP)