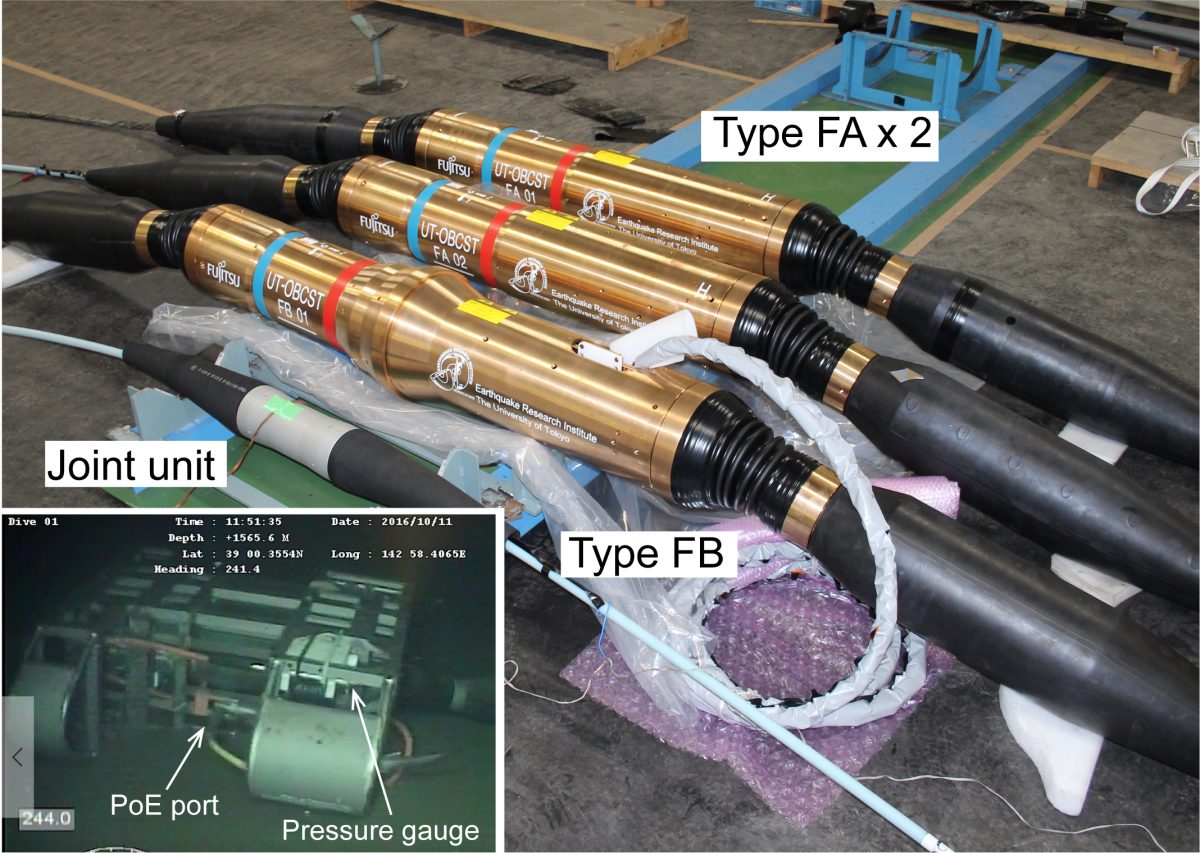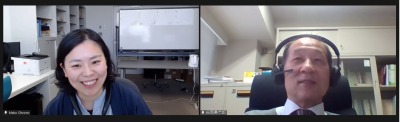下記のとおり地震研究所談話会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。
今回は、コロナウィルス感染対策として、地震研究所の会場での開催は行いません。
WEB会議システムを利用した参加のみとなります。参加に必要な設定URL・PWD
については、参加をご希望される方宛に別途ご連絡をいたしますので、共同利用担当宛
(k-kyodoriyo@eri.u-tokyo.ac.jp)お問い合わせください。
なお、お知らせする設定URLの二次配布はご遠慮ください。また、著作権の問題があ
りますので、配信される映像、音声の録画、録音を固く禁じます。
記
日 時 令和2年11月20日(金)午後1時30分~
インターネット WEB会議
1. 13:30-13:45
演題:Harmonic tremor model during the 2011 Shinmoe-dake eruption, Japan
【所長紹介(受入教員:市原美恵)】
著者:○武尾 実(気象庁)
2. 13:45-14:00
演題:シミュレーションによる釜石沖繰り返し地震の予測実験の検証
著者:○吉田真吾・加藤尚之・福田淳一・五十嵐俊博
要旨:Yoshida et al. (2016, EPS)で行った、論文発表後の釜石沖繰り返し地震の
予測について検証する。
3. 14:00-14:15
演題:日本海における確率論的津波ハザード評価
著者:〇Iyan E. MULIA、石辺岳男(地震予知総合研究振興会)、佐竹健治、
Aditya Riadi GUSMAN (GNS Science)、室谷智子(国立科学博物館)
要旨: 日本海東縁部の活断層による、沿岸での再来期間100年、400年、1000年の最大の
津波高さや、各沿岸での津波に寄与する活断層を明らかにした。
4. 14:15-14:30
演題:高分解能反射法地震探査による中央構造線活断層系(四国地域)の浅部~深部形状
【2019年度所長裁量経費報告】
著者:〇石山達也・加藤直子・佐藤比呂志、越谷 信(岩手大学)、
松原 誠(防災科学技術研究所)、 石川正弘(横浜国立大学)
要旨:新たな高分解能反射法地震探査により推定された中央構造線活断層系(四国地域)の
浅部~深部形状とその地質学的意義について報告する。
○発表者
※時間は質問時間を含みます。
※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。
〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1
東京大学地震研究所研究支援チーム
E-mail:k-kyodoriyo@eri.u-tokyo.ac.jp
※次回の談話会は令和2年12月18日(金)午後1時30分~です。