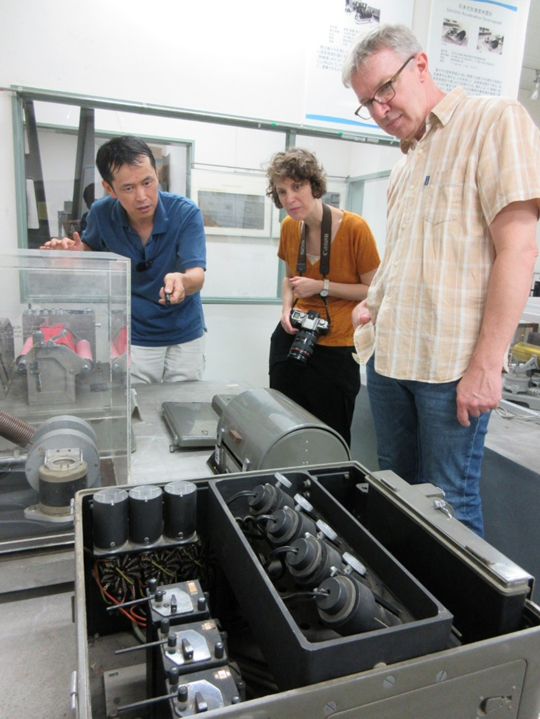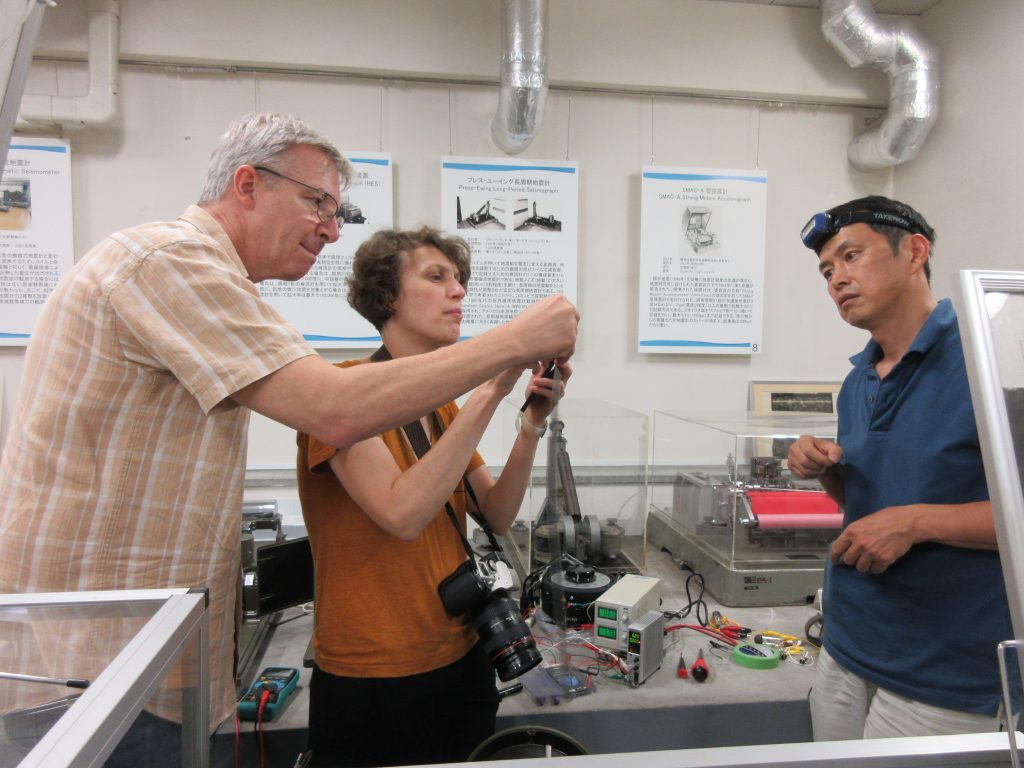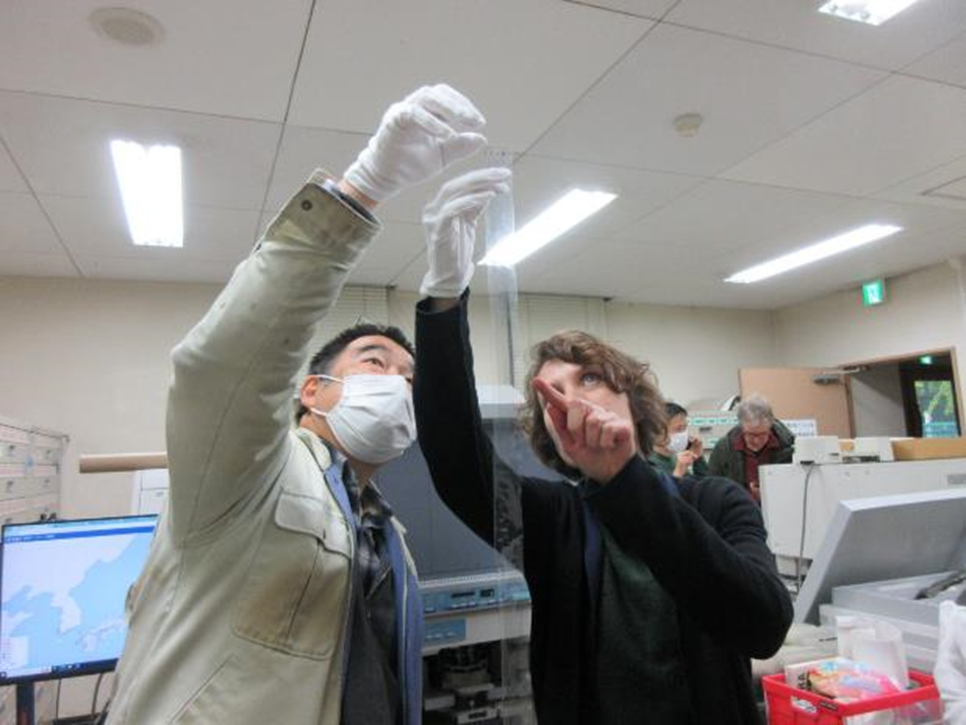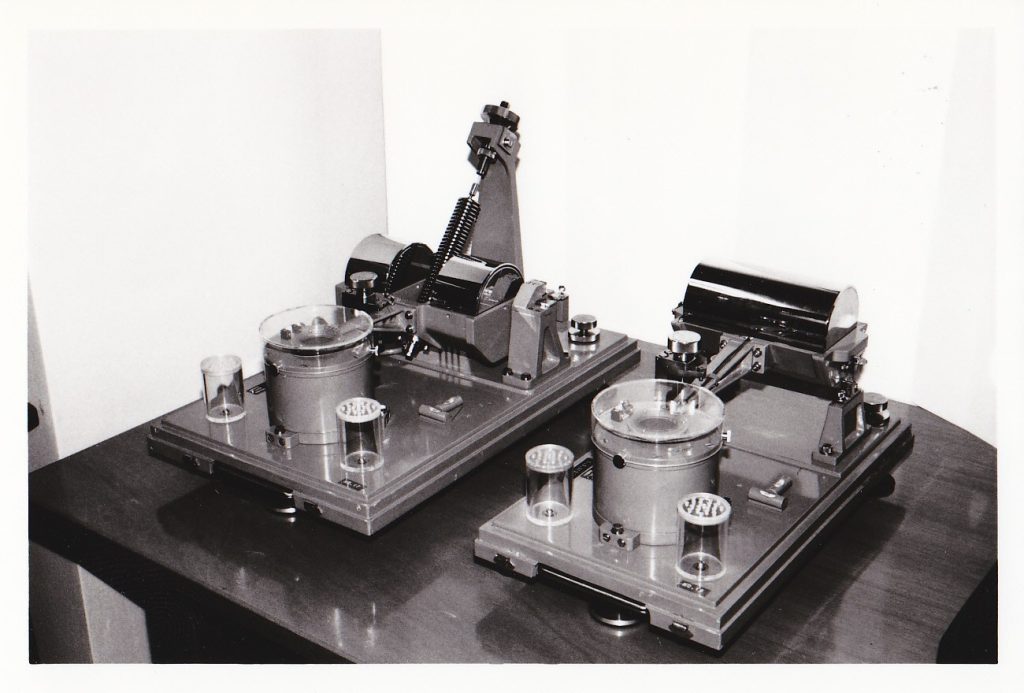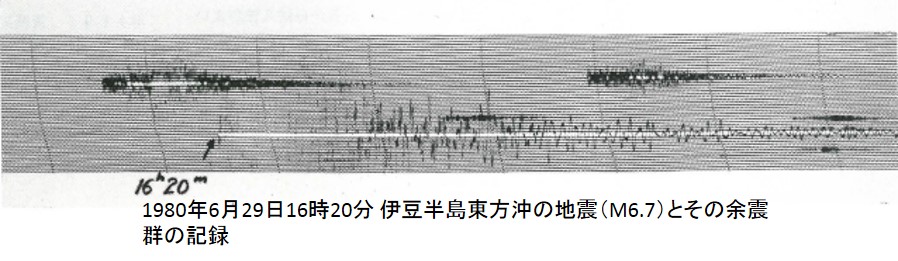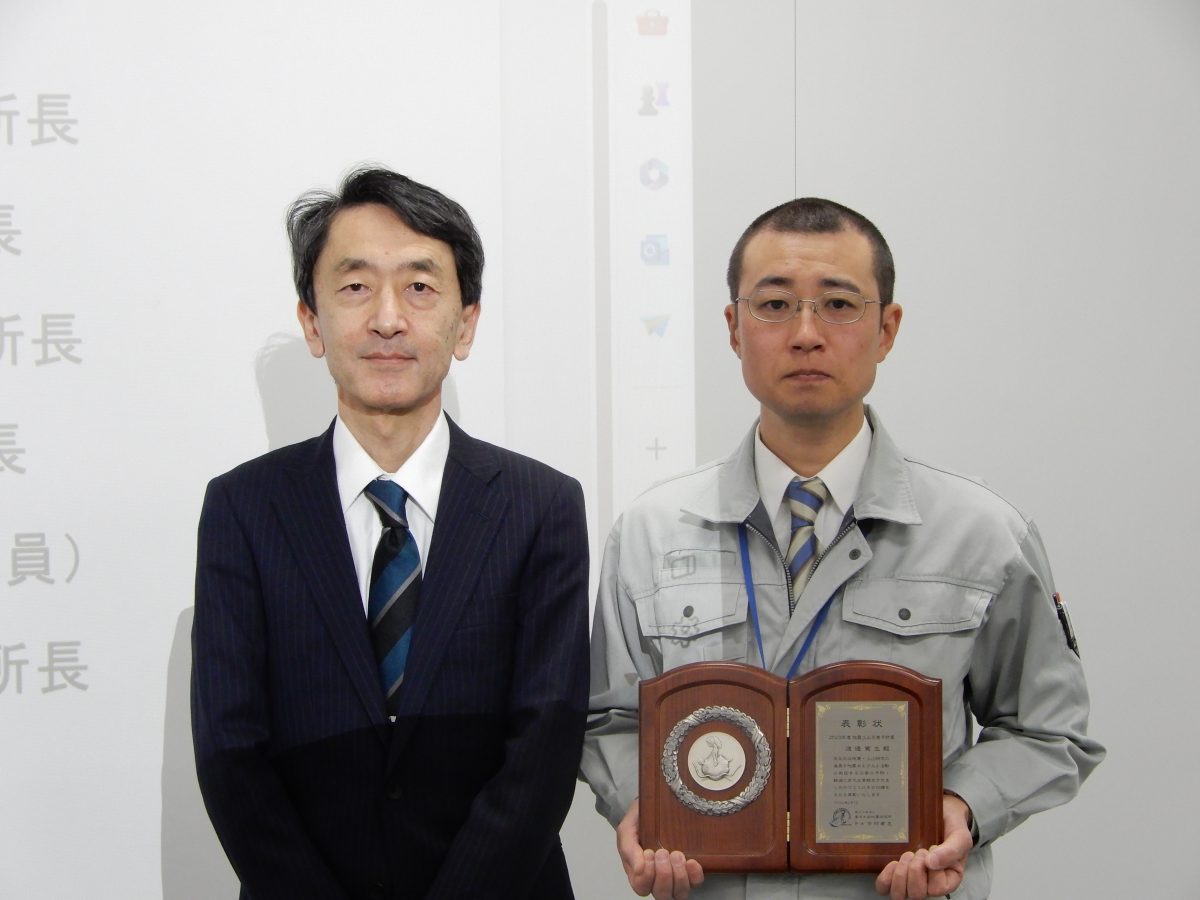下記のとおり地震研究所談話会を開催いたします。
ご登録いただいたアドレスへ、開催当日にZoom URLとパスワードをお送りいたします。
なお、お知らせするZoom URLの二次配布はご遠慮ください。また、著作権の問題が
ありますので、配信される映像・音声の録画、録音を固く禁じます。
記
日 時: 令和6年3月22日(金) 午後1時30分~
場 所: 地震研究所1号館2階 セミナー室
Zoom Webinarにて同時配信
1. 13:30-13:45
演題:噴火した火山混合物のガス推力領域の流体力学に対する多相効果 【地震研特任研究員成果報告】
著者:○Deboprasad TALUKDAR・Yujiro SUZUKI
要旨:Elucidate the effect of solid particle concentration (volume fraction) and size (diameter) on the background gas phase velocity of a polydisperse jet.
2. 13:45-14:00
演題:Oldest-2アレイ観測:太平洋最古の海洋底でのリソスフェア・アセノスフェアシステム研究のための第2回海底観測【所長裁量経費成果報告】
著者:○一瀬建日・馬場聖至、Ban-Yuan KUO(Academia Sinica)、 PeiYing Patty LIN (National Taiwan Normal University)、 Wu-Cheng CHI(Academia Sinica)、 Chen-Hsiang HUNG (National Taiwan Normal University)、 Ding-Jiun LIN (National Central University), Hogyum KIM (Seoul National University)、竹内 希・川勝 均・塩原 肇・歌田久司・ 清水久芳・森重 学・臼井嘉哉, onboard scientists of 2022/2023 Oldest-2 cruises by R/V Legend
要旨:Oldest-2観測の設置回収航海の結果について報告する.
3. 14:00-14:15
演題:三浦半島断層群・相模トラフ調査観測プロジェクト【R4年度所長裁量経費報告】
著者:○石山達也・三宅弘恵・古村孝志
4. 14:15-14:30
演題:情報科学-固体地球科学融合研究プロジェクト部 活動報告 【所長裁量経費成果報告】
著者:〇長尾大道・情報科学-固体地球科学融合研究プロジェクト部メンバー
要旨:文部科学省「情報科学を活用した地震調査研究プロジェクト」(STAR-Eプロジェクト)における今年度の研究成果のほか、今年度から始動したカリフォルニア工科大学との国際連携について報告する。
5. 14:30-14:45
演題: ディープラーニングを用いた地震波形予測,シミュレーション,生成
著者:〇仲田理映、Pu REN(LBNL)、 Dongwei LYU(UC Berkeley)、Zhengfa BI(LBNL)、Maxime LACOUR(UC Berkeley)、仲田典弘(LBNL, MIT)、Benjamin ERICHSON(ICSI)、Michael MAHONEY(UC Berkeley, ICSI, LBNL)
○発表者
※時間は質問時間を含みます。
※既に継続参加をお申し出いただいている方は、当日zoom URLを自動送信いたします。
※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。
〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1
東京大学地震研究所 共同利用担当
E-mail:k-kyodoriyo(at)eri.u-tokyo.ac.jp
※次回の談話会は令和6年4月26日(金) 午後1時30分~です。