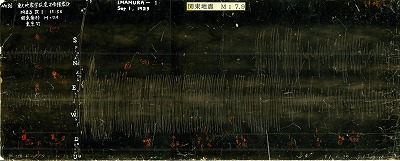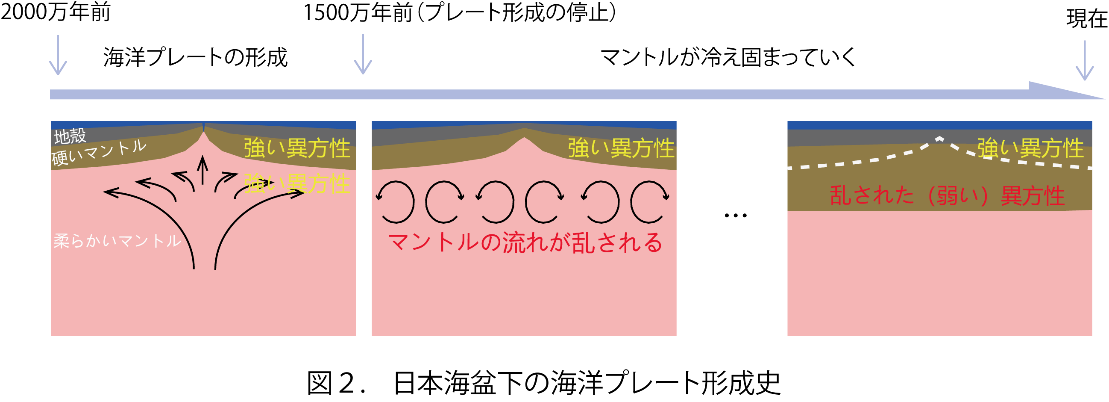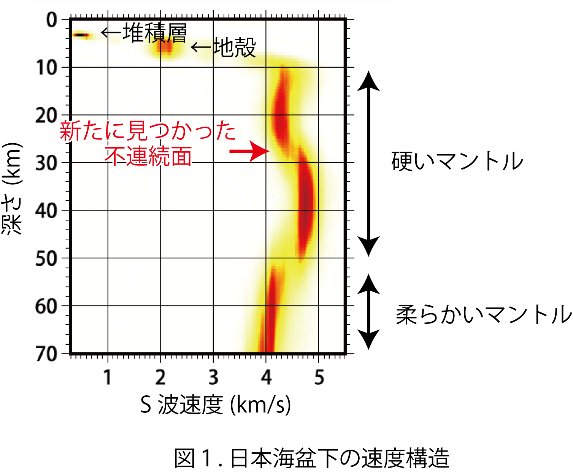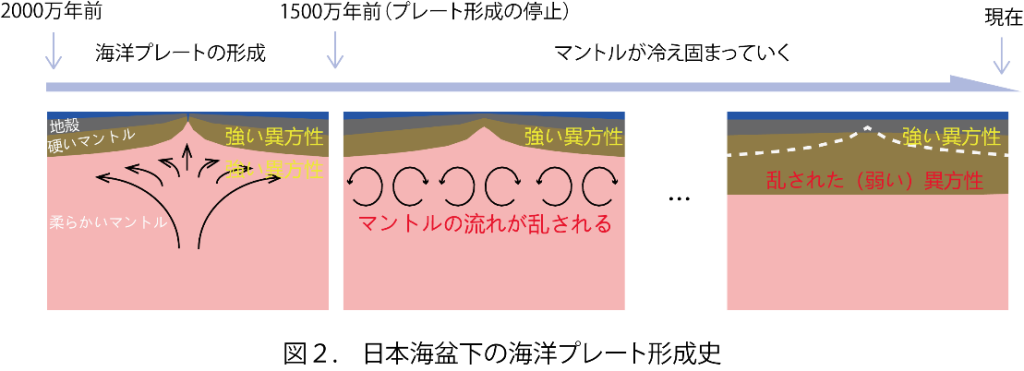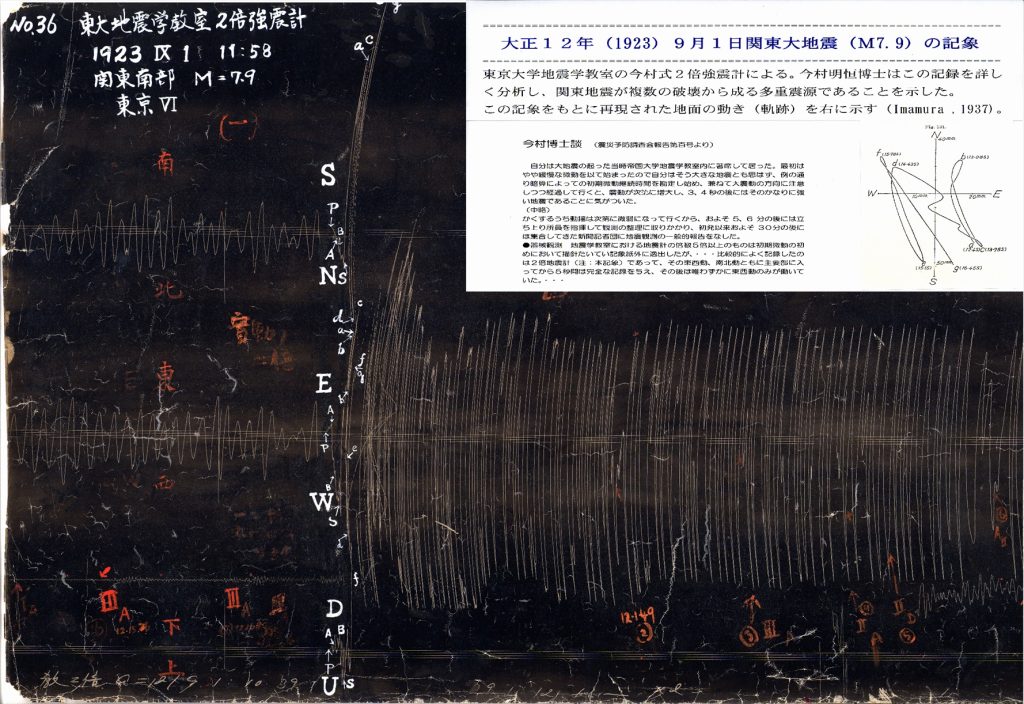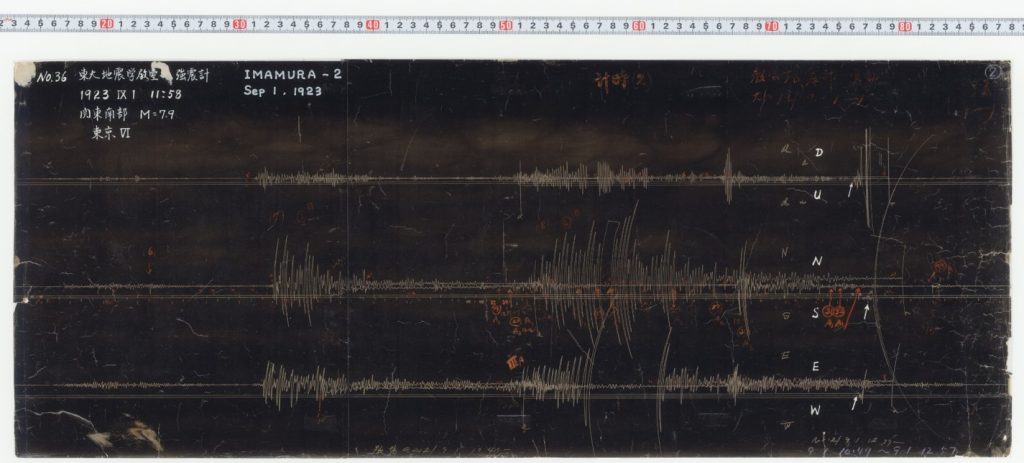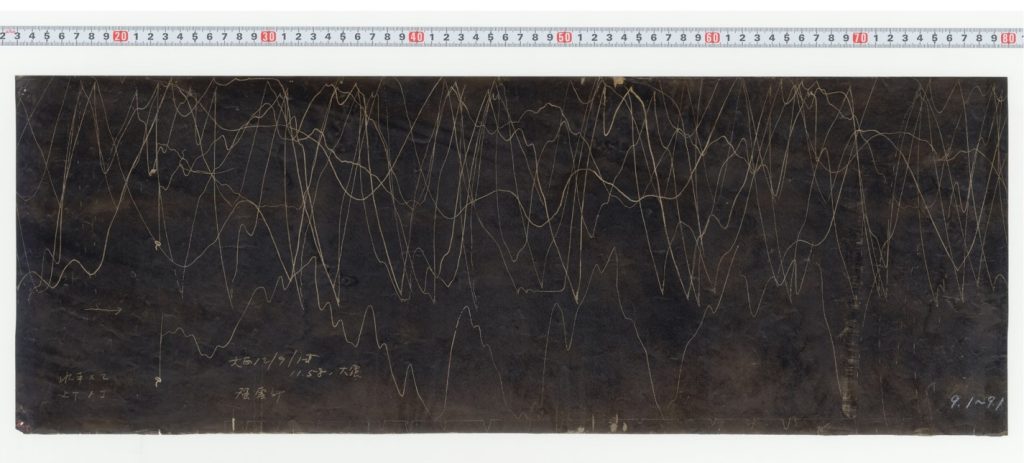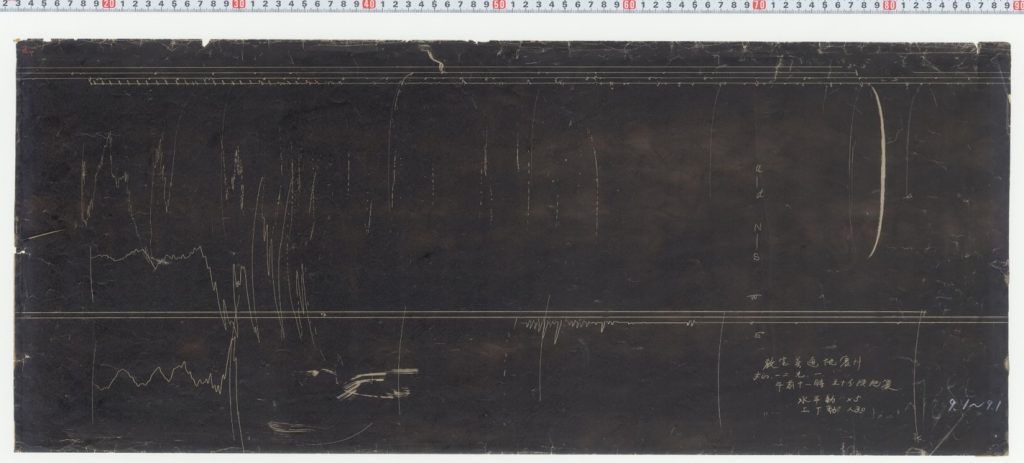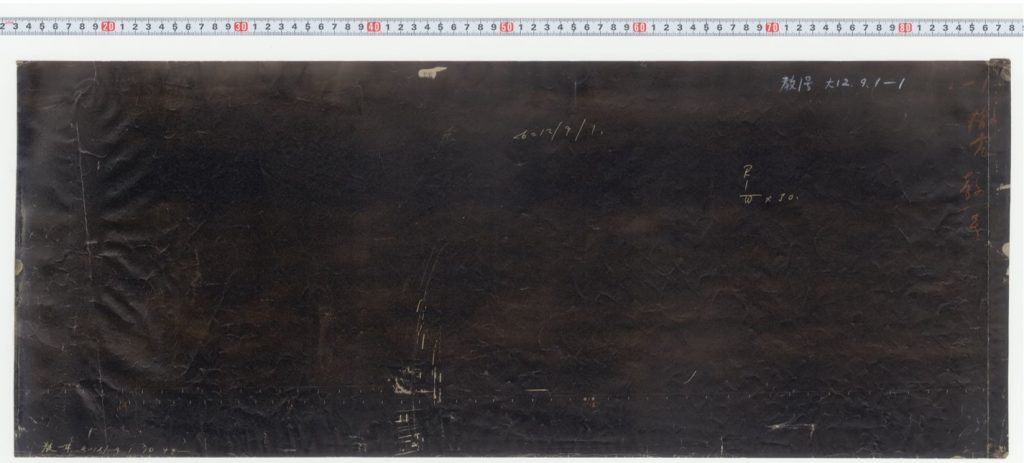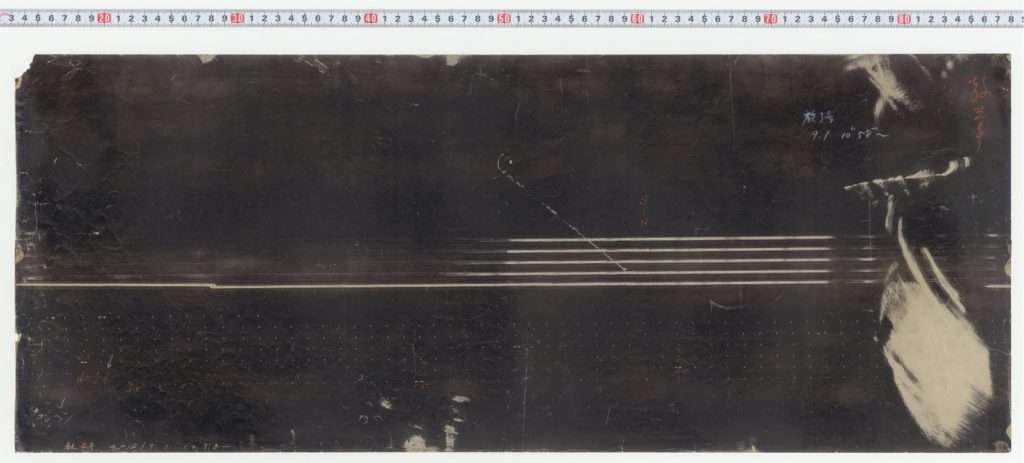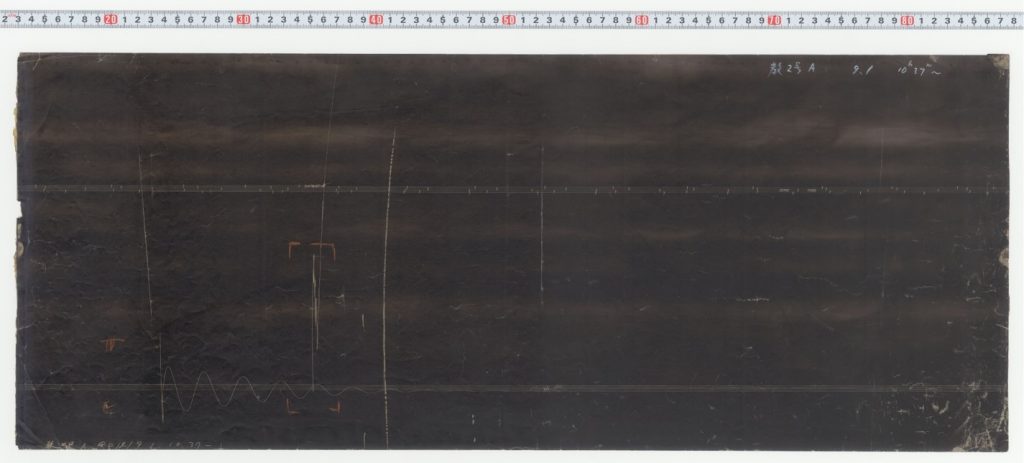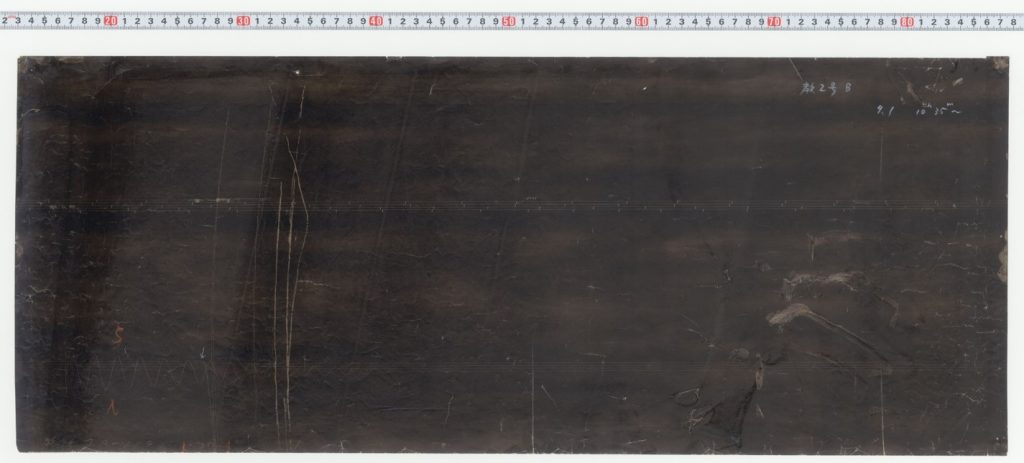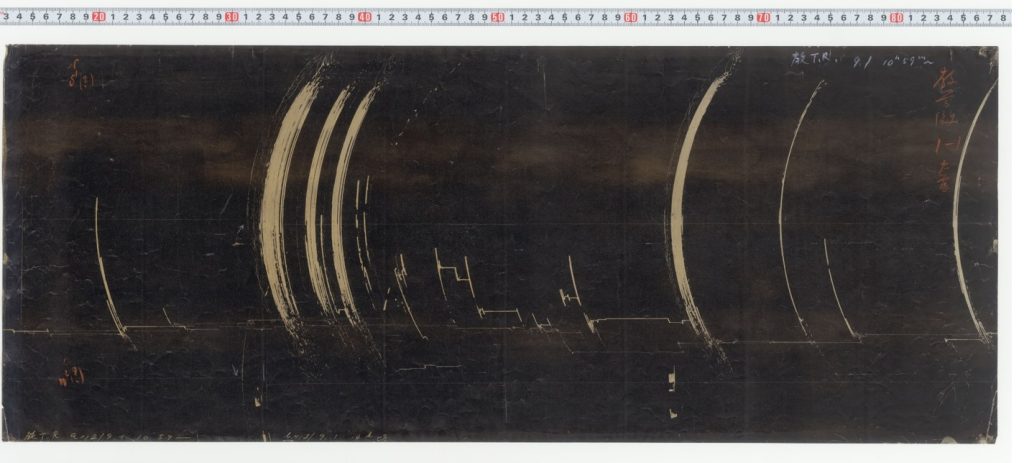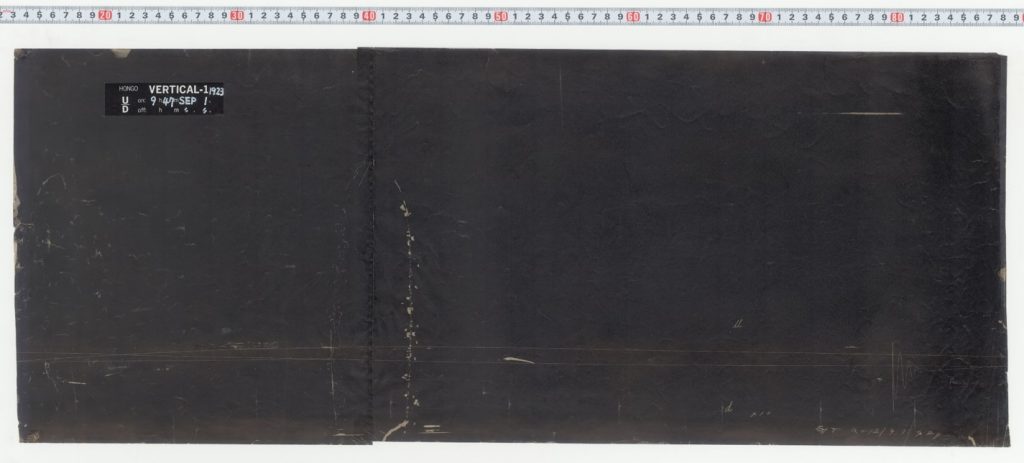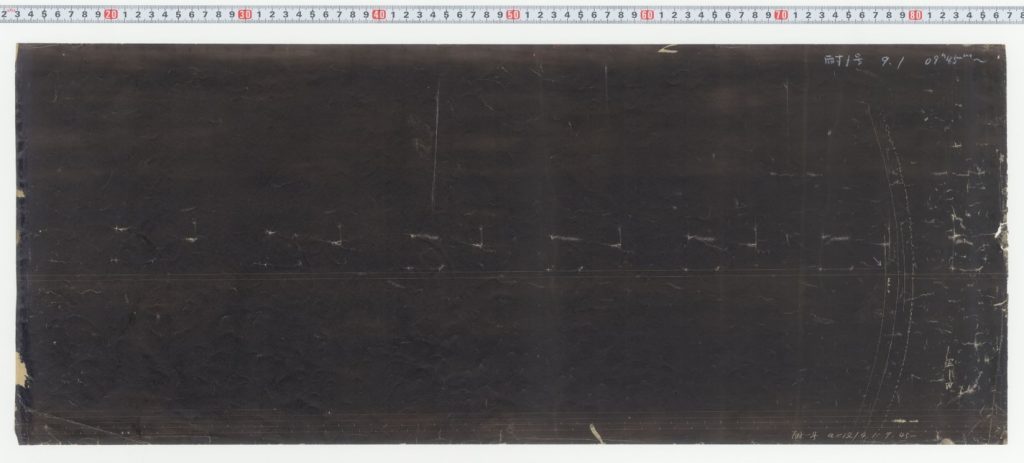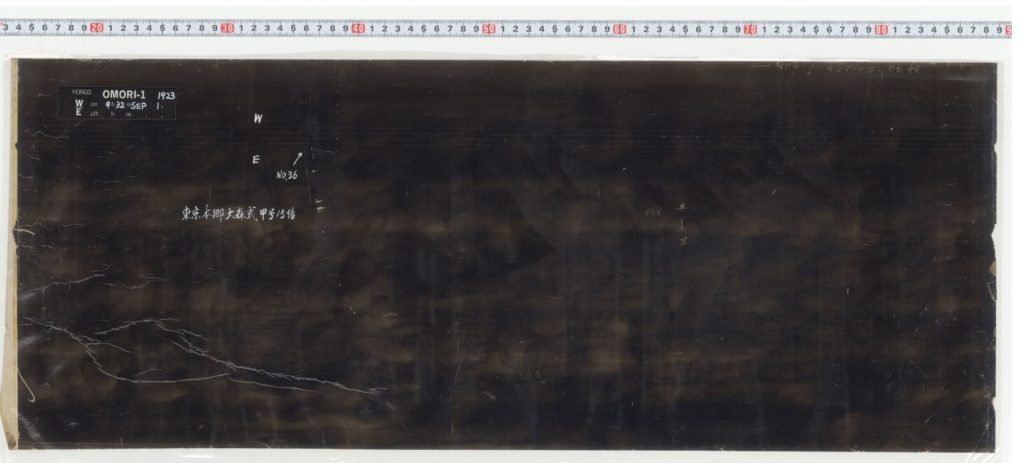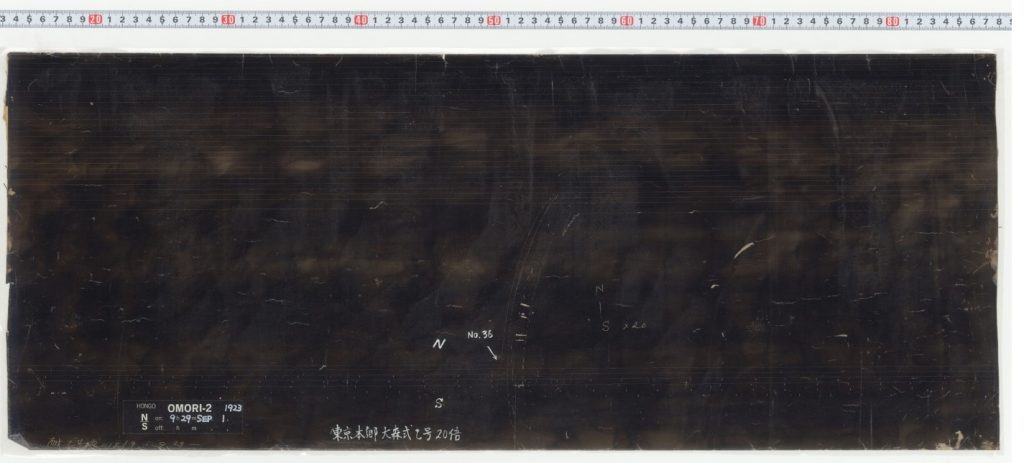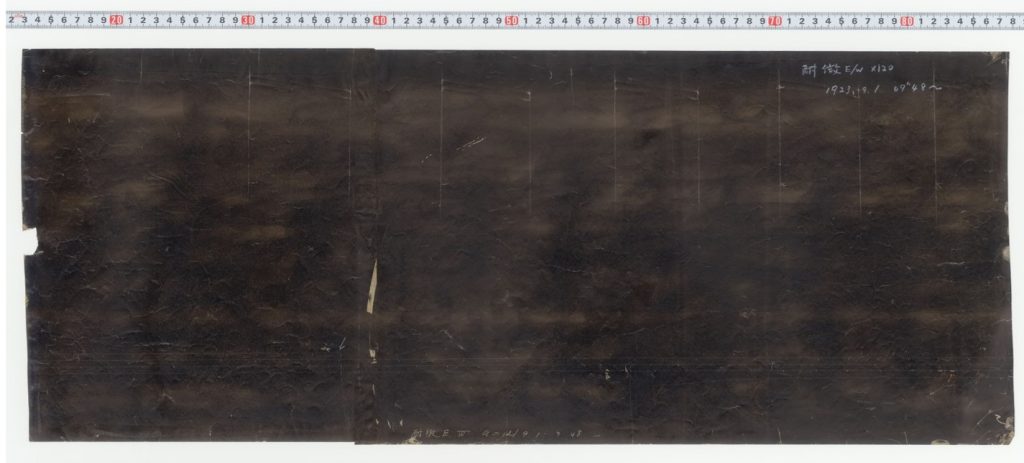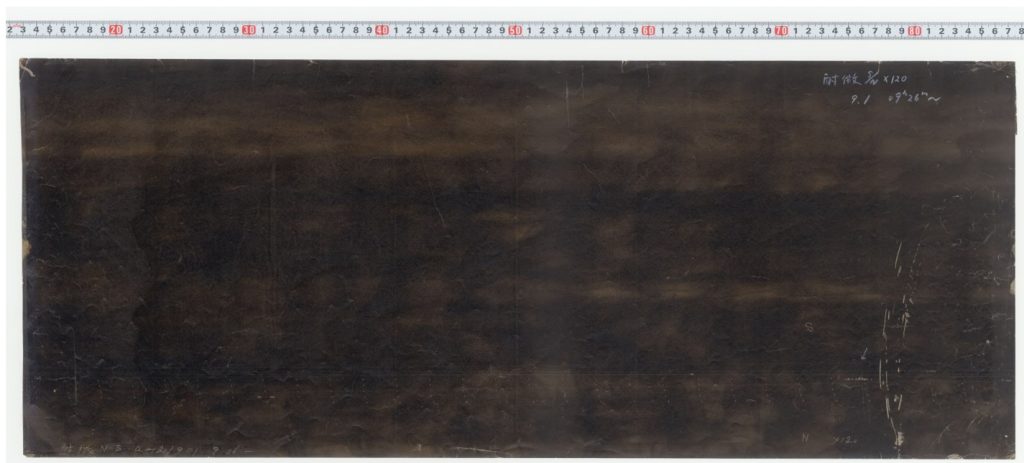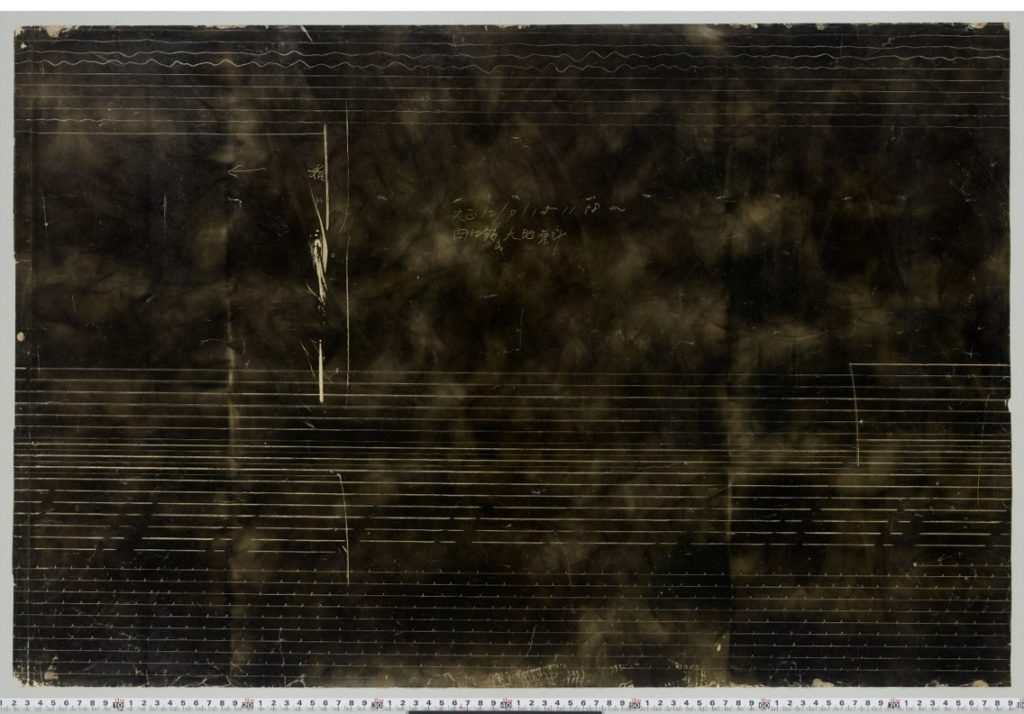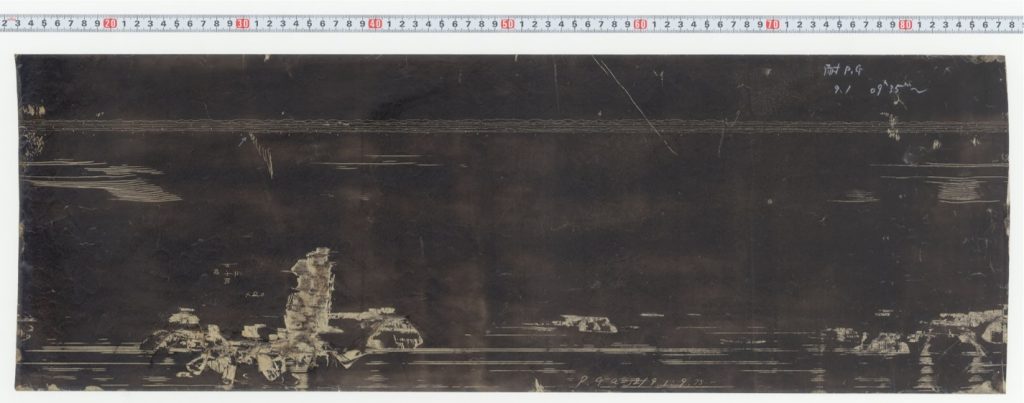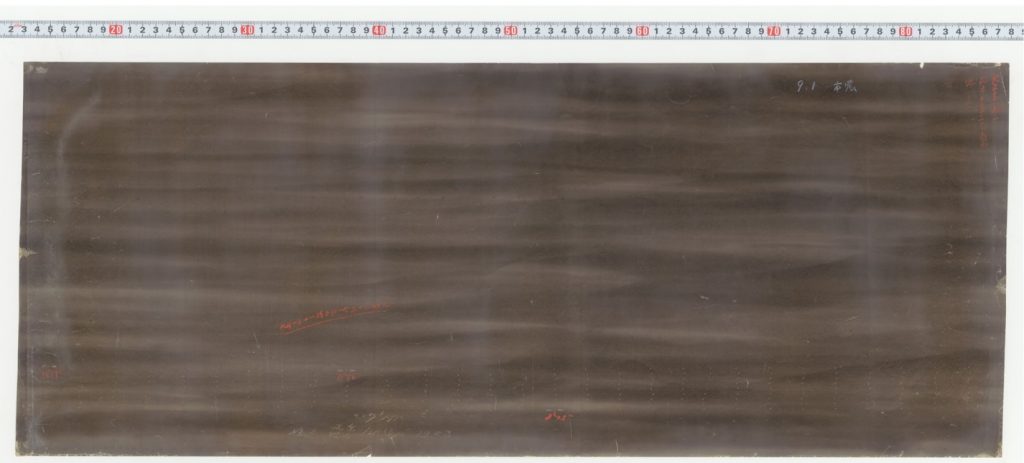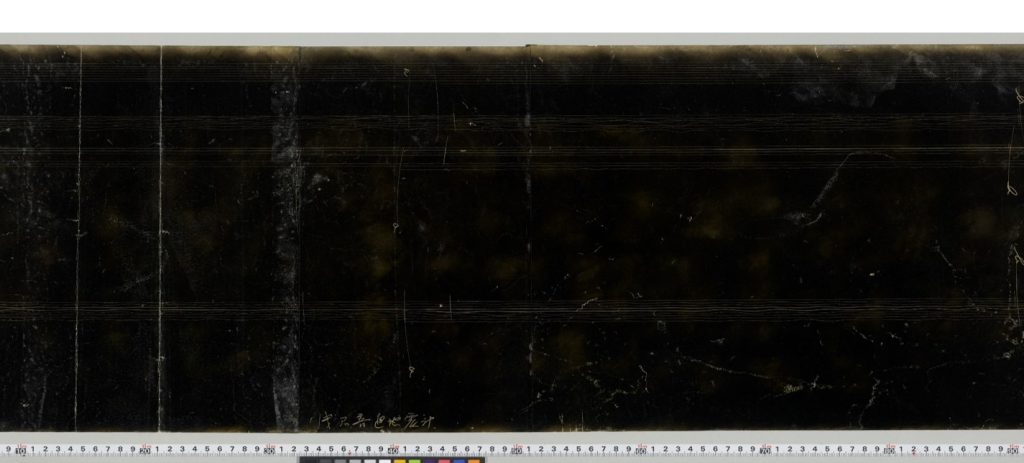下記のとおり地震研究所談話会を開催いたします。
ご登録いただいたアドレスへ、開催当日午前中にURL・PWDをお送りいたします。
なお、お知らせするzoomURLの二次配布はご遠慮ください。
ありますので、配信される映像・音声の録画、録音を固く禁じます。
記
日 時: 令和5年4月21日(金) 午後1時30分~
開催方法: インターネット WEB会議
1. 13:30-13:45
演題:トルコ・シリア地震災害調査速報
著者:○楠 浩一・毎田悠承、真田靖士(大阪大学)、日比野 陽(名古屋大学)
要旨:2023年トルコ―シリア地震に対して派遣された科学研究費補助金、日本建築学会、土木学会の合同調査団の災害調査速報を行います。
2. 13:45-14:00
演題:地震背景ノイズレベルの増大によって検知される長期間の噴火前駆過程:霧島山新燃岳の例
著者:○市原美恵・大湊隆雄、Kostas I. KONSTANTINOU (台湾中央大)、山河和也(山梨県富士山研)、渡邉篤志・武尾 実
3. 14:00-14:15
演題:深層学習を用いた地震波自動処理
著者:○加藤 慎也、 飯尾 能久・片尾 浩・澤田 麻沙代・冨阪 和秀・水島 理恵(京都大学防災研究所)
要旨:開発した深層学習を用いた地震波解析(走時読み取りや極性決定など)の自動化パッケージの紹介をする。
○発表者
※時間は質問時間を含みます。
※既に継続参加をお申し出いただいている方は、当日zoomURLを自動送信いたします。
※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。
〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1
東京大学地震研究所 共同利用担当
E-mail:k-kyodoriyo(at)eri.u-tokyo.ac.jp
※次回の談話会は令和5年5月19日(金) 午後1時30分~です。


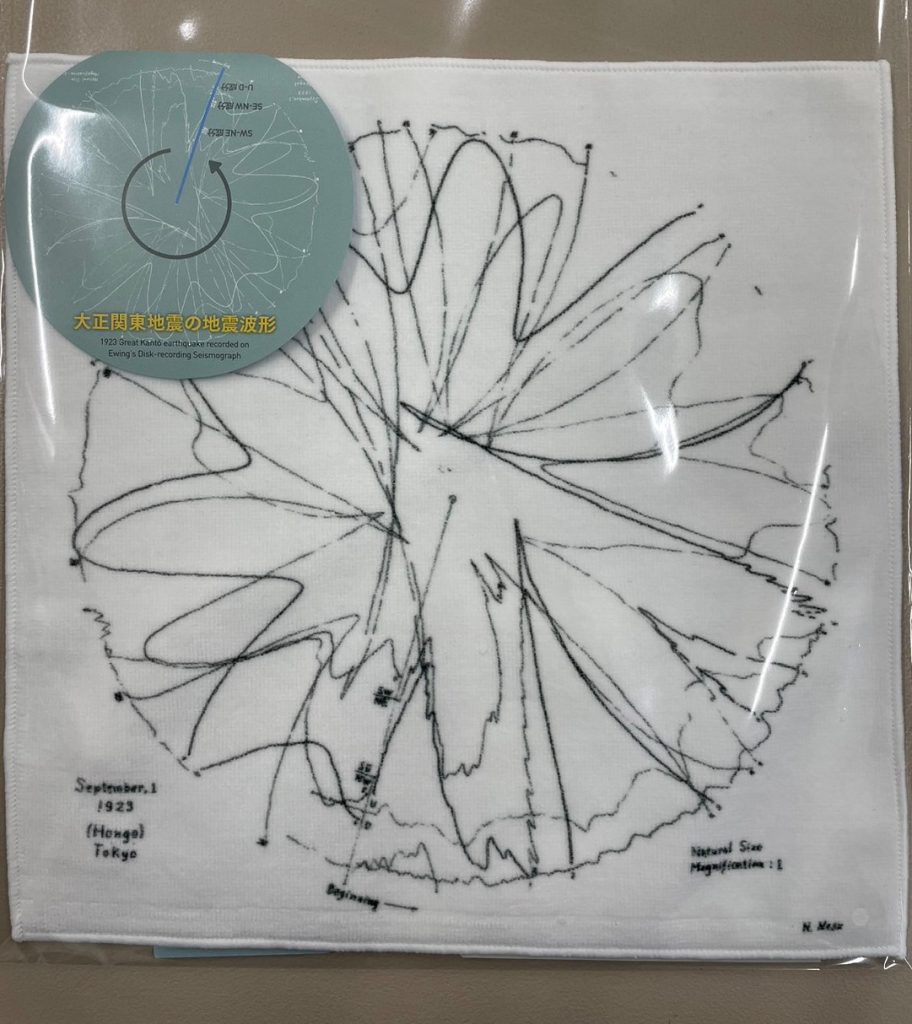

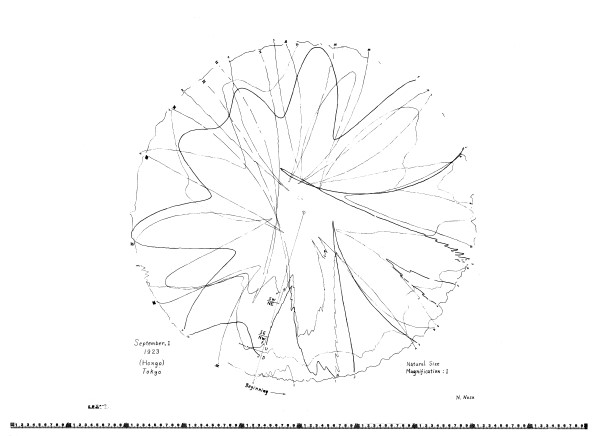

.jpg)