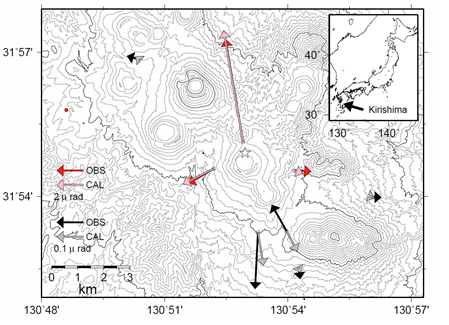2015年4月25日に発生したネパール・ゴルカ地震(Mw7.8)は,インド-オーストラリアプレートとユーラシアプレートの境界で発生した逆断層型の地震である.ゴルカ地震の震源断層の形状を明らかにすることは,衝突帯のテクトニクスを理解する上で重要である.そこで,2015年以降,トリブバン大学,ネパール科学技術院,山形大学との共同研究を進めている.2019年に自然地震を用いた反射法の解析により,震源断層の形状を高い精度で明らかにした(Kurashimo et al., 2019).本震時における断層面上のすべり量が大きな領域は,地震波トモグラフィによる速度構造では,High Vp, High Vp/Vsの特徴を示す領域と対応している.2020年度の自然地震観測は新型コロナウィルス蔓延のため,中止せざるを得ない状況ではあるが,解析作業は継続している.
「部門・センターの研究活動」カテゴリーアーカイブ
3.5.11 富士川河口断層帯の重点的な調査観測
富士川河口断層帯は,日本列島の陸域では最大クラスの平均変位速度が明らかにされている大規模な断層帯である.伊豆衝突帯の西縁に位置し,フィリピン海プレートのプレート境界断層の陸上延長に相当する.このことから,本断層帯は陸上の活断層としての重要性のみならず,南海トラフで発生する海溝型地震の長期評価にも影響を与える.さらに,本断層帯は人口稠密域かつ大規模経済圏を繋ぐ動脈上に位置していることから,本断層帯から発生する地震像を明らかにしていくことは社会的にも重要な課題である.この様な背景に基づき,2017年度から3ヶ年で,構造探査に基づく震源断層システムの解明・活断層システムの分布・形状と活動性・地震活動から見たプレート構造・史料地震調査・強震動予測・地域研究会をサブテーマとする調査研究を行った.2020年には,本プロジェクトのとりまとめを行った.駿河湾横断地殻構造探査によって明らかになったプレート境界断層の海底断層は,陸上の富士川河口断層帯に連続することが明らかになった.また,陸域では浅層反射法地震探査とボーリング・トレンチ調査により,沈み込み帯の先端部で特徴的なスラストの伏臥状構造や前面の断層の通過位置・活動特性を明らかにすることができた.
3.5.10 日本海地震・津波調査プロジェクト
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う大津波は,日本列島の広汎な領域に極めて甚大な人的・物的な被害を及ぼし,防災対策の見直しが必要になっている.日本海側には,津波や強震動を引き起こす活断層が多数分布している.このことを背景として,文部科学省の「ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究(2007〜2012年)」において新潟沖〜西津軽沖にかけての領域を対象に調査観測を進め,震源断層モデルを構築した.しかし,それ以外のほとんどの地域については,震源断層モデルや津波波源モデルを決定するための観測データが十分に得られていない.こうした問題点を解決するために,2013年度より「日本海地震津波調査プロジェクト」が開始された.本プロジェクトでは,日本海の沖合から沿岸域及び陸域にかけての領域で,津波の波高予測を行うのに必要な,日本海の津波波源モデルや沿岸・陸域における震源断層モデルを構築するための観測データを取得する.また,これらのモデルを用いて,津波・強震動シミュレーションを行い,防災対策をとる上での基礎資料を提供するとともに,地震調査研究推進本部の実施する長期評価・強震動評価・津波評価に資する基礎データを提供する.また,このような科学的側面に加えて,津波や強震動による被害予測に対する社会的要請の切迫性に鑑みて,調査・研究成果にもとづいて防災リテラシーの向上を目指して,地域研究会を立ち上げ,行政と研究者間で津波や強震動による災害予測に関する情報と問題意識の共有化を図っている.
2020年度には,津軽半島南部を東西に横断する区間で地殻構造探査を実施し,基本的な地殻構造の他,測線周辺の活断層や震源断層の形状を明らかにした.とくに,津軽平野西端の伏在活断層を見いだし,1766年明和津軽地震に相当する震源断層を明らかにした.2020年度は,本プロジェクトの最終年度にあたり,日本海と沿岸域の震源断層の矩形モデルをとりまとめた.これらの矩形断層モデルをもとに,日本海沿岸での津波予測をおこなった.大和海盆と日本海盆で実施してきた広帯域海底地震計を含む地震観測記録の解析により,日本海海域下のリソスフェアーの厚さを明らかにした.海陸統合地殻構造探査の成果と併せて,日本海東縁から日本海側にひずみが集中する基本的なメカニズムが明らかになった.日本海側の平野下の新たに見いだした伏在活断層を含め,震源断層モデルを構築した.被害地震発生の中期予測のための基礎資料をえるために,プレート形状を含め上盤プレートのモデル化を行い,測地データや発震機構から推定される応力状態のデータを基に,断層面に作用するクーロン応力の変化を求めた.こうした成果は,日本海沿岸の道府県での研究会を通じて広報された.
3.11.8 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト:サブプロジェクト(b)「官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備」
2017年から「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」が開始された.このプロジェクトは,3つのサブプロジェクトからなり,その中のサブプロジェクト(b) 「官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備」の一部を地震研究所で担当している.これまでに解明を進めてきた首都圏の地震像の精緻化や都市の詳細な地震被害評価に資するものにするため,政府関係機関が保有する,首都圏に整備された稠密かつ高精度な地震観測網(MeSO-net)と全国規模の地震観測網(K-NET,Hi-net等)により得られるリアルタイムの観測データ,民間が保有する地震観測データを統合した超高密度地震動観測データを収集・整備することを目標としている.
具体的には,MeSO-net等で収集された高密度な地震観測データを利用して,首都圏の地震ハザード評価に資する首都圏中心部や伊豆地域における詳細な地下構造の提案,首都圏における過去~現在の地震像の解明,将来の大地震による揺れの予測手法の開発,統合された地震観測データを用いてノイズレベルの高い首都圏でも適用可能な自動震源決定手法の高度化,歴史地震による揺れの分布の再現,3 次元階層化地震活動予測モデルを開発等の研究を行っている.
今年度は,これまでに得られた地震記録による読み取り値を用いて地震波速度異方性構造を推定し,首都圏下に沈み込むフィリピン海プレートの構造を明らかにした.等方性の地震波速度だけではなく,速度異方性の情報を加えたことで,プレート境界のみならず,沈み込むプレート内に関する詳細な特徴を得ることができた.その結果は,現在の地震活動と比較することができ,プレートの生成,変形,運動等の解明に大きな影響を与える.それは,今後発生すると考えられている首都圏の大地震の地震像を想定する際に,重要な要素の一つになる.
大地震が発生した際の地震波による地表面の揺れは,必ずしも均質ではなく,地域によって異なっている.揺れは,地震波減衰構造や地盤特性等に大きく影響されるためであり,細かな地点ごとの情報があれば,そこから算出することが可能である.しかし,詳細な被害分布を推定するには,まだ地下構造の情報が足りない.そこで,これまでに観測された地震動を用いて,相対的な地点ごと揺れの特徴を求めた.その情報をもとにして,面震源(断層)を仮定した際の震度分布推定アルゴリズムのプロトタイプを開発した.
大地震の発生は大きな被害をもたらすが,その頻度は高くなく,その情報は限られている.そのため,大地震の地震像やその被害状況を知るためには,過去に遡って古文書等から読み解く必要があり,これまでに多くの文献が収集されてきた.被害の記述から被害の程度を判定し,その分布から震源の位置や地震の規模等を知ることができた.ただ,その震度は,震源から同心円状に分布するわけではなく,地域による不均質がみられる.地下構造や地盤特性の影響と考えられるが,それを現在の地震の震度分布と比較するために,震度のデータベースを作成している.具体的には,古文書に書かれている被害地点を古地図の中から探し出し,位置を特定する.そして,その地点に地震計を設置し,現在の地震による揺れを観測する.古文書に記述されていない地点でも同時に観測することで,相対的な震度を推定することができ,震度分布の密度を高めることが可能になり,歴史地震の地震像を推定する際の重要な情報の一つとすることが期待される.
近年に発生した大地震の本震発生前後の地震活動を統計モデルで解析し,余震活動の収束性や本震に至る地震活動の特徴の解析を継続して行い,統計モデルの高度化をはかっている(例えば岐阜・長野県境の地震).